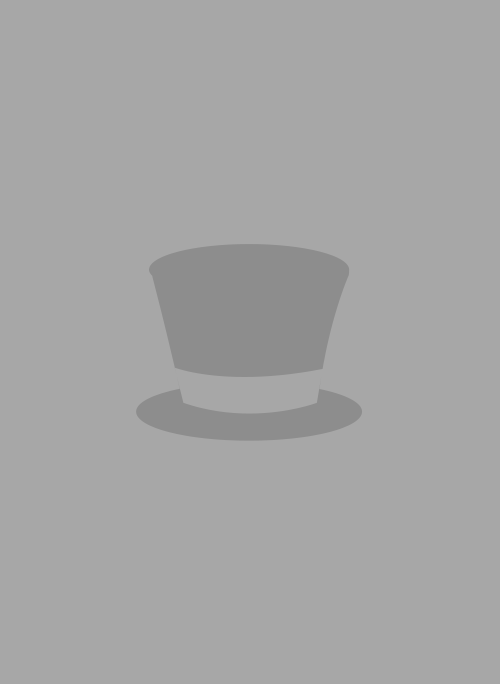〇月◎日(晴れ)午前七時
いつもは心地よい日差しを受けて目を覚ますのだが、今日はすこし違った。
耳障りな鳥たちの声に起こされたのだ。目を開けてようやく昨晩のことを思い出した。
あの後、姿を消した父を見つけることは出来なかった。別れて悲しいとか寂しいとか、そういった感情はあまりわかなかった。
突然、父親だと紹介されて、実感もわかないまま、別れたのだから仕方がない。
ただ、腹が満たされたことは父に感謝した。縁があればまた会えることも願って。
そして、焼き鳥屋の倉庫を見つけて中に入り、そのまま寝てしまったのだ。耳障りな鳥の声は、ハト小屋にいるハトたちである。
「おい、ピヨいるか。外に出るぞ」
倉庫の中は薄暗いが、俺は猫だ。近くで寝ていたピヨに声をかけると、難なく外に出た。ピヨはというと、寝ぼけ眼で遅れて出てくる。そういえば、鳥族って暗いのは苦手だったんだっけ。何となく、勝てたという優越感に浸れた。
「さて、クロたちに見つかっても喧嘩はうられないだろうけど、帰るにしても距離があるんだよな」
来た時と同じように橋を渡るのが最短距離なのだが、足が弱そうな父がいたから、その道を選んだのだ。帰りは交通量が少ないところを通りたい。危険は避けたいからな。
ふと、駐車場の方を見ると、そこに見慣れた車があることに気づいた。
「朝飯をもらっている魚屋の車じゃないか。近くまで配達しているんだな……よし、いいことを思いついたぞ。ピヨ、あの車の荷台に乗って帰ろう」
ピヨも賛成のようで首肯する。見つからないようにしなければいけないが、その心配もなさそうだ。荷台を見てみると段ボールが数個あり、その陰に隠れられそうだった。
早速、ピヨを背中に乗せて跳び乗る。後は、ひと眠りしていつもの魚屋まで運んでもらえるのを待てばいい。
と、思っていたら人の気配がした。間違いない。魚屋の親父だ。
「ふははっ! 俺はなんて賢い猫さんなんだ。これぞ秘義、隠れタダ乗りだ」
ピヨの視線が突き刺さるように冷たく感じたが、それはここでは気にしないでおこう。
魚屋の親父は荷台を確認することなく、車に乗った。すぐに車が動きはじめ、駐車場を出て大通りへと入る。しかし、そこで思わぬ事態が起きた。車は橋を渡ることなく、逆方向へと走りはじめたのだ。
「えええっ! 魚屋の親父、停めてくれ。俺が行きたいのはそっちじゃない」
慌てて飛び降りようとしても下は車道だ。後続車に轢かれるかもしれないし、飛び降りた衝撃で怪我をするかもしれない。
「俺は猫だから着地には自信があるとしても……この高さじゃあ、ピヨがな」
ピヨは鳥だが、まだヒナだから飛べない。いろいろ考えたが、このまま暴れても意味がないと思い、車が停まるまで、じっとしていることにした。
車は速度を増し、ビルがあった景色から徐々に建物がすくなくなっていく。一時間後には、山だらけの景色になった。隣にいるピヨの視線が何かを訴えているようで痛い。
すっごく不安になってきた。俺はシティー派なんだ。空気が美味いのはいいとは思うが、田舎の永住なんてごめんだ。しかし、その想いも美味い空気の中に消え、更に車は海沿いを走り、峠を越えていく。
最終的に、車が停まった場所は田園広がる超がつくほどの田舎だった。
魚屋の親父が車のエンジンを切って降りる。そして、平屋に向かうと呼び鈴のボタンを押していた。玄関から出てきたのは女性だった。
「よく来たね。今回は一週間いられるんだっけ?」
「ああ、留守中の仕事は店の若い衆に頼んだよ。じゃあ、作業をするか」
そういった魚屋の親父は家の裏へと姿を消した。高枝切りバサミをもってきたので、この一週間は庭の手入れをするのだろう。
今なら、降りても気づかれなさそうだ。ピヨを背中に乗せて荷台から飛び降りる。
とはいえ、無事に降りることはできたものの、餌の調達はしなければいけない。日も真上近くにあるので、そろそろ昼といったところか。今から餌場を捜さないと夕食にありつける可能性は低くなる。
庭を出ると、前にあるのは田園風景だ。しばらく景色を眺めていると、風にのって食べ物の匂いがしてきた。
これは、行くしかない。食欲をそそる強烈な匂いにつられて歩いて行くと、道の脇に肉団子がいくつか置いてあった。こんなご馳走は都会では見たことがないぞ。無意識のうちによだれが一気に口の中に広がる。
「俺ってすごい運がいいのかもしれないな。では、持ち主がいないようなので、遠慮なくいただきます」
口を開けて肉団子をいただこうとした、その時だ。
「死になくなければ、その肉団子を食うのはやめな」
まずは聞こえた野太い声。そして、急に目の前に現れた大きな影に食事を邪魔される。
「見たことない顔だな。排気ガスの嫌な匂いもしやがる……」
顔を上げると、強面の大型犬が俺を睨みつけていた。
いつもは心地よい日差しを受けて目を覚ますのだが、今日はすこし違った。
耳障りな鳥たちの声に起こされたのだ。目を開けてようやく昨晩のことを思い出した。
あの後、姿を消した父を見つけることは出来なかった。別れて悲しいとか寂しいとか、そういった感情はあまりわかなかった。
突然、父親だと紹介されて、実感もわかないまま、別れたのだから仕方がない。
ただ、腹が満たされたことは父に感謝した。縁があればまた会えることも願って。
そして、焼き鳥屋の倉庫を見つけて中に入り、そのまま寝てしまったのだ。耳障りな鳥の声は、ハト小屋にいるハトたちである。
「おい、ピヨいるか。外に出るぞ」
倉庫の中は薄暗いが、俺は猫だ。近くで寝ていたピヨに声をかけると、難なく外に出た。ピヨはというと、寝ぼけ眼で遅れて出てくる。そういえば、鳥族って暗いのは苦手だったんだっけ。何となく、勝てたという優越感に浸れた。
「さて、クロたちに見つかっても喧嘩はうられないだろうけど、帰るにしても距離があるんだよな」
来た時と同じように橋を渡るのが最短距離なのだが、足が弱そうな父がいたから、その道を選んだのだ。帰りは交通量が少ないところを通りたい。危険は避けたいからな。
ふと、駐車場の方を見ると、そこに見慣れた車があることに気づいた。
「朝飯をもらっている魚屋の車じゃないか。近くまで配達しているんだな……よし、いいことを思いついたぞ。ピヨ、あの車の荷台に乗って帰ろう」
ピヨも賛成のようで首肯する。見つからないようにしなければいけないが、その心配もなさそうだ。荷台を見てみると段ボールが数個あり、その陰に隠れられそうだった。
早速、ピヨを背中に乗せて跳び乗る。後は、ひと眠りしていつもの魚屋まで運んでもらえるのを待てばいい。
と、思っていたら人の気配がした。間違いない。魚屋の親父だ。
「ふははっ! 俺はなんて賢い猫さんなんだ。これぞ秘義、隠れタダ乗りだ」
ピヨの視線が突き刺さるように冷たく感じたが、それはここでは気にしないでおこう。
魚屋の親父は荷台を確認することなく、車に乗った。すぐに車が動きはじめ、駐車場を出て大通りへと入る。しかし、そこで思わぬ事態が起きた。車は橋を渡ることなく、逆方向へと走りはじめたのだ。
「えええっ! 魚屋の親父、停めてくれ。俺が行きたいのはそっちじゃない」
慌てて飛び降りようとしても下は車道だ。後続車に轢かれるかもしれないし、飛び降りた衝撃で怪我をするかもしれない。
「俺は猫だから着地には自信があるとしても……この高さじゃあ、ピヨがな」
ピヨは鳥だが、まだヒナだから飛べない。いろいろ考えたが、このまま暴れても意味がないと思い、車が停まるまで、じっとしていることにした。
車は速度を増し、ビルがあった景色から徐々に建物がすくなくなっていく。一時間後には、山だらけの景色になった。隣にいるピヨの視線が何かを訴えているようで痛い。
すっごく不安になってきた。俺はシティー派なんだ。空気が美味いのはいいとは思うが、田舎の永住なんてごめんだ。しかし、その想いも美味い空気の中に消え、更に車は海沿いを走り、峠を越えていく。
最終的に、車が停まった場所は田園広がる超がつくほどの田舎だった。
魚屋の親父が車のエンジンを切って降りる。そして、平屋に向かうと呼び鈴のボタンを押していた。玄関から出てきたのは女性だった。
「よく来たね。今回は一週間いられるんだっけ?」
「ああ、留守中の仕事は店の若い衆に頼んだよ。じゃあ、作業をするか」
そういった魚屋の親父は家の裏へと姿を消した。高枝切りバサミをもってきたので、この一週間は庭の手入れをするのだろう。
今なら、降りても気づかれなさそうだ。ピヨを背中に乗せて荷台から飛び降りる。
とはいえ、無事に降りることはできたものの、餌の調達はしなければいけない。日も真上近くにあるので、そろそろ昼といったところか。今から餌場を捜さないと夕食にありつける可能性は低くなる。
庭を出ると、前にあるのは田園風景だ。しばらく景色を眺めていると、風にのって食べ物の匂いがしてきた。
これは、行くしかない。食欲をそそる強烈な匂いにつられて歩いて行くと、道の脇に肉団子がいくつか置いてあった。こんなご馳走は都会では見たことがないぞ。無意識のうちによだれが一気に口の中に広がる。
「俺ってすごい運がいいのかもしれないな。では、持ち主がいないようなので、遠慮なくいただきます」
口を開けて肉団子をいただこうとした、その時だ。
「死になくなければ、その肉団子を食うのはやめな」
まずは聞こえた野太い声。そして、急に目の前に現れた大きな影に食事を邪魔される。
「見たことない顔だな。排気ガスの嫌な匂いもしやがる……」
顔を上げると、強面の大型犬が俺を睨みつけていた。