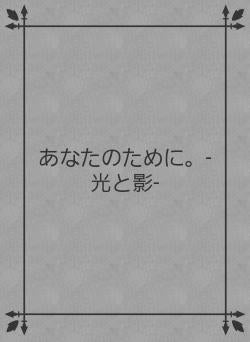保育士さんの言葉を聞いたお義母さんは意外そうに目を少し見開いた。
「アタシ達の頃なんか父親は育児に無関心だったけどねぇ。
男は外出て稼いで、女は家で家事に育児をやってってのが普通だったからね。
そう思うと、最近の男はなかなか気が利いて、いいじゃないか。隅におけないねぇ」
お義母さんはふっと笑って写真を見つめていた。
めったに人を褒めないお義母さんが、最近の父親を褒めた。
実際私がお義母さんに褒められたのは、味噌汁の味がいいことくらい。
世のお父さん、これは誇っていいことですよと全国のお父さんに言ってやりたい。
なんて思っていた私の思考が、お義母さんの次の言葉で停止する。
「アンタもそんな男のところに嫁いだっていんだよ」
「…え?」
食べていたサンドイッチを落としそうになって、持ち直す。
目を見開き、口を開けたままお義母さんを見つめれば、お義母さんの目は真剣だった。
「理人はいつ目が覚めるか分からない。
それどころか、あいつの母親としてこんなことはないと信じたいけど、目が覚めないまま死ぬ可能性だってある。
そんな息子のことを待ち続けるくらいなら、日海とアンタのことを受け入れてくれる男のことろに嫁いだ方がアンタも日海も父親がいて幸せなんじゃないかい?
理人を待ち続けてもし理人が帰らぬ人になったら、アンタも悲しいだろうけど、一番悲しいのは父親のいなくなった日海なんだよ」