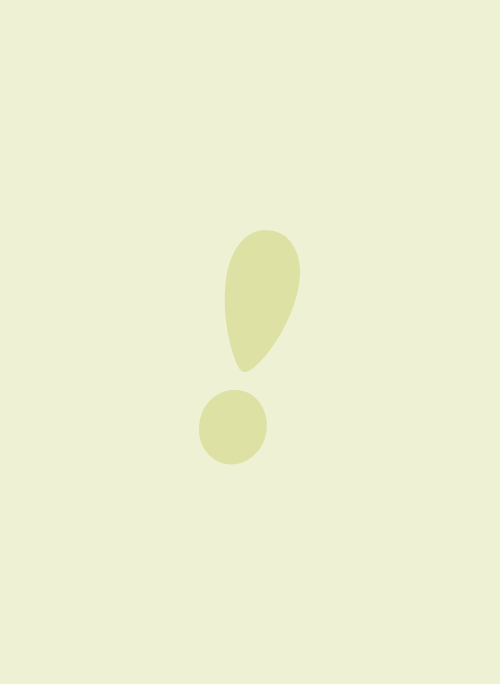「その様子だったら心配はなさそうだな。話もゆっくりできそうだ。もししんどかったら言えよ?いくら話の途中でも…な?」
渚はその言葉を聞いて、一瞬ビクッとした。
きっと聞かれることは手首の怪我のことだろう。
それぐらいの予測は簡単に立てられた。
自動的に自分の行動が思い出される。
そして思い出すと同時に身体中が震えだし、自然に涙が溢れてきた。
急に自分の周りの空気だけが急速に冷やされたかのように、身体の震えはとまらず、コントロールが効かなかった。
自分の頭の中がだんだん恐怖で満たされていくのが分かった
。隼人は渚を落ち着かせるために、すぐに渚を抱きしめた。
その瞬間、渚の身体が一瞬でどれだけ冷やされ、震えていたのかが分かった。
すでに周りの声が聞こえていないだろうという状況だった。
渚はその言葉を聞いて、一瞬ビクッとした。
きっと聞かれることは手首の怪我のことだろう。
それぐらいの予測は簡単に立てられた。
自動的に自分の行動が思い出される。
そして思い出すと同時に身体中が震えだし、自然に涙が溢れてきた。
急に自分の周りの空気だけが急速に冷やされたかのように、身体の震えはとまらず、コントロールが効かなかった。
自分の頭の中がだんだん恐怖で満たされていくのが分かった
。隼人は渚を落ち着かせるために、すぐに渚を抱きしめた。
その瞬間、渚の身体が一瞬でどれだけ冷やされ、震えていたのかが分かった。
すでに周りの声が聞こえていないだろうという状況だった。