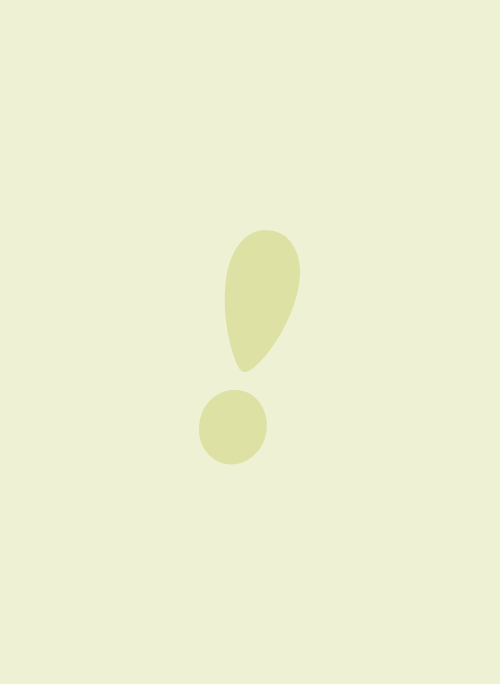次に渚が目を覚ましたのはその日の夕方だった。
誰かが病室に入ってくる音で目が覚めたのだ。
左手首の傷の痛みに多少うめきはしたものの、両手を支えに何とか起き上がった。
「悪い、起こしちゃったか?ゆっくり寝ててもいいぞ?」
その声を聞いて、渚は安堵の表情を漏らした。
もちろんその声の主は隼人である。
「大丈夫だよ、先生…。身体が悪くて入院してるんじゃないんだから」
渚はできるだけ元気に聞こえるように声を出したのだが、やはり出てきた声は少し疲れたような声だった。
隼人は渚のベットの横にある椅子に腰をかけると、渚の表情を静かに観察した。
「…ふーん、だいぶ元気になったんじゃないか?目にはまだいつもの力は戻ってないけど、結構体力的には戻ってきてるみたいだな。安心したよ」
隼人はほっと息を漏らすと同時に笑顔を見せた。
その笑顔につられて渚も軽く笑顔を見せた。
誰かが病室に入ってくる音で目が覚めたのだ。
左手首の傷の痛みに多少うめきはしたものの、両手を支えに何とか起き上がった。
「悪い、起こしちゃったか?ゆっくり寝ててもいいぞ?」
その声を聞いて、渚は安堵の表情を漏らした。
もちろんその声の主は隼人である。
「大丈夫だよ、先生…。身体が悪くて入院してるんじゃないんだから」
渚はできるだけ元気に聞こえるように声を出したのだが、やはり出てきた声は少し疲れたような声だった。
隼人は渚のベットの横にある椅子に腰をかけると、渚の表情を静かに観察した。
「…ふーん、だいぶ元気になったんじゃないか?目にはまだいつもの力は戻ってないけど、結構体力的には戻ってきてるみたいだな。安心したよ」
隼人はほっと息を漏らすと同時に笑顔を見せた。
その笑顔につられて渚も軽く笑顔を見せた。