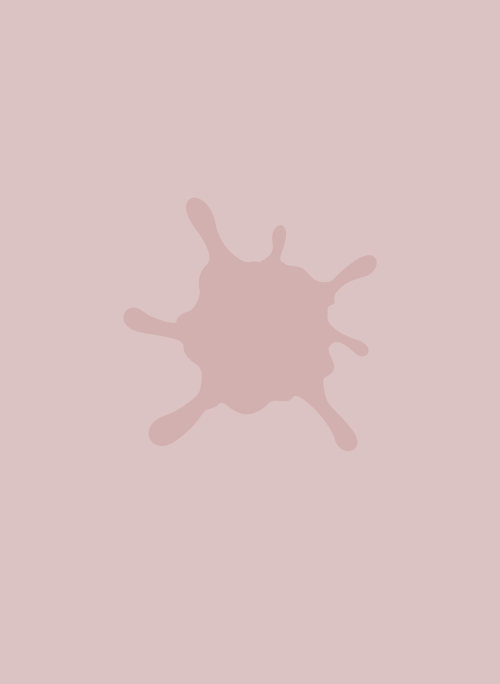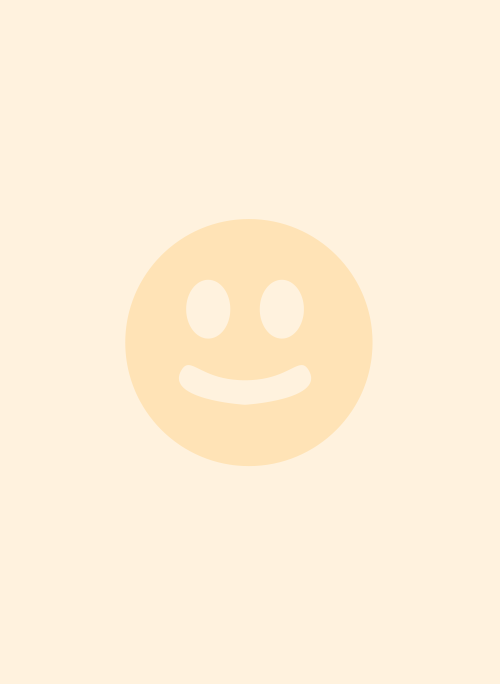目的地が近づくにつれて、裕貴とワックスの表情が強張ってきた気がする。当たり前だ。先程まで自分たちがいた場所に戻ってきたのだから。
車は運送会社の前で停まった。退社時間を過ぎたのだろう。電気が消えている。
降車した貫野がガラス張り手押しの扉に手をかけるが、開かないようで首を横に振った。
続けて十一朗も降りると、すぐに裏口に足を向けた。貫野と文目もついてくる。先に降りたはずの裕貴は立ち尽くしたまま、ワックスも視線を向けただけでついてこなかった。
裏口から微かに明かりが見えた。中に誰かいる。真犯人は帰ってはいない。
そう感じた瞬間、どっと嫌な汗が出た。いつもなら扉を叩くことができたはずだ。動けずにいると、貫野がガラス扉を叩きながら大声をあげた。
「もう閉めたんですか。話をしたいので、出ていただけないでしょうか」
貫野の言葉が終わるより先に、曇りガラスの向こうで人影が動いた。扉が開いて顔を出したのは、事務員の女性だった。十一朗の顔を知っているので驚いた顔をすると、奥のほうに声をかける。社長がいるのは確実だ。しかし、事務員はこちらに向かってくると、扉を少し開けてから貫野に告げた。
「申し訳ありません。社長は帰ってしまったので、後日きていただけないでしょうか」
「後日ですか。では都合のいい日は?」
「明日からは海外出張です。帰るのは一週間後だと言っていました」
「自宅の住所を教えていただけると助かるのですが」
執拗な貫野の食い下がりに、事務員は苛立った様子で睨みつけた。
「それはお教えすることができません。個人情報ですから。それとお名前を――」
仕方なく貫野が警察手帳を出した。途端に事務員が硬直して、目を見開いた。
「社長は中にいますね。開けてくれませんか」
ここで駄目ですと事務員が言うと、犯人隠匿罪となる。視線を落したままの事務員に扉を開けてもらった貫野は中に入った。続いて十一朗も続く。文目は裕貴とワックスに手招きして呼んでから、二人を通してから中に入った。
「なんですか。あなたは!」
不意に覚えのある声が響いた。社長に間違いないが、会った時の雰囲気とは違うドスの利いた声だった。
「あんたを升田殺しで逮捕する」
「升田? 誰なんですか。知らない人です。出ていかないと警察を……」
途中まで社長は言ってから口を閉じた。「逮捕する」というのは警察だけだ。
「知らない人ですか。では、事件当日に電話をかけてきた和田さんは知っていますよね」
貫野に詰め寄られた社長は口籠りながら後退していく。
その時、何をやっていたのか文目が奥の部屋から姿を見せた。
「先輩、奥にブランド物のバッグと宝石がありました。商品番号を照会しますか」
見事な手並みだった。貫野が社長の気を引いているうちに、文目は内部観察したのだ。
本来なら、令状なしで探るのは褒められた行為ではないが、相手の罪を明るみにさえすれば、誰も文句は言えない。
十一朗は社長を見た。畳みかけるのなら今だ。今この場でとっておきの言葉を、脳内から弾き出した。
「それは企業から任された荷物ですよね。社長さんは通関士の免許も持っているから、輸入品の取り扱いにも長けていそうですし」
社長の顔色が変わり、あの高級ソファーに力なく座りこんだ。後ろめたさがないのなら、こんな反応はあり得ない。
「通話履歴を調べたら、すぐにわかってしまうことですよ」
座りこんだ社長の顔を覗きこみながら貫野が言うと、唇を振るわせながら社長は叫んだ。
「私は悪くない。あいつは死んで当然の男だったんだ!」
社長の叫びで室内のガラスが震えた。
升田は確かに悪鬼とも呼べるような男だ。しかし、殺していい命があるのか。
十一朗は答えに迷った。その時、ワックスが社長に向かって叫んだ。
「あんた言ったよな。物がなくなるのはまだいいんだよ。だけど人の命はねって! 何で、こんなに雰囲気のいい会社を……社員まで裏切るような真似するんだよ!」
殺人が悪いとだけしか思い浮かばなかった十一朗にとって、ワックスの叫びは目が覚めたような気がした。
社長が全身を震わせて紅潮した。怒りが現れ出た表情だった。
「子供に何がわかる。親父の会社を潰したくない気持ちがわかるか。従業員を首にしたくない経営者の気持ちがわかるか」
十一朗は社長の言葉を思い出していた。
『私の居場所であり、誇りでもあるのがこの会社だからね』
自分がミス研部に感じていることと同じだ。ミス研部員が馬鹿にされたなら黙ってはいられない。困ったら互いに助け合う。
従業員をクビにしたくない気持ちはわかる。部員が泣くのを見たくない。社長は自分と同じ被害者なのかもしれない。
車は運送会社の前で停まった。退社時間を過ぎたのだろう。電気が消えている。
降車した貫野がガラス張り手押しの扉に手をかけるが、開かないようで首を横に振った。
続けて十一朗も降りると、すぐに裏口に足を向けた。貫野と文目もついてくる。先に降りたはずの裕貴は立ち尽くしたまま、ワックスも視線を向けただけでついてこなかった。
裏口から微かに明かりが見えた。中に誰かいる。真犯人は帰ってはいない。
そう感じた瞬間、どっと嫌な汗が出た。いつもなら扉を叩くことができたはずだ。動けずにいると、貫野がガラス扉を叩きながら大声をあげた。
「もう閉めたんですか。話をしたいので、出ていただけないでしょうか」
貫野の言葉が終わるより先に、曇りガラスの向こうで人影が動いた。扉が開いて顔を出したのは、事務員の女性だった。十一朗の顔を知っているので驚いた顔をすると、奥のほうに声をかける。社長がいるのは確実だ。しかし、事務員はこちらに向かってくると、扉を少し開けてから貫野に告げた。
「申し訳ありません。社長は帰ってしまったので、後日きていただけないでしょうか」
「後日ですか。では都合のいい日は?」
「明日からは海外出張です。帰るのは一週間後だと言っていました」
「自宅の住所を教えていただけると助かるのですが」
執拗な貫野の食い下がりに、事務員は苛立った様子で睨みつけた。
「それはお教えすることができません。個人情報ですから。それとお名前を――」
仕方なく貫野が警察手帳を出した。途端に事務員が硬直して、目を見開いた。
「社長は中にいますね。開けてくれませんか」
ここで駄目ですと事務員が言うと、犯人隠匿罪となる。視線を落したままの事務員に扉を開けてもらった貫野は中に入った。続いて十一朗も続く。文目は裕貴とワックスに手招きして呼んでから、二人を通してから中に入った。
「なんですか。あなたは!」
不意に覚えのある声が響いた。社長に間違いないが、会った時の雰囲気とは違うドスの利いた声だった。
「あんたを升田殺しで逮捕する」
「升田? 誰なんですか。知らない人です。出ていかないと警察を……」
途中まで社長は言ってから口を閉じた。「逮捕する」というのは警察だけだ。
「知らない人ですか。では、事件当日に電話をかけてきた和田さんは知っていますよね」
貫野に詰め寄られた社長は口籠りながら後退していく。
その時、何をやっていたのか文目が奥の部屋から姿を見せた。
「先輩、奥にブランド物のバッグと宝石がありました。商品番号を照会しますか」
見事な手並みだった。貫野が社長の気を引いているうちに、文目は内部観察したのだ。
本来なら、令状なしで探るのは褒められた行為ではないが、相手の罪を明るみにさえすれば、誰も文句は言えない。
十一朗は社長を見た。畳みかけるのなら今だ。今この場でとっておきの言葉を、脳内から弾き出した。
「それは企業から任された荷物ですよね。社長さんは通関士の免許も持っているから、輸入品の取り扱いにも長けていそうですし」
社長の顔色が変わり、あの高級ソファーに力なく座りこんだ。後ろめたさがないのなら、こんな反応はあり得ない。
「通話履歴を調べたら、すぐにわかってしまうことですよ」
座りこんだ社長の顔を覗きこみながら貫野が言うと、唇を振るわせながら社長は叫んだ。
「私は悪くない。あいつは死んで当然の男だったんだ!」
社長の叫びで室内のガラスが震えた。
升田は確かに悪鬼とも呼べるような男だ。しかし、殺していい命があるのか。
十一朗は答えに迷った。その時、ワックスが社長に向かって叫んだ。
「あんた言ったよな。物がなくなるのはまだいいんだよ。だけど人の命はねって! 何で、こんなに雰囲気のいい会社を……社員まで裏切るような真似するんだよ!」
殺人が悪いとだけしか思い浮かばなかった十一朗にとって、ワックスの叫びは目が覚めたような気がした。
社長が全身を震わせて紅潮した。怒りが現れ出た表情だった。
「子供に何がわかる。親父の会社を潰したくない気持ちがわかるか。従業員を首にしたくない経営者の気持ちがわかるか」
十一朗は社長の言葉を思い出していた。
『私の居場所であり、誇りでもあるのがこの会社だからね』
自分がミス研部に感じていることと同じだ。ミス研部員が馬鹿にされたなら黙ってはいられない。困ったら互いに助け合う。
従業員をクビにしたくない気持ちはわかる。部員が泣くのを見たくない。社長は自分と同じ被害者なのかもしれない。