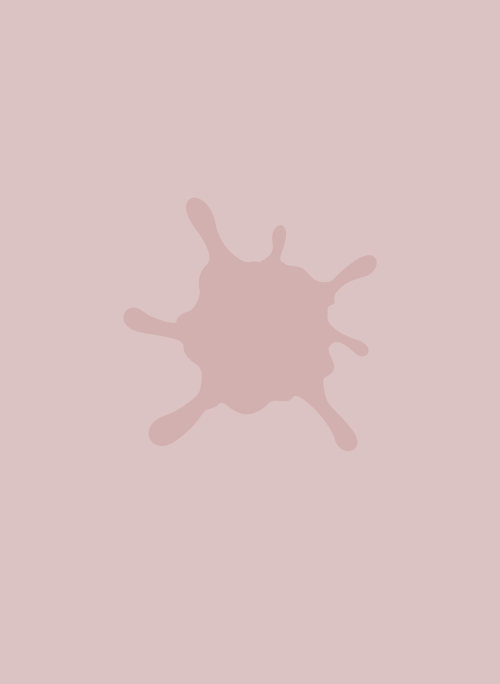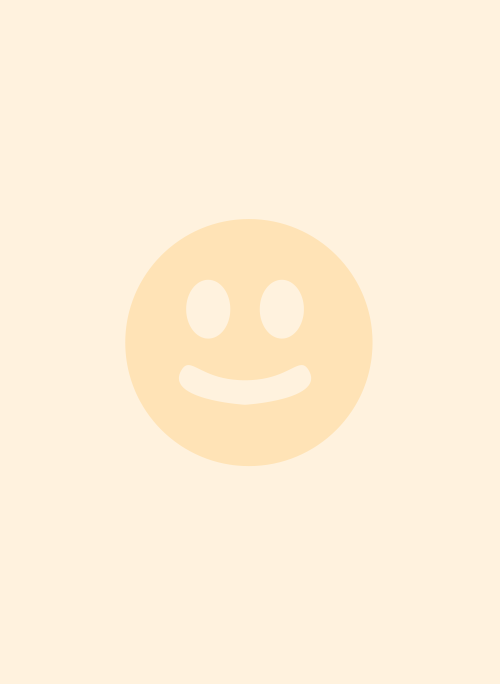電車の通過音が徐々に遠ざかっていく。踏切の音が途切れると、皆の呼吸音だけが病室に響いていた。
静まる時を待っていたのだろうか。不意に綾花の母が和田を見た。
話してもいいか――。彼女の目が和田に語っていた。
十一年前の襲撃事件は、八木親子や和田の心理内では、まだ解決していないだろう。何をしても八木彰夫は帰ってはこない。両者の時間はとまったままのはずだ。
それでも、十一年間の心と心の語り合いは無駄ではなかったのだろう。
全てを察したかのように和田は首を縦に振って応えた。
以心伝心。他人でも繋がる心がある。二人の間にはそれを感じた。
綾花の母は、十一朗と貫野のほうに顔を向けると口を開いた。
「和田さんを知ったのは、綾花の幼稚園の運動会の前日です。保険金はおりていましたが、専業主婦だった私は仕事を探すのに苦労していました。収入がほとんどゼロという不安な生活の中で、綾花に運動靴を買ってあげることができなかった。親として情けなくて、涙が出ました。そんな時、運動靴が届けられたんです」
玄関先に手紙と一緒にいろんなものが届けられるようになった。綾花はそう言っていた。
和田があしながおじさんとして、はじめて届けたものが運動靴だったのだろう。
「扉を開けると知らない男性がいました。そして受け取ってくださいと箱を渡されたんです。対応に困る私に男性は、八木さんの同僚の和田ですと自己紹介してくれました。箱の中には『君のあしながおじさんより』という手紙がありました。嬉しかった……彼の好意に感謝しました。それから彼は、いろんなものを買っては届けてくれたんです」
綾花の母が和田のことを彼と言った。親密な関係になっているのだということが窺えた。
この時、綾花の母は、和田が輸送車襲撃事件の被害者であると知らなかったはずだ。被害者の綾花の母からしてみると、夫が死んだ事件の新聞を見る気にもならないだろう。しかも犯人は逃走中。やり場のない怒りをどこにぶつけたらいいのか。
――苦しんでいたに違いない。事件の証拠をつかめない警察も憎んでいたことだろう。救いの手を差し伸べた和田の存在は、綾花の母には大きな存在だったであろうと想像がついた。
「その時から彼との交流がはじまりました。彼は誠実な人で、男と女の関係を求めることがなかった。そのせいでしょうか。私は逆に彼に惹かれていきました。そんな時、彼の口から聞いたんです。妻子がいたこと。襲撃事件の時に同乗していたこと。重傷を負って犯人の顔を見ていないこと。そして、私にぶ厚い封筒を渡してきました」
十一朗は封筒の中が何であったのかを察した。和田が必要なくなったという保険金、千四百万円の一部だろう。
和田は八木親子の将来を保証する代わりに、犯人の顔を見ていないという嘘をついた。犯人の升田が捕まると、その口から共犯の自分の名前が出ることは確実だ。
せめて綾花が成長するまでは嘘を。償いのために金を。
そんな気持ちの中で和田は、嘘をついた自分を慰めていたのかもしれない。
同時に和田は妻子がいたと告げて、綾花の母との距離を保った。男と女の関係になることを嫌ったのだろう。
綾花の母が息を吐いた。
十一年間もの出来事を思い出し語るのは、相当の辛苦を伴うのだろう。代わって和田が話に加わった。
「封筒を渡したのは、綾花さんが高校に合格した時です。償いきれないでしょうが、肩の荷がおりた気がしました。けれどその頃でした。升田が刑務所から出たと知ったのは……あいつはハイエナのような男です。組の情報網を使って、必ず私を見つけようとする。自首しなければ二人が危険と感じ、会うのはこれが最後と決めて、万年筆を予約しました」
万年筆を見つけたのはミステリー研究部全員の手だ。裕貴もワックスも綾花も、エンジ色で『AYAKA.Y』と刻印された現物を見ている。
あの万年筆には和田の最後の償いの気持ちが込められていたのだ。裕貴、ワックス、綾花は息を呑んで聞いていた。
万年筆の予約で和田が自分の名前ではなく、八木和歌子名義にしたのは、升田の追跡をかわすためだったのだろう。その時は、升田が現れるなどとは考えもしなかったはずだ。
そして、万年筆を受け取った直後に、綾花の母に電話をかけたに違いない。
静まる時を待っていたのだろうか。不意に綾花の母が和田を見た。
話してもいいか――。彼女の目が和田に語っていた。
十一年前の襲撃事件は、八木親子や和田の心理内では、まだ解決していないだろう。何をしても八木彰夫は帰ってはこない。両者の時間はとまったままのはずだ。
それでも、十一年間の心と心の語り合いは無駄ではなかったのだろう。
全てを察したかのように和田は首を縦に振って応えた。
以心伝心。他人でも繋がる心がある。二人の間にはそれを感じた。
綾花の母は、十一朗と貫野のほうに顔を向けると口を開いた。
「和田さんを知ったのは、綾花の幼稚園の運動会の前日です。保険金はおりていましたが、専業主婦だった私は仕事を探すのに苦労していました。収入がほとんどゼロという不安な生活の中で、綾花に運動靴を買ってあげることができなかった。親として情けなくて、涙が出ました。そんな時、運動靴が届けられたんです」
玄関先に手紙と一緒にいろんなものが届けられるようになった。綾花はそう言っていた。
和田があしながおじさんとして、はじめて届けたものが運動靴だったのだろう。
「扉を開けると知らない男性がいました。そして受け取ってくださいと箱を渡されたんです。対応に困る私に男性は、八木さんの同僚の和田ですと自己紹介してくれました。箱の中には『君のあしながおじさんより』という手紙がありました。嬉しかった……彼の好意に感謝しました。それから彼は、いろんなものを買っては届けてくれたんです」
綾花の母が和田のことを彼と言った。親密な関係になっているのだということが窺えた。
この時、綾花の母は、和田が輸送車襲撃事件の被害者であると知らなかったはずだ。被害者の綾花の母からしてみると、夫が死んだ事件の新聞を見る気にもならないだろう。しかも犯人は逃走中。やり場のない怒りをどこにぶつけたらいいのか。
――苦しんでいたに違いない。事件の証拠をつかめない警察も憎んでいたことだろう。救いの手を差し伸べた和田の存在は、綾花の母には大きな存在だったであろうと想像がついた。
「その時から彼との交流がはじまりました。彼は誠実な人で、男と女の関係を求めることがなかった。そのせいでしょうか。私は逆に彼に惹かれていきました。そんな時、彼の口から聞いたんです。妻子がいたこと。襲撃事件の時に同乗していたこと。重傷を負って犯人の顔を見ていないこと。そして、私にぶ厚い封筒を渡してきました」
十一朗は封筒の中が何であったのかを察した。和田が必要なくなったという保険金、千四百万円の一部だろう。
和田は八木親子の将来を保証する代わりに、犯人の顔を見ていないという嘘をついた。犯人の升田が捕まると、その口から共犯の自分の名前が出ることは確実だ。
せめて綾花が成長するまでは嘘を。償いのために金を。
そんな気持ちの中で和田は、嘘をついた自分を慰めていたのかもしれない。
同時に和田は妻子がいたと告げて、綾花の母との距離を保った。男と女の関係になることを嫌ったのだろう。
綾花の母が息を吐いた。
十一年間もの出来事を思い出し語るのは、相当の辛苦を伴うのだろう。代わって和田が話に加わった。
「封筒を渡したのは、綾花さんが高校に合格した時です。償いきれないでしょうが、肩の荷がおりた気がしました。けれどその頃でした。升田が刑務所から出たと知ったのは……あいつはハイエナのような男です。組の情報網を使って、必ず私を見つけようとする。自首しなければ二人が危険と感じ、会うのはこれが最後と決めて、万年筆を予約しました」
万年筆を見つけたのはミステリー研究部全員の手だ。裕貴もワックスも綾花も、エンジ色で『AYAKA.Y』と刻印された現物を見ている。
あの万年筆には和田の最後の償いの気持ちが込められていたのだ。裕貴、ワックス、綾花は息を呑んで聞いていた。
万年筆の予約で和田が自分の名前ではなく、八木和歌子名義にしたのは、升田の追跡をかわすためだったのだろう。その時は、升田が現れるなどとは考えもしなかったはずだ。
そして、万年筆を受け取った直後に、綾花の母に電話をかけたに違いない。