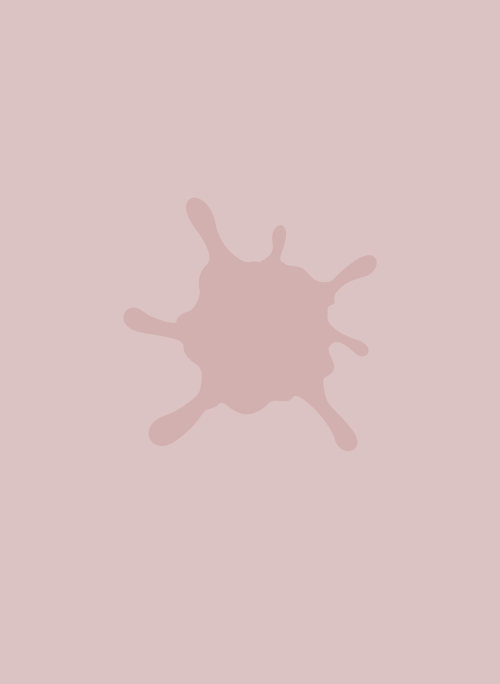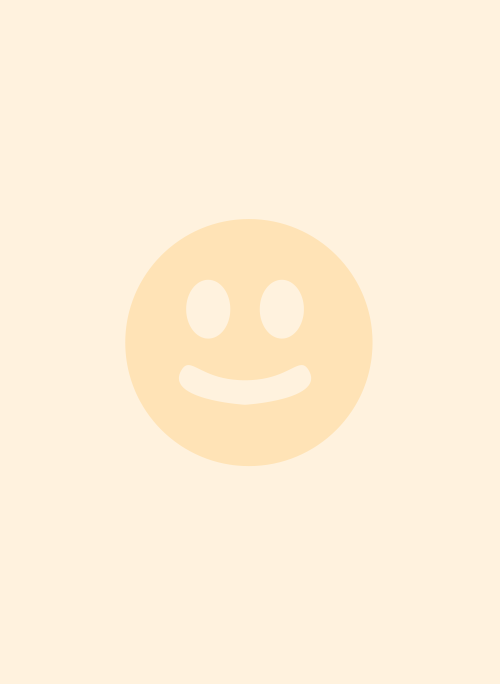「何故、十一年後の今になって和田と争い、自殺未遂をしてまで証拠を隠そうとしたんですか。十一年前の事件を隠し続けたりしていなければ、あなたは升田を殺さずにすんだはずなのに」
和田は口を閉ざすと、八木和歌子と綾花に一瞬だけ視線を向けた。同時に和田の目から涙が零れ落ちた。そして、小さな声で何か言う。全員が聴き取れない震えが混じった声だ。
「あしながおじさん……」
その時、和田ではなく綾花が声を出した。そして懐から何かを取り出す。取り出されたのは薄汚れた安全祈願のお守りだった。
「お父さんがいなくなってから、何故か玄関先に手紙と一緒にいろんなものが届けられるようになりました。運動会近くになると運動靴。小学校入学前にはランドセル。誰からなのかわからずに母に訊いたことがあります。手紙にはいつも『君のあしながおじさんより』と……今日、母から聞いて、和田さんがそのあしながおじさんだと知りました」
十一朗も裕貴もワックスも和田を見た。貫野と文目も同じ反応をした。
十一年前の事件の直後、和田は妻子を失っている。それが病気だったとわかった今、和田が何を考え、今までを生きてきたのか見えた気がした。
十一朗は程度の予想をつけながらも、和田を見た。
「輸送会社の社長に聞きました。保険金として千四百万円をあなたに渡したと。そして升田は仲間に七百万を返してもらえると言っていたそうです。もしかしてそのお金は……」
「必要なくなりました。私が重傷で入院している時、娘は死にました。あれほど苦しんでいたのに、最期はあっけなかったそうです。娘を追うように妻も天国に逝きました。私が彼女たちを死なせてしまったようなものなんです。馬鹿なことをやって、娘の最期に立ち会えなかった。妻が一番苦しい時に隣にいてやれなかった。私は生き甲斐をなくしました。その時、新聞である記事を見たんです。輸送車襲撃事件の被害者のことが書いてありました」
十一朗は図書館で見た縮小版の新聞記事を思い出していた。
最愛の妻と子を亡くした男が、最愛の夫を亡くした妻と子を見る。その時、和田の心の中に何が生まれたのか。黙っていた貫野が居住まいを正して、和田に訊いた。
「償いですか……」
最愛の者を亡くした被害者の気持ちは、はかり知れない。亡くした者は二度と帰ってこない。どんなに償っても許されることではない。
しかし、和田は知っていた。最愛の者を亡くす苦しみだけは――。
「せめて、せめて八木の娘さんが大学に進学するまではと考えていました。時がきたら自首するつもりでした。そんな時、捕まっていた升田が出てきたと知りました。このまま私が彼女たちの近くにいたら、必ず被害が及ぶ。そして、自首を決めて電話をかけたんです」
電話をかけた相手が綾花の母だったのだろう。
和田は綾花の母を呼び出して、十一年前の事件の真相を語ったに違いない。その時、彼女はどんな反応をしたのだろうか。
複雑な感情の中にいたに違いない。しかし、綾花の母も最愛の夫を亡くした身だ。和田の気持ちを察し、せめて自分の娘にも真実を語ってほしいと携帯の電話番号をポケットに押しこんだのかもしれない。
ところが、和田はそこで大きな息を吐いた。真剣な表情だった。
「八木さん。娘さんの電話番号を無理やり書かせてすみませんでした。あの時、私は手袋をしていたので、メモからは八木さんの指紋しか検出されなかったのでしょう」
ここで和田は再び頭をさげながら、十一朗の推理を覆す言葉を発した。
和田は何があっても、今回の事件の共犯を八木和歌子とは言わないつもりだ。全ての罪を受けとめようとしている。
十一朗は和田の中に、命を懸けても償うという覚悟を見た。
「もういいんです。和田さん!」
瞬間、綾花の母が声をあげた。大粒の涙を流しながら、唇を噛んでいた。そして、綾花を抱き寄せながら、「お父さんのこと、黙っていてごめんね」と涙声で言った。
「夫を刺した男を殴ってやったのを、私は後悔していません。あなたがやらなくても、升田は私が殺していました。そして、私は和田さん。あなたを十一年前の事件の共犯だとは思っていないんです……一番許せないのは升田。そして、あなたを命懸けで守ろうとした夫を私は誇りに思っています」
八木和歌子が全てを語った途端、和田は大声を張りあげながら泣いた。
十一年前の罪を自分は償いきれているのか。そんな悩みと感情が爆発したかのような声だった。
何度も「すまない。すまない」と連呼した。綾花の母と綾花に言ったのか、命を落とした八木彰夫に詫びるものだったのか。
少なくとも自分の罪から逃げる、表面上の謝罪ではなかった。今までの彼の行動が、それを証明していた。
息を吐いた十一朗を貫野が見た。よくやったということなのだろう。
しかし、事件は解決してはいない。十一年前に繋がる今回の事件。升田が死んだ夜の話がまだだ。
「あの夜、私が仕事場で休憩している時に電話がありました。着信を見ると公衆電話からでした。私の携帯に公衆電話でかけてくる人は和田さんだけです。電話を取ると彼は、大事な話がある。近所の公園で会えないかと私に言いました」
数日前の記憶を辿るように、綾花の母が語りはじめる。
全員視線が彼女の口に集中する。十一朗は望んでいた事件の真相を前に、思わず息を呑んだ。
近くを通る電車の音と通過を告げる踏切の音が、事件の夜を思い出させるかのように微かに聞こえていた。
和田は口を閉ざすと、八木和歌子と綾花に一瞬だけ視線を向けた。同時に和田の目から涙が零れ落ちた。そして、小さな声で何か言う。全員が聴き取れない震えが混じった声だ。
「あしながおじさん……」
その時、和田ではなく綾花が声を出した。そして懐から何かを取り出す。取り出されたのは薄汚れた安全祈願のお守りだった。
「お父さんがいなくなってから、何故か玄関先に手紙と一緒にいろんなものが届けられるようになりました。運動会近くになると運動靴。小学校入学前にはランドセル。誰からなのかわからずに母に訊いたことがあります。手紙にはいつも『君のあしながおじさんより』と……今日、母から聞いて、和田さんがそのあしながおじさんだと知りました」
十一朗も裕貴もワックスも和田を見た。貫野と文目も同じ反応をした。
十一年前の事件の直後、和田は妻子を失っている。それが病気だったとわかった今、和田が何を考え、今までを生きてきたのか見えた気がした。
十一朗は程度の予想をつけながらも、和田を見た。
「輸送会社の社長に聞きました。保険金として千四百万円をあなたに渡したと。そして升田は仲間に七百万を返してもらえると言っていたそうです。もしかしてそのお金は……」
「必要なくなりました。私が重傷で入院している時、娘は死にました。あれほど苦しんでいたのに、最期はあっけなかったそうです。娘を追うように妻も天国に逝きました。私が彼女たちを死なせてしまったようなものなんです。馬鹿なことをやって、娘の最期に立ち会えなかった。妻が一番苦しい時に隣にいてやれなかった。私は生き甲斐をなくしました。その時、新聞である記事を見たんです。輸送車襲撃事件の被害者のことが書いてありました」
十一朗は図書館で見た縮小版の新聞記事を思い出していた。
最愛の妻と子を亡くした男が、最愛の夫を亡くした妻と子を見る。その時、和田の心の中に何が生まれたのか。黙っていた貫野が居住まいを正して、和田に訊いた。
「償いですか……」
最愛の者を亡くした被害者の気持ちは、はかり知れない。亡くした者は二度と帰ってこない。どんなに償っても許されることではない。
しかし、和田は知っていた。最愛の者を亡くす苦しみだけは――。
「せめて、せめて八木の娘さんが大学に進学するまではと考えていました。時がきたら自首するつもりでした。そんな時、捕まっていた升田が出てきたと知りました。このまま私が彼女たちの近くにいたら、必ず被害が及ぶ。そして、自首を決めて電話をかけたんです」
電話をかけた相手が綾花の母だったのだろう。
和田は綾花の母を呼び出して、十一年前の事件の真相を語ったに違いない。その時、彼女はどんな反応をしたのだろうか。
複雑な感情の中にいたに違いない。しかし、綾花の母も最愛の夫を亡くした身だ。和田の気持ちを察し、せめて自分の娘にも真実を語ってほしいと携帯の電話番号をポケットに押しこんだのかもしれない。
ところが、和田はそこで大きな息を吐いた。真剣な表情だった。
「八木さん。娘さんの電話番号を無理やり書かせてすみませんでした。あの時、私は手袋をしていたので、メモからは八木さんの指紋しか検出されなかったのでしょう」
ここで和田は再び頭をさげながら、十一朗の推理を覆す言葉を発した。
和田は何があっても、今回の事件の共犯を八木和歌子とは言わないつもりだ。全ての罪を受けとめようとしている。
十一朗は和田の中に、命を懸けても償うという覚悟を見た。
「もういいんです。和田さん!」
瞬間、綾花の母が声をあげた。大粒の涙を流しながら、唇を噛んでいた。そして、綾花を抱き寄せながら、「お父さんのこと、黙っていてごめんね」と涙声で言った。
「夫を刺した男を殴ってやったのを、私は後悔していません。あなたがやらなくても、升田は私が殺していました。そして、私は和田さん。あなたを十一年前の事件の共犯だとは思っていないんです……一番許せないのは升田。そして、あなたを命懸けで守ろうとした夫を私は誇りに思っています」
八木和歌子が全てを語った途端、和田は大声を張りあげながら泣いた。
十一年前の罪を自分は償いきれているのか。そんな悩みと感情が爆発したかのような声だった。
何度も「すまない。すまない」と連呼した。綾花の母と綾花に言ったのか、命を落とした八木彰夫に詫びるものだったのか。
少なくとも自分の罪から逃げる、表面上の謝罪ではなかった。今までの彼の行動が、それを証明していた。
息を吐いた十一朗を貫野が見た。よくやったということなのだろう。
しかし、事件は解決してはいない。十一年前に繋がる今回の事件。升田が死んだ夜の話がまだだ。
「あの夜、私が仕事場で休憩している時に電話がありました。着信を見ると公衆電話からでした。私の携帯に公衆電話でかけてくる人は和田さんだけです。電話を取ると彼は、大事な話がある。近所の公園で会えないかと私に言いました」
数日前の記憶を辿るように、綾花の母が語りはじめる。
全員視線が彼女の口に集中する。十一朗は望んでいた事件の真相を前に、思わず息を呑んだ。
近くを通る電車の音と通過を告げる踏切の音が、事件の夜を思い出させるかのように微かに聞こえていた。