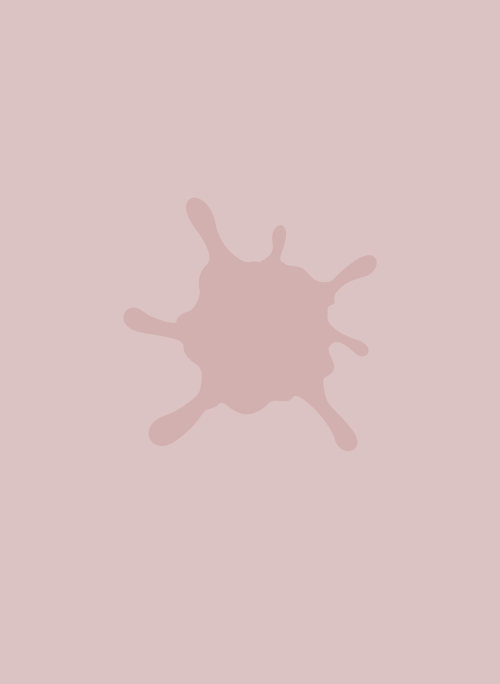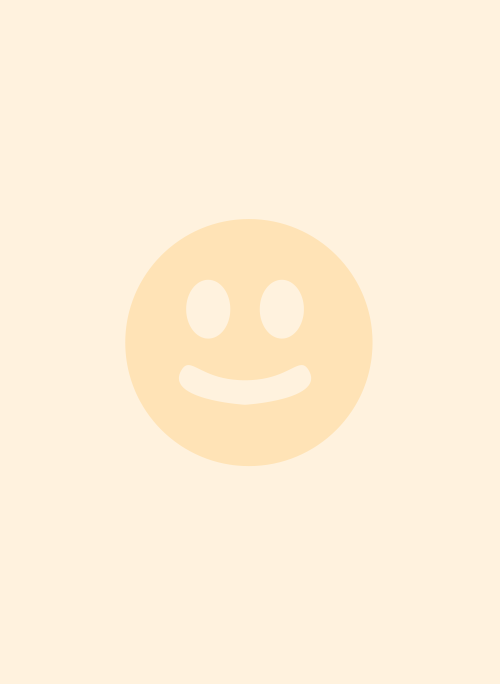「直接、十一年前の事件を聞いても、口は割らないと思うんだ。だけどそれなら、相手が違うといっても牽制することはできる」
「お前さん、お得意の誘導尋問ってやつか」
「誘導尋問は俺じゃなくて、貫野さんの仕事になるんだから、よく覚えておいてくれよ。そして、更に追及してくれ。刺された傷を隠したのは、なぜかって」
聞いて貫野は気づいた様子だった。その尋問が、左利きの人物を庇っていないかという質問に直結するものだということを。十一年前の事件を掘り出す質問だということを。
「とんでもない爆弾だな。だが、奴は押し黙ると思うぞ」
「言ったろ牽制だって。男が左利きの真犯人を庇っているとしたら、残された行動はひとつになるんだ。自分が犯人だと認めなければ、左利きの犯人を守れなくなる。だから、十一年前の事件も今回の事件の真相も自白せざる負えなくなるんだ」
「揺さぶりか……刑事部長が割らせの東海林と言われていたって話を思い出した」
言ってから貫野は場が悪そうにカップを取った。しかし、中身は空だ。
「別に口ごもらなくていいよ。親子だって言いたいんだろ」
紅茶を一口した十一朗は貫野を見た。複雑な表情を少し覗かせた貫野は、すぐに隣にいる文目のメモを覗きこんだ。
この行動の意味を十一朗は知っている。貫野の両親は弁護士だ。刑事は犯人を追いつめる責務がある。弁護士は犯人を守る立場になる時がある。いわば犬猿の仲だ。
刑事部長の父を追いかけはじめた十一朗を前にして、何も感じていないはずがなかった。親子という繋がりを強く意識しているに違いなかった。
同時にここにくる前の会話を十一朗は思い出した。裏で糸を引いているのは父ではない。貫野なのだろう。はやく気づくべきだったのだ。左利きの真犯人の案を出し、それが十一朗の手柄だと刑事部長の父に教えた。そう文目の口から聞いた時点で。
解決への道筋が見えたため、貫野が立ちあがった。置いてある領収書を見ると、また合計金額より多い数の札を置いた。
「じゃあ、俺たちは行くぞ。高校生名探偵殿のご依頼を果たさなければなりませんので」
相変わらずの嫌味口調だが、十一朗は嫌な気分にはならなかった。それよりも――。
「あのさ、貫野さん」
十一朗の呼びかけに貫野が振り返った。敬称を付けたことはあまりない。そのため困惑した表情だった。
「協力に感謝」
敬礼して告げた十一朗に、貫野が吐き捨てるような声を出して返した。
「ガラにもないこと言うんじゃねえよ。調子狂うじゃねえか」
出ていった貫野の背中を見ながら十一朗は感じていた。
あの貫野相手なら、柵(しがらみ)に縛られることなく、ともに行動できそうだなと。
「お前さん、お得意の誘導尋問ってやつか」
「誘導尋問は俺じゃなくて、貫野さんの仕事になるんだから、よく覚えておいてくれよ。そして、更に追及してくれ。刺された傷を隠したのは、なぜかって」
聞いて貫野は気づいた様子だった。その尋問が、左利きの人物を庇っていないかという質問に直結するものだということを。十一年前の事件を掘り出す質問だということを。
「とんでもない爆弾だな。だが、奴は押し黙ると思うぞ」
「言ったろ牽制だって。男が左利きの真犯人を庇っているとしたら、残された行動はひとつになるんだ。自分が犯人だと認めなければ、左利きの犯人を守れなくなる。だから、十一年前の事件も今回の事件の真相も自白せざる負えなくなるんだ」
「揺さぶりか……刑事部長が割らせの東海林と言われていたって話を思い出した」
言ってから貫野は場が悪そうにカップを取った。しかし、中身は空だ。
「別に口ごもらなくていいよ。親子だって言いたいんだろ」
紅茶を一口した十一朗は貫野を見た。複雑な表情を少し覗かせた貫野は、すぐに隣にいる文目のメモを覗きこんだ。
この行動の意味を十一朗は知っている。貫野の両親は弁護士だ。刑事は犯人を追いつめる責務がある。弁護士は犯人を守る立場になる時がある。いわば犬猿の仲だ。
刑事部長の父を追いかけはじめた十一朗を前にして、何も感じていないはずがなかった。親子という繋がりを強く意識しているに違いなかった。
同時にここにくる前の会話を十一朗は思い出した。裏で糸を引いているのは父ではない。貫野なのだろう。はやく気づくべきだったのだ。左利きの真犯人の案を出し、それが十一朗の手柄だと刑事部長の父に教えた。そう文目の口から聞いた時点で。
解決への道筋が見えたため、貫野が立ちあがった。置いてある領収書を見ると、また合計金額より多い数の札を置いた。
「じゃあ、俺たちは行くぞ。高校生名探偵殿のご依頼を果たさなければなりませんので」
相変わらずの嫌味口調だが、十一朗は嫌な気分にはならなかった。それよりも――。
「あのさ、貫野さん」
十一朗の呼びかけに貫野が振り返った。敬称を付けたことはあまりない。そのため困惑した表情だった。
「協力に感謝」
敬礼して告げた十一朗に、貫野が吐き捨てるような声を出して返した。
「ガラにもないこと言うんじゃねえよ。調子狂うじゃねえか」
出ていった貫野の背中を見ながら十一朗は感じていた。
あの貫野相手なら、柵(しがらみ)に縛られることなく、ともに行動できそうだなと。