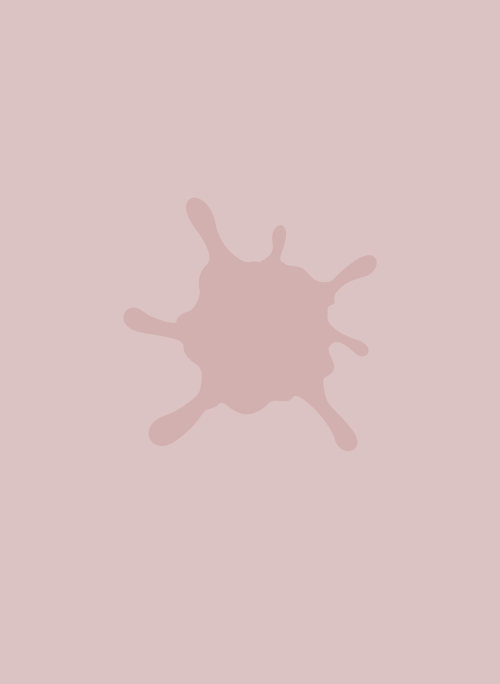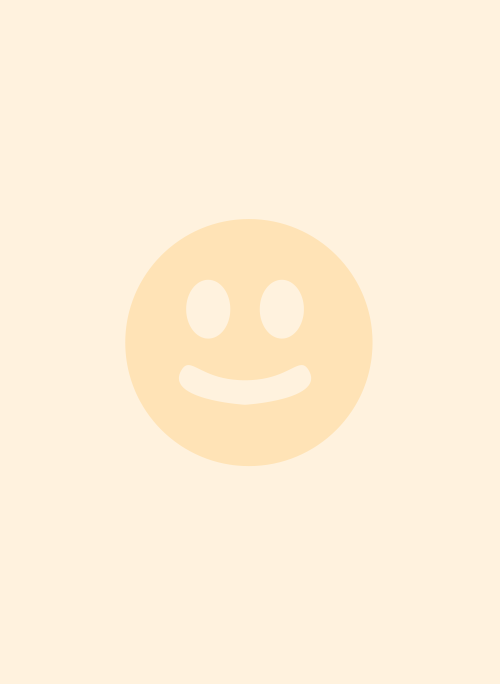「全部読めと言っているわけじゃないんだ。傷害事件だったから、傷とかそういった文字を気にして抜き出してくれればいい。あとは俺が選別するから」
十一朗が言い終わるより先に、裕貴と綾花は選別をはじめていた。特に綾花は速読なのか、手の動きがはやい。何冊もの推理小説で鍛えてきた、十一朗でも負けてしまいそうなはやさだ。
もしかしたら、事件ルポ本を読むのも好きなのかもしれないな。十一朗はそう感じた。
選別された資料が次々と十一朗の前に置かれていく。殺人、傷害、事故、強盗――。
十数年前のほうが事件事故は少ないはずだが、こうあふれ返ると犯罪はなくならないのかと憂鬱になってくる。
工場の流れ作業って、こんな感じなのかなとか思えてくる。いや、刑事になっても同じような捜査をするのだろう。探偵になりたいと思っていた時とは、また違う感覚が十一朗の中で芽生えはじめていた。
その時だ。誰よりもはやかった綾花の手がとまった。一枚の記事を見ながら震えている。ミス研の部室で見た、あの時を彷彿とさせるものだった。
「嘘、そんなの聞いてない。そんなの知らない」
綾花は念仏のように言葉を繰り返していた。途端に顔面蒼白になって噎せはじめた。慌てた裕貴が綾花に駆け寄る。十一朗は駆け寄る前に、彼女の異常を察知した。
「過呼吸だ! 落ち着け八木……俺の指が見えるか。俺の指に合わせて呼吸をしろ」
おそらく、新聞記事から信じ難いものを発見してしまったのだろう。そのために、精神的に混乱して過換気症を引き起こしてしまったのだ。死に直結するような症状ではないが、最悪の場合、失神することもある。
十一朗は綾花の正面に座って人差し指を立て、冷静に呼吸をすることを指示した。二酸化炭素の排出量を押さえるか、血中の二酸化炭素濃度を元に戻すのが有効な対処法とされているからだ。
立てて折り曲げてを繰り返すうちに、綾花の呼吸が正常に戻り、顔色も少しずつ赤みがさしてきた。
「もう大丈夫そうだな。無茶しなくてもいいから、帰って休んだほうがいいよ」
取り敢えずは安心だ――と、十一朗が思った途端。綾花が突然、落涙しながら抱きついてきた。しかも異常の前と同じ言葉を何度も繰り返している。
十一朗は頭の中が真っ白になってしまった。一瞬、紅潮しているのではないかと考えた。そして、目の前にいる裕貴と目が合った。すると、熱くなった体が一気に冷却されていく。
「オッケー。よし、落ち着こう。とにかく全員席に戻って……話はそれからだ」
皆に指示したものの、鼓動が静まらない。一番、落ち着いてないのは自分なのではないか。綾花の両肩をつかんで離した十一朗は、彼女を諭しながら席に着こうとした。
すると、綾花が十一朗の腕を取った。離れないでということか。困惑するしかない。
しかし、彼女の差し出したもう一方の手に、縮刷版の一冊が広げられていた。
「その記事の中に、父の名前が……私、知らなかった。ずっと」
途切れ途切れで話す綾花の手から縮刷版を受け取った。十一朗の視界にある記事が飛びこんできた。
『輸送車強盗殺傷事件』
発生したのは十一年前、十一朗が小学一年生の時だ。縮刷版なので記事の内容は詳細ではないが、残っていたところを見ると、かなり凄惨な事件だったのだろう。
『停車中に背後から襲われた輸送員がひとり死亡。ひとり重体。犯人は逃走中』
と印刷されていた。それよりも目にとまったのは死亡した人物の名前だった。『八木彰夫(あきお)』。
「まさか八木……君のお父さんって」
十一朗が訊いても、綾花は答えられずに首を横に振るだけだった。
『知らなかった。ずっと』という彼女の言葉が全てを表していた。綾花はこの記事を見てはじめて知ったのだ。父が死んだ本当の理由を――。
十一朗が言い終わるより先に、裕貴と綾花は選別をはじめていた。特に綾花は速読なのか、手の動きがはやい。何冊もの推理小説で鍛えてきた、十一朗でも負けてしまいそうなはやさだ。
もしかしたら、事件ルポ本を読むのも好きなのかもしれないな。十一朗はそう感じた。
選別された資料が次々と十一朗の前に置かれていく。殺人、傷害、事故、強盗――。
十数年前のほうが事件事故は少ないはずだが、こうあふれ返ると犯罪はなくならないのかと憂鬱になってくる。
工場の流れ作業って、こんな感じなのかなとか思えてくる。いや、刑事になっても同じような捜査をするのだろう。探偵になりたいと思っていた時とは、また違う感覚が十一朗の中で芽生えはじめていた。
その時だ。誰よりもはやかった綾花の手がとまった。一枚の記事を見ながら震えている。ミス研の部室で見た、あの時を彷彿とさせるものだった。
「嘘、そんなの聞いてない。そんなの知らない」
綾花は念仏のように言葉を繰り返していた。途端に顔面蒼白になって噎せはじめた。慌てた裕貴が綾花に駆け寄る。十一朗は駆け寄る前に、彼女の異常を察知した。
「過呼吸だ! 落ち着け八木……俺の指が見えるか。俺の指に合わせて呼吸をしろ」
おそらく、新聞記事から信じ難いものを発見してしまったのだろう。そのために、精神的に混乱して過換気症を引き起こしてしまったのだ。死に直結するような症状ではないが、最悪の場合、失神することもある。
十一朗は綾花の正面に座って人差し指を立て、冷静に呼吸をすることを指示した。二酸化炭素の排出量を押さえるか、血中の二酸化炭素濃度を元に戻すのが有効な対処法とされているからだ。
立てて折り曲げてを繰り返すうちに、綾花の呼吸が正常に戻り、顔色も少しずつ赤みがさしてきた。
「もう大丈夫そうだな。無茶しなくてもいいから、帰って休んだほうがいいよ」
取り敢えずは安心だ――と、十一朗が思った途端。綾花が突然、落涙しながら抱きついてきた。しかも異常の前と同じ言葉を何度も繰り返している。
十一朗は頭の中が真っ白になってしまった。一瞬、紅潮しているのではないかと考えた。そして、目の前にいる裕貴と目が合った。すると、熱くなった体が一気に冷却されていく。
「オッケー。よし、落ち着こう。とにかく全員席に戻って……話はそれからだ」
皆に指示したものの、鼓動が静まらない。一番、落ち着いてないのは自分なのではないか。綾花の両肩をつかんで離した十一朗は、彼女を諭しながら席に着こうとした。
すると、綾花が十一朗の腕を取った。離れないでということか。困惑するしかない。
しかし、彼女の差し出したもう一方の手に、縮刷版の一冊が広げられていた。
「その記事の中に、父の名前が……私、知らなかった。ずっと」
途切れ途切れで話す綾花の手から縮刷版を受け取った。十一朗の視界にある記事が飛びこんできた。
『輸送車強盗殺傷事件』
発生したのは十一年前、十一朗が小学一年生の時だ。縮刷版なので記事の内容は詳細ではないが、残っていたところを見ると、かなり凄惨な事件だったのだろう。
『停車中に背後から襲われた輸送員がひとり死亡。ひとり重体。犯人は逃走中』
と印刷されていた。それよりも目にとまったのは死亡した人物の名前だった。『八木彰夫(あきお)』。
「まさか八木……君のお父さんって」
十一朗が訊いても、綾花は答えられずに首を横に振るだけだった。
『知らなかった。ずっと』という彼女の言葉が全てを表していた。綾花はこの記事を見てはじめて知ったのだ。父が死んだ本当の理由を――。