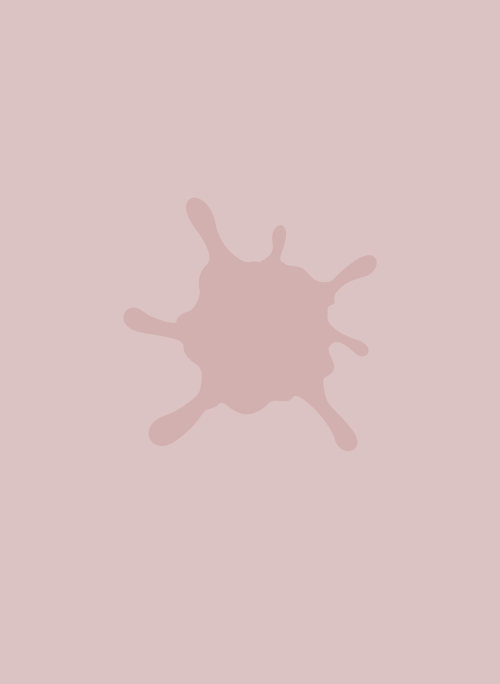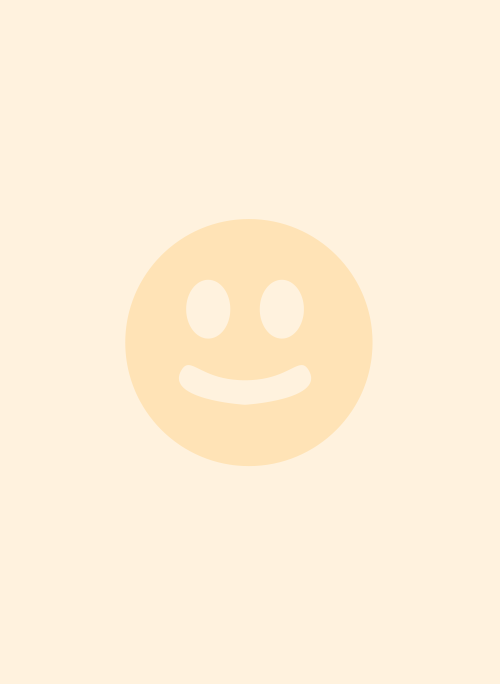街並みを前景に、紅く染まった夕陽が落ちていく。頭上では帰りの合図を仲間に知らせるカラスたちの鳴き声が繰り返されていた。
十一朗が現場に訪れたのは昨日のことだ。しかし、今日は鑑識課員の姿もなければ、刑事の姿もない。一般の通行も現在は許可されている。
前日に見た殺人現場と踏切を繋ぐ赤い斑点は、視認できないほど薄くなっていた。
凄惨な現場だ。ミス研部員といっても血糊を見る行為は適切ではないし、いいこととはいえない。十一朗は安堵の息を吐いた。
謎の男は遺書を綴りながら、殺害現場から踏切に向かって歩いている。そのたった百メートルの間で手にしていた紙を切り取り、ある筆記用具で文字を書いたのだ。
十一朗は男の遺書を不用意に見せてくれた貫野のお蔭で確認している。その遺書には特徴的な跡があった。それが『裏抜け』という、インクが紙の裏に染みこんだ状態だ。
何を探せばいいのか、十一朗はまだ話してはいない。裕貴たちは指示を待っていた。
「俺が立っているここから、踏切の手前の間に証拠が落ちているはずなんだ。それが、男が遺書を書くために使った筆記用具。万年筆だ」
「万年筆?」
十一朗の言葉に敏感に反応したのは綾花だった。そう、ここではわずか百メートルの間で書かれた遺書というのが、ひとつの謎となる。
裏抜けするような粗悪な紙に、万年筆という高級な筆記用具で書いたのは何故か?
あまりにも矛盾しているのだ。その謎に詰まった時、きっと誰もが考える。
その時、男が持っていた筆記用具は、万年筆だけだったのではないか。その万年筆は自分の所持品だったのか。
「ねえプラマイ。それって……」
次に問いかけてきたのは裕貴だった。推理スピードは遅いほうだが、今日は冴えている。
「なんとなくわかってきただろ。男は突発的に殺しをしている。それなのに遺書を書き、自殺未遂までした。誰かを庇っているのは確実なんだ。けど、そうなると疑問が残る。何故、犯行時に凶器を持っていたかということだ」
計画的犯行でなければ、凶器は手元にはないはずだ。だとしたら次に考えるのは、凶器を誰が持ってきたかということになる。
「凶器は共犯が用意した可能性が高い。主犯は意識不明の男じゃない。共犯者だ」
十一朗の推理に、綾花が唇を震わせていた。部室での会話を思い出したのかもしれない。『君のお母さんの利き手って……左か?』という十一朗の問いを。
「探すぞ。万年筆! 俺とプラマイが右側探すから、三島と八木は左側な」
重い空気を振り払うように、ワックスが率先して行動開始した。
十一朗はミス研のムードメーカーともいえる、ワックスのそんな部分に助けられてきた。
もし自分の推理だけで暴走していたら、裕貴も呆れて離れているだろうと思う。夢中になりすぎて、周りがよく見えていない瞬間があると自覚しているからだ。
そんな時にワックスは、必ずと言っていいほど修正の道を切り開いてくれる。
ミス研部員の証拠探しがはじまった。鑑識課員が見つけられなかった物だ。簡単に発見できるとは思えない。側溝や植え込みの中も調べる。
植え込みの中を覗いた途端に眩暈がした。缶やコンビニパンの袋が大量に落ちていたのだ。モラルまで捨ててしまったのだろうか。十一朗は重い息を吐きながら軍手をつけた。
こんなこともあろうかと用意してきて正解だった。ボランティア用のゴミ袋も持参しているので、通行人からしてみれば証拠集めなどとは思われないだろう。
面倒臭いのでゴミを纏めてつかむ。すると、右手に激痛が走った。何かが刺さったのだ。
「いって」
慌てて引っ込めた軍手が黒く染まっていた。流出したインクに間違いない。
「プラマイ、これ見つけたぜ」
不意に隣にいたワックスがエンジの物を十一朗に見せた。万年筆のキャップに間違いない。十一朗もつかみ出したゴミを取り分ける。その中に万年筆の本体があった。キャップがはずれていたために、ペン先が突き刺さったのだ。軍手を取ると血が滲んでいた。
「うわっ、最悪……」
それでも一回の手掴みで発見できたのは幸運だろう。暗くなると苦戦は確実だった。
「おーい。裕貴、八木、見つけたぞ」
十一朗の報告を聞いて、二人が駆け寄ってくる。
万年筆は土で汚れていたものの、原形をとどめていた。色を見ると女物だ。汚れを軍手で拭き取ると、文字が刻印されているのに気づいた。
『AYAKA.Y』と彫られている。謎の男と唯一繋がりのある綾花の名前だった。
十一朗が現場に訪れたのは昨日のことだ。しかし、今日は鑑識課員の姿もなければ、刑事の姿もない。一般の通行も現在は許可されている。
前日に見た殺人現場と踏切を繋ぐ赤い斑点は、視認できないほど薄くなっていた。
凄惨な現場だ。ミス研部員といっても血糊を見る行為は適切ではないし、いいこととはいえない。十一朗は安堵の息を吐いた。
謎の男は遺書を綴りながら、殺害現場から踏切に向かって歩いている。そのたった百メートルの間で手にしていた紙を切り取り、ある筆記用具で文字を書いたのだ。
十一朗は男の遺書を不用意に見せてくれた貫野のお蔭で確認している。その遺書には特徴的な跡があった。それが『裏抜け』という、インクが紙の裏に染みこんだ状態だ。
何を探せばいいのか、十一朗はまだ話してはいない。裕貴たちは指示を待っていた。
「俺が立っているここから、踏切の手前の間に証拠が落ちているはずなんだ。それが、男が遺書を書くために使った筆記用具。万年筆だ」
「万年筆?」
十一朗の言葉に敏感に反応したのは綾花だった。そう、ここではわずか百メートルの間で書かれた遺書というのが、ひとつの謎となる。
裏抜けするような粗悪な紙に、万年筆という高級な筆記用具で書いたのは何故か?
あまりにも矛盾しているのだ。その謎に詰まった時、きっと誰もが考える。
その時、男が持っていた筆記用具は、万年筆だけだったのではないか。その万年筆は自分の所持品だったのか。
「ねえプラマイ。それって……」
次に問いかけてきたのは裕貴だった。推理スピードは遅いほうだが、今日は冴えている。
「なんとなくわかってきただろ。男は突発的に殺しをしている。それなのに遺書を書き、自殺未遂までした。誰かを庇っているのは確実なんだ。けど、そうなると疑問が残る。何故、犯行時に凶器を持っていたかということだ」
計画的犯行でなければ、凶器は手元にはないはずだ。だとしたら次に考えるのは、凶器を誰が持ってきたかということになる。
「凶器は共犯が用意した可能性が高い。主犯は意識不明の男じゃない。共犯者だ」
十一朗の推理に、綾花が唇を震わせていた。部室での会話を思い出したのかもしれない。『君のお母さんの利き手って……左か?』という十一朗の問いを。
「探すぞ。万年筆! 俺とプラマイが右側探すから、三島と八木は左側な」
重い空気を振り払うように、ワックスが率先して行動開始した。
十一朗はミス研のムードメーカーともいえる、ワックスのそんな部分に助けられてきた。
もし自分の推理だけで暴走していたら、裕貴も呆れて離れているだろうと思う。夢中になりすぎて、周りがよく見えていない瞬間があると自覚しているからだ。
そんな時にワックスは、必ずと言っていいほど修正の道を切り開いてくれる。
ミス研部員の証拠探しがはじまった。鑑識課員が見つけられなかった物だ。簡単に発見できるとは思えない。側溝や植え込みの中も調べる。
植え込みの中を覗いた途端に眩暈がした。缶やコンビニパンの袋が大量に落ちていたのだ。モラルまで捨ててしまったのだろうか。十一朗は重い息を吐きながら軍手をつけた。
こんなこともあろうかと用意してきて正解だった。ボランティア用のゴミ袋も持参しているので、通行人からしてみれば証拠集めなどとは思われないだろう。
面倒臭いのでゴミを纏めてつかむ。すると、右手に激痛が走った。何かが刺さったのだ。
「いって」
慌てて引っ込めた軍手が黒く染まっていた。流出したインクに間違いない。
「プラマイ、これ見つけたぜ」
不意に隣にいたワックスがエンジの物を十一朗に見せた。万年筆のキャップに間違いない。十一朗もつかみ出したゴミを取り分ける。その中に万年筆の本体があった。キャップがはずれていたために、ペン先が突き刺さったのだ。軍手を取ると血が滲んでいた。
「うわっ、最悪……」
それでも一回の手掴みで発見できたのは幸運だろう。暗くなると苦戦は確実だった。
「おーい。裕貴、八木、見つけたぞ」
十一朗の報告を聞いて、二人が駆け寄ってくる。
万年筆は土で汚れていたものの、原形をとどめていた。色を見ると女物だ。汚れを軍手で拭き取ると、文字が刻印されているのに気づいた。
『AYAKA.Y』と彫られている。謎の男と唯一繋がりのある綾花の名前だった。