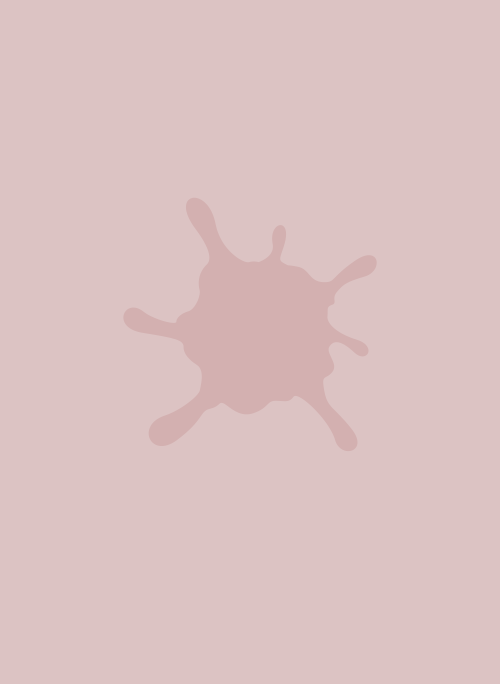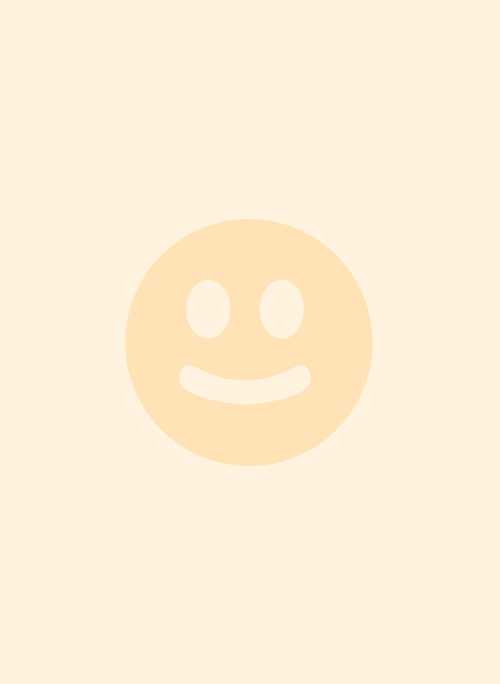翌朝六時――目覚まし時計で数分狂わずに起床した十一朗は、いつものように一家団欒の食卓についた。
しかし、今朝はいつもと様子が違っていた。寡黙な父が新聞を開くことなく、十一朗を見つめていた。ふと、十一朗の中で昨晩の貫野の一言が引き出された。
『お前は一度、親御さんに叱ってもらわなきゃ駄目だな……終わったら、絶対に電話してやる。覚悟しとけよ!』
忠告通りに連絡されたのだなと確信した。母も詳細を聞いたのだろう。席に着くことなく心配そうに事の進行を窺っていた。
「話は貫野に聞いた。また事件に首を突っこんだそうだな……お前はまだ高校生だ。出しゃばった真似はするな」
父の叱責に十一朗は全身の血液が沸騰するような体温の上昇を感じた。『出しゃばった』という言いかたは癇に障った。思わず身を乗り出して父に反論した。
「俺が進路の話をはじめるといつも話題をそらす癖に、問題起こした時だけ口出しすんのかよ! 親父は俺の進路をどう思ってるんだ。あの日から何も聞いてないぞ!」
『お前は刑事に向いている』それが父の口癖だった。それなのに、あの日から『刑事』の文字すら父の口から出ていない。
言い終わってから十一朗は我に返った。面と向かって父に『親父』と言ったのははじめてだった。封印してきた本音を正面から叩きつけたのもはじめてだ。全てがはじめてづくし。
様子を窺っていた母が包丁を手に、直立不動のまま立ち尽くしていた。
テレビに映ったニュースキャスターが淡々と雲の流れを説明する声だけが、キッチンに響く。普段、和気あいあいとした憩いの場に、呼吸困難になりそうな張り詰めた空間が形成された。
あの日を語らないのは、父と母が決めた暗黙の了解のようだった。十一朗だけが外れ者になっていたのだ。この状況を打破しなければ物事は解決しないと十一朗は考えた。
あの日より自分は成長している。だが、人生の岐路という進路の場に立って悩み続けてきたのも事実だ。今は背中を押してくれる両親の一言が欲しかった。
「コーヒーに砂糖は入れる? グラニュー糖切らしちゃったみたいなのよね」
胃が痛むような重厚な対立を前に、母が降参の白旗をあげて話題をそらした。
しかし、十一朗は引いた架線を切り落とすつもりはなかった。
「母さんはどう考えているんだよ? 俺は大学にいくけど、その先は気にならないのか?」
母は父に返答を求めるように視線を動かすと、十一朗に詰めた弁当を差し出して答えた。
「誰かの指図を受けて決めるものじゃない。あなたの将来はあなたが決めるものでしょ」
大人が辿り着くであろう尤もな意見を母は語った。父は同意もせずに新聞を開いた。
それを見た十一朗は父の新聞を奪い取った。母が両手で口を押さえて声をあげかける。
「俺が刑事になったら、父さんはどう思うか聞いてんだよ。刑事部長の息子っていう肩書きは俺は嫌いだ。俺は俺だ。比べられる重圧だって知ってる。本当は――」
俺の求める進路は探偵なんかじゃないんだ……言いかけて十一朗は口を閉ざした。父の背中を追い続けてきてはいたが、現場で働く父の姿を見たことはなかった。
刑事の顔をした父を見たのは久保の事件がはじめてだった。現れた威厳溢れる父の姿に息を呑んだ。それは一瞬の出来事だったが、十一朗にとっては将来の変更を考えさせられた瞬間となったのだ。
十一朗が奪い取った新聞を丸めて手にした父は、カバンを取って立ちあがった。
その丸めた新聞で十一朗は頭を叩かれた。思わぬ父の行動に驚いて顔をあげる。すると、あの日から忘れていた父の笑顔がそこにあった。
「そうだな、お前はお前だよ。だけどこれだけは忘れるな。お前は俺の誇りある一人息子だ。それは何があっても変わらない」
聞いて胸が熱くなった。父は自分を避けていたわけではない。認めていてくれたからこそ、静かに見守り続けていてくれたのだとわかった。
安堵した母から手製の弁当を受け取った父は、再び十一朗に視線を向けて言った。
「親父と言われるのも、悪くないな」
父に声をかけようとした十一朗だったが、紡いだ文字を脳内で変更した。
「親父! 仕事、行ってらっしゃい」
右手をあげて玄関を出た父の姿は、久保の時に見た威厳溢れるものとは違うが、更に大きく見えた。
しかし、今朝はいつもと様子が違っていた。寡黙な父が新聞を開くことなく、十一朗を見つめていた。ふと、十一朗の中で昨晩の貫野の一言が引き出された。
『お前は一度、親御さんに叱ってもらわなきゃ駄目だな……終わったら、絶対に電話してやる。覚悟しとけよ!』
忠告通りに連絡されたのだなと確信した。母も詳細を聞いたのだろう。席に着くことなく心配そうに事の進行を窺っていた。
「話は貫野に聞いた。また事件に首を突っこんだそうだな……お前はまだ高校生だ。出しゃばった真似はするな」
父の叱責に十一朗は全身の血液が沸騰するような体温の上昇を感じた。『出しゃばった』という言いかたは癇に障った。思わず身を乗り出して父に反論した。
「俺が進路の話をはじめるといつも話題をそらす癖に、問題起こした時だけ口出しすんのかよ! 親父は俺の進路をどう思ってるんだ。あの日から何も聞いてないぞ!」
『お前は刑事に向いている』それが父の口癖だった。それなのに、あの日から『刑事』の文字すら父の口から出ていない。
言い終わってから十一朗は我に返った。面と向かって父に『親父』と言ったのははじめてだった。封印してきた本音を正面から叩きつけたのもはじめてだ。全てがはじめてづくし。
様子を窺っていた母が包丁を手に、直立不動のまま立ち尽くしていた。
テレビに映ったニュースキャスターが淡々と雲の流れを説明する声だけが、キッチンに響く。普段、和気あいあいとした憩いの場に、呼吸困難になりそうな張り詰めた空間が形成された。
あの日を語らないのは、父と母が決めた暗黙の了解のようだった。十一朗だけが外れ者になっていたのだ。この状況を打破しなければ物事は解決しないと十一朗は考えた。
あの日より自分は成長している。だが、人生の岐路という進路の場に立って悩み続けてきたのも事実だ。今は背中を押してくれる両親の一言が欲しかった。
「コーヒーに砂糖は入れる? グラニュー糖切らしちゃったみたいなのよね」
胃が痛むような重厚な対立を前に、母が降参の白旗をあげて話題をそらした。
しかし、十一朗は引いた架線を切り落とすつもりはなかった。
「母さんはどう考えているんだよ? 俺は大学にいくけど、その先は気にならないのか?」
母は父に返答を求めるように視線を動かすと、十一朗に詰めた弁当を差し出して答えた。
「誰かの指図を受けて決めるものじゃない。あなたの将来はあなたが決めるものでしょ」
大人が辿り着くであろう尤もな意見を母は語った。父は同意もせずに新聞を開いた。
それを見た十一朗は父の新聞を奪い取った。母が両手で口を押さえて声をあげかける。
「俺が刑事になったら、父さんはどう思うか聞いてんだよ。刑事部長の息子っていう肩書きは俺は嫌いだ。俺は俺だ。比べられる重圧だって知ってる。本当は――」
俺の求める進路は探偵なんかじゃないんだ……言いかけて十一朗は口を閉ざした。父の背中を追い続けてきてはいたが、現場で働く父の姿を見たことはなかった。
刑事の顔をした父を見たのは久保の事件がはじめてだった。現れた威厳溢れる父の姿に息を呑んだ。それは一瞬の出来事だったが、十一朗にとっては将来の変更を考えさせられた瞬間となったのだ。
十一朗が奪い取った新聞を丸めて手にした父は、カバンを取って立ちあがった。
その丸めた新聞で十一朗は頭を叩かれた。思わぬ父の行動に驚いて顔をあげる。すると、あの日から忘れていた父の笑顔がそこにあった。
「そうだな、お前はお前だよ。だけどこれだけは忘れるな。お前は俺の誇りある一人息子だ。それは何があっても変わらない」
聞いて胸が熱くなった。父は自分を避けていたわけではない。認めていてくれたからこそ、静かに見守り続けていてくれたのだとわかった。
安堵した母から手製の弁当を受け取った父は、再び十一朗に視線を向けて言った。
「親父と言われるのも、悪くないな」
父に声をかけようとした十一朗だったが、紡いだ文字を脳内で変更した。
「親父! 仕事、行ってらっしゃい」
右手をあげて玄関を出た父の姿は、久保の時に見た威厳溢れるものとは違うが、更に大きく見えた。