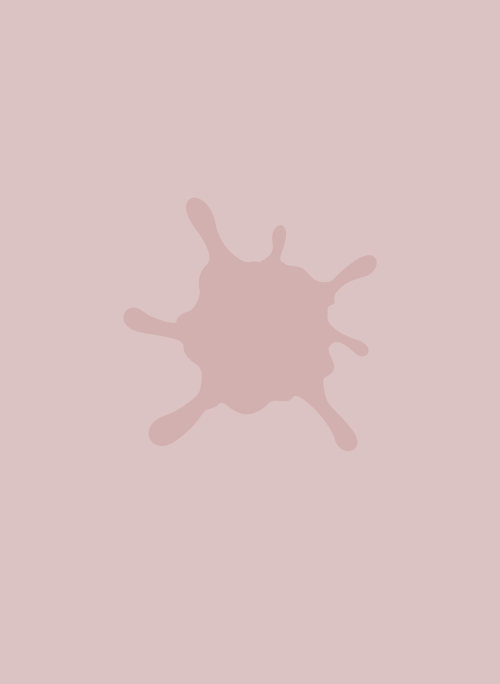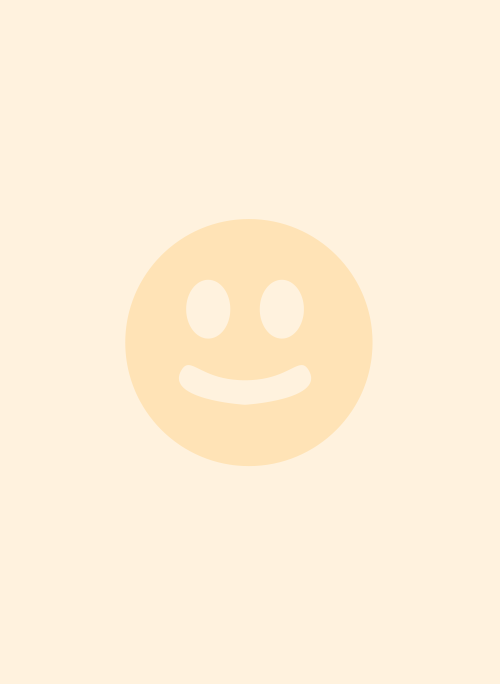十一朗が現場に着いた時には、すでに陽も落ちて、周囲は闇に包まれようとしていた。
暗くなってしまえば捜索活動は難航する。今日の捜査はここまでと決めたのか、鑑識が撤収作業をはじめているところだった。
停車した車から真っ先に降りた十一朗は、その場で一回転しながら辺りを観察した。
殺害現場の路地を出て、左折すると謎の男が自殺未遂した踏切が見える。距離は約百メートルといったところだろうか。
刺した男の返り血を浴びたのだろう。謎の男が進んだ軌跡を示すように、赤い斑点が殺害現場と踏切を結んでいた。
十一朗は反転すると、現場に足を向けた。追うように降りてきた貫野が歩いてくる。
殺害現場で足をとめた十一朗は、その場にしゃがみ込んだ。死んだ男が残した血糊を、入念に観察する。
薄暗くなってはいるが、路面に付着した夥しいまでの血痕は確認でき、事件の壮絶さを物語っていた。
十一朗の背後で貫野が「はあ」と疲れた声を出す。
「普通、高校生が死んだ奴の血糊を真剣に見るか? ねーよ。もう、どうにかしてくれよ。こいつのこと」
貫野の悲鳴を横に、文目も苦笑いをする。その時、二人とは違う足音が近づいてきた。
十一朗が顔をあげると、そこには久保殺害現場で会った鑑識のひとりが立っていた。
「十一朗くん、何か疑問でも? こっちに差し支えないことなら話すけど……」
鑑識員の意外な言葉に、貫野のほうが仰天した。「ちょっと待て」と即座に割って入る。
「高校生相手におかしいだろ! いくら刑事部長の息子でも、それは駄目だ」
貫野の忠告に、鑑識員は間違ったことはしてないと言うように、逆に目を白黒させた。
「あれ、貫野刑事、知らないんですか? 五年前の話。刑事部長が非番中に現行犯逮捕した男がいたじゃないですか。あれ、十一朗くんの助言があったからできたって話ですよ」
聞いた貫野と文目が同時に十一朗を見た。思わぬ話題の変換に十一朗は頭を抱える。
「あれは、俺が偶然気づいたってだけで、父さんでも見たていたらわかったはずだって……」
それは、十一朗が中学入学を控えた頃だった。
小さくなった学習机を買い替えようという話になって、父と母とともに家を出た。
目的の学習机も望み以上の素晴らしい物が見つかって、気持ち豊かに駐車場に向かおうとした時だ。目の前の交差点で、幼女が車に轢かれた。
頭から血を流し倒れこんだまま微動だにしない。その場にいた誰もが少女が信号無視で飛び出して轢かれたと思っていた。
しかし、倒れこんだ少女を見た十一朗は近くにいた男を指差して、父に指示を出した。
「父さん、あいつが犯人だ。すぐに取り押さえて事情聴取して!」
突然出された息子の発言に戸惑った父だったが、男と目があった途端、相手は逃げ出した。いきなり逃げ出した男を、疑わない刑事はいない。
その場で男は取り押さえられ、あっけなく自分が幼女を押したのだと自供した。
「十一朗……何故、あいつが犯人だと、わかったんだ?」
聞いた父に向かって十一朗は、何の躊躇もなく言い切った。
「だって、あの子の背中に足跡(ゲソコン)があるじゃないか。あの足跡、あの靴のメーカーだよ。あの子の近くにいて、あの靴を履いていたのは、あいつだけだったから」
男は信号待ちをする幼女の背後に立つと、車がくるのを見て蹴り飛ばしたのだ。幼女の背中にある足跡が、はっきりとそれを示していた。
しかし、実はその足跡はタイヤ跡と重なっていて、判別が難しかったという。
翌日――新聞の地域欄に『小学校六年生の冷静な判断で、犯人が現行犯逮捕』という、恥ずかしいくらい大きな十一朗の写真と記事が載っていた。
母は「この子は私の誇りです」と喜んだ。しかし、父は前までは「刑事を目指すといい」と言っていたのに、この一件以来、十一朗の将来について一切語らなくなった。
父さんは俺と係わるのが嫌になったのかもしれない。十一朗はそう感じていた。
夢は刑事だった。だけど、このまま父さんと話せないくらいだったら違う世界に――。
事実、十一朗が刑事に執着がないと知ると、父は障りなく話をするようになった。将来は探偵と決めたのは、そんな裏の事情もあったのだ。
十一朗の過去話を淡々と貫野や文目に話す鑑識員を横に、十一朗は路面を見つめた。
「鑑識さん、ちょっと疑問に思ったことがあるんだけど。自殺未遂をした人の着用物とか、見ることはできないかな?」
十一朗の要望に鑑識員は嫌そうな顔をするのではなく、逆に興奮したように鼻息を荒くし、着用物を映した写真を収めたファイルを持ってきた。
もはや、証拠大開放祭りだ。絶対に有り得ない状況に貫野が頭を抱えていた。
「これが着用物の写真ですね。実は僕も疑問に思っていたことが……なので、僕の推論と十一朗くんの見解が同じか是非、お話を頂戴したい」
何が疑問点なのか、鑑識員は敢えて言わなかった。貫野と文目も覗きこむ。
十一朗は前に予測した通りの違和感を捉えて、鑑識員を見た。
「致命傷は最後の一突きで傷は心臓の大動脈に達していたんだよな。それにしては浴びている血の量が少ない」
心臓は体内に血液を巡らすポンプだ。その心臓の中でも太い大動脈を貫けば、刃物を抜いた瞬間、夥しいまでの鮮血が飛び散る。
見せてもらった服の写真は、その血の跡がほとんど見当たらない。着用物に付着しなくても、路面には相当量の血の痕跡が残されるはずだ。それが現場にはない。
相当量の鮮血を浴びた者が存在する。そしてそれは、自殺未遂をした男ではない。
やはり被疑者とされる意識不明の男は主犯ではないのではないか。左利きの人物が主犯なのではないか。
「あと、ここに残った血の跡って、なんか変じゃないか?」
十一朗が指差した場所を見た鑑識員が、「やはり、そこに目をつけられましたか」と目上の者に語るような丁寧な口調で返した。
暗くなってしまえば捜索活動は難航する。今日の捜査はここまでと決めたのか、鑑識が撤収作業をはじめているところだった。
停車した車から真っ先に降りた十一朗は、その場で一回転しながら辺りを観察した。
殺害現場の路地を出て、左折すると謎の男が自殺未遂した踏切が見える。距離は約百メートルといったところだろうか。
刺した男の返り血を浴びたのだろう。謎の男が進んだ軌跡を示すように、赤い斑点が殺害現場と踏切を結んでいた。
十一朗は反転すると、現場に足を向けた。追うように降りてきた貫野が歩いてくる。
殺害現場で足をとめた十一朗は、その場にしゃがみ込んだ。死んだ男が残した血糊を、入念に観察する。
薄暗くなってはいるが、路面に付着した夥しいまでの血痕は確認でき、事件の壮絶さを物語っていた。
十一朗の背後で貫野が「はあ」と疲れた声を出す。
「普通、高校生が死んだ奴の血糊を真剣に見るか? ねーよ。もう、どうにかしてくれよ。こいつのこと」
貫野の悲鳴を横に、文目も苦笑いをする。その時、二人とは違う足音が近づいてきた。
十一朗が顔をあげると、そこには久保殺害現場で会った鑑識のひとりが立っていた。
「十一朗くん、何か疑問でも? こっちに差し支えないことなら話すけど……」
鑑識員の意外な言葉に、貫野のほうが仰天した。「ちょっと待て」と即座に割って入る。
「高校生相手におかしいだろ! いくら刑事部長の息子でも、それは駄目だ」
貫野の忠告に、鑑識員は間違ったことはしてないと言うように、逆に目を白黒させた。
「あれ、貫野刑事、知らないんですか? 五年前の話。刑事部長が非番中に現行犯逮捕した男がいたじゃないですか。あれ、十一朗くんの助言があったからできたって話ですよ」
聞いた貫野と文目が同時に十一朗を見た。思わぬ話題の変換に十一朗は頭を抱える。
「あれは、俺が偶然気づいたってだけで、父さんでも見たていたらわかったはずだって……」
それは、十一朗が中学入学を控えた頃だった。
小さくなった学習机を買い替えようという話になって、父と母とともに家を出た。
目的の学習机も望み以上の素晴らしい物が見つかって、気持ち豊かに駐車場に向かおうとした時だ。目の前の交差点で、幼女が車に轢かれた。
頭から血を流し倒れこんだまま微動だにしない。その場にいた誰もが少女が信号無視で飛び出して轢かれたと思っていた。
しかし、倒れこんだ少女を見た十一朗は近くにいた男を指差して、父に指示を出した。
「父さん、あいつが犯人だ。すぐに取り押さえて事情聴取して!」
突然出された息子の発言に戸惑った父だったが、男と目があった途端、相手は逃げ出した。いきなり逃げ出した男を、疑わない刑事はいない。
その場で男は取り押さえられ、あっけなく自分が幼女を押したのだと自供した。
「十一朗……何故、あいつが犯人だと、わかったんだ?」
聞いた父に向かって十一朗は、何の躊躇もなく言い切った。
「だって、あの子の背中に足跡(ゲソコン)があるじゃないか。あの足跡、あの靴のメーカーだよ。あの子の近くにいて、あの靴を履いていたのは、あいつだけだったから」
男は信号待ちをする幼女の背後に立つと、車がくるのを見て蹴り飛ばしたのだ。幼女の背中にある足跡が、はっきりとそれを示していた。
しかし、実はその足跡はタイヤ跡と重なっていて、判別が難しかったという。
翌日――新聞の地域欄に『小学校六年生の冷静な判断で、犯人が現行犯逮捕』という、恥ずかしいくらい大きな十一朗の写真と記事が載っていた。
母は「この子は私の誇りです」と喜んだ。しかし、父は前までは「刑事を目指すといい」と言っていたのに、この一件以来、十一朗の将来について一切語らなくなった。
父さんは俺と係わるのが嫌になったのかもしれない。十一朗はそう感じていた。
夢は刑事だった。だけど、このまま父さんと話せないくらいだったら違う世界に――。
事実、十一朗が刑事に執着がないと知ると、父は障りなく話をするようになった。将来は探偵と決めたのは、そんな裏の事情もあったのだ。
十一朗の過去話を淡々と貫野や文目に話す鑑識員を横に、十一朗は路面を見つめた。
「鑑識さん、ちょっと疑問に思ったことがあるんだけど。自殺未遂をした人の着用物とか、見ることはできないかな?」
十一朗の要望に鑑識員は嫌そうな顔をするのではなく、逆に興奮したように鼻息を荒くし、着用物を映した写真を収めたファイルを持ってきた。
もはや、証拠大開放祭りだ。絶対に有り得ない状況に貫野が頭を抱えていた。
「これが着用物の写真ですね。実は僕も疑問に思っていたことが……なので、僕の推論と十一朗くんの見解が同じか是非、お話を頂戴したい」
何が疑問点なのか、鑑識員は敢えて言わなかった。貫野と文目も覗きこむ。
十一朗は前に予測した通りの違和感を捉えて、鑑識員を見た。
「致命傷は最後の一突きで傷は心臓の大動脈に達していたんだよな。それにしては浴びている血の量が少ない」
心臓は体内に血液を巡らすポンプだ。その心臓の中でも太い大動脈を貫けば、刃物を抜いた瞬間、夥しいまでの鮮血が飛び散る。
見せてもらった服の写真は、その血の跡がほとんど見当たらない。着用物に付着しなくても、路面には相当量の血の痕跡が残されるはずだ。それが現場にはない。
相当量の鮮血を浴びた者が存在する。そしてそれは、自殺未遂をした男ではない。
やはり被疑者とされる意識不明の男は主犯ではないのではないか。左利きの人物が主犯なのではないか。
「あと、ここに残った血の跡って、なんか変じゃないか?」
十一朗が指差した場所を見た鑑識員が、「やはり、そこに目をつけられましたか」と目上の者に語るような丁寧な口調で返した。