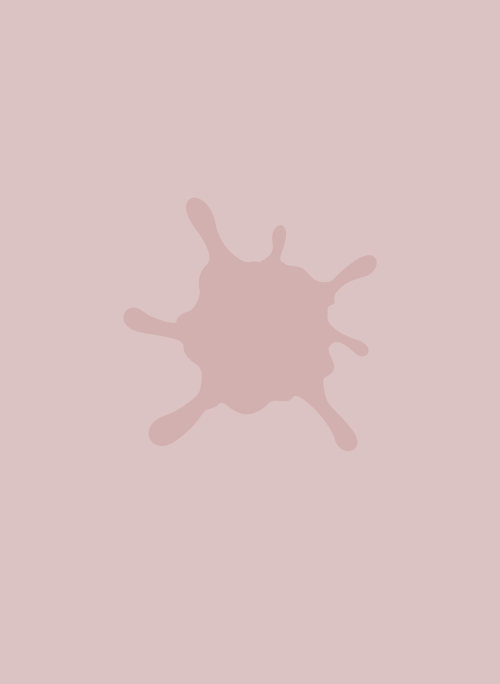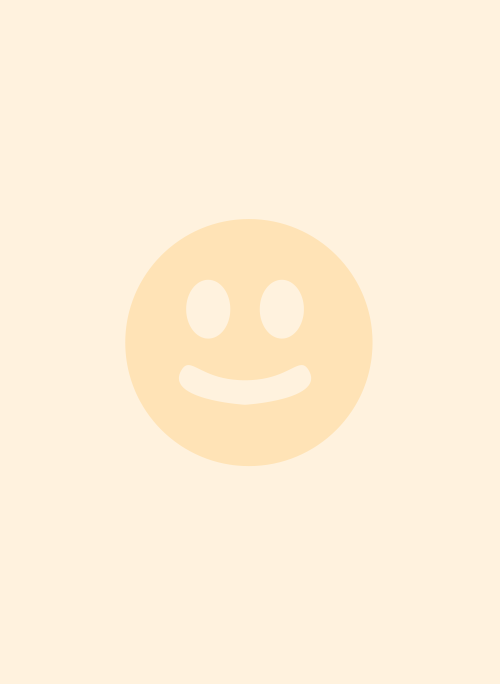飛び込み自殺をした男を知らない。
綾花はその証言だけすると口ごもってしまった。男の素性を本当に知らないのか。それとも隠したいだけなのか。
その胸中は口を閉ざす本人しか捉え切れないものであると同時に、追及して吐かせないことにはわかり得ないものだ。
相手は高校一年生の女子。無理に連行するのは貫野も気が引けるのだろう。
貫野は手袋をはめた手で袋に入った紙を慎重に取り出すと、綾花の前に突き出した。
「わかるか? 紙には数字が書かれていた。これが電話番号だと気づいてかけたら、あんたの携帯に繋がった。で、ここに呼び出したってわけだ」
貫野の説明が終わるまで、綾花は視線を床に落とし続けていた。裕貴が促すように綾花の耳元で小さく囁く。
「大丈夫。信頼できる刑事さんだから、知っていることは全部教えてあげて」
横にいた十一朗には、はっきりと裕貴の声が聞き取れた。貫野には聞こえたのだろうか。何の反応も見せていないので聞こえていないだろう。
しかし、優しく促されても綾花は首を振った。
男を知らない――これは事実なのかもしれない。十一朗は確信した。これ以上聞いても彼女は何も話せないのだろう。
「分かった。じゃあ、もう何も聞かないよ」
十一朗の言葉を聞いて、貫野が「おいおい」と割りこんできた。『また刑事面して、事件に足突っ込んでくれる気かよ……』それが貫野の言い分に違いない。
「知らないって言っているんだから、もう聞くなよ。時には紳士的に行動しないと、貫野刑事、いつまでたっても結婚できないぞ」
十一朗の戒めに、貫野はこめかみを引き攣らせ、ほぼ同時に文目が爆笑した。
静寂包む病院内なので、少しでも声が大きければ非常に目立つ。患者の検診時刻なのか、病室の出入りをしていた看護師が、鬼の形相でこちらを睨みつけていた。
部下の失態で恥をかいたのと、図星を刺されたのが相当気にくわなかったのだろう。
貫野は積もり積もった十一朗への怒りを発散させるかのように、文目の頭を手帳で叩く。
毎回、十一朗は感じている。父が刑事部長でなければ、とっくに貫野は暴行を仕掛けてきていて、裁判沙汰になっているだろうと。
顔をあげた綾花は貫野に目を向けると、冷静に思い出すかのように語りはじめた。
「電話で内容を聞いた時には、母が飛び込み自殺をしたものだと思ったんです。だけど、寝ていたのは知らない男のかたで……」
納得しきれていないのか貫野が妙な舌打ちをする。刑事というより悪人にしか見えない。
十一朗は相変わらずの、いい加減な判断と行動に呆れながら貫野を見た。
「どうせ電話で詳細を語らなかったんだろ。あんたの親が電車に飛び込み自殺したって、言ったんじゃないか? 『あんたの携帯番号を持っていた男が、電車に飛び込み自殺した』って言わなきゃいけないのに」
これも図星だったのだろう。貫野が一歩引いて言葉にならない唸り声を出した。
すると、貫野は逃げ場を失ったのか、十一朗たちミス研全員を追い払うかのような手の動きを見せる。
「あーっ、わかった。全部信じたわけじゃないが、今回は放免だ。また事情聴取するかもしれないが、全ては他が繋がってからだ。いけ」
いけと言われても、十一朗たちが全面的にいうことを聞く必要はない。
「裕貴、八木さんを送ってあげてくれ。俺はもう少し、ここに残る」
十一朗の発言に、まずワックスが動揺した。自分はどちら側につけばいいのか、選択仕兼ねているのだ。
困った挙句に不機嫌そうに睨みつける貫野と目が合い、ワックスは裕貴のほうについた。
「じゃあ、帰るね。貫野巡査……じゃなかった。警部補を困らせたら駄目だよ」
途中で失言したことに気づいた裕貴が慌てて訂正するが、完全に周りには聞こえている。
反射的にというか貫野は、部下の文目に目を向けて拳を握り締めた。今度こそ叩かれては困ると、文目は笑いを堪えるのに必死になっている。
裕貴たちがエレベーターに乗って姿が見えなくなるまで、十一朗と貫野、文目の三名は黙り続け、三階を示したランプが一階になったところで、ようやく向き合った。
綾花はその証言だけすると口ごもってしまった。男の素性を本当に知らないのか。それとも隠したいだけなのか。
その胸中は口を閉ざす本人しか捉え切れないものであると同時に、追及して吐かせないことにはわかり得ないものだ。
相手は高校一年生の女子。無理に連行するのは貫野も気が引けるのだろう。
貫野は手袋をはめた手で袋に入った紙を慎重に取り出すと、綾花の前に突き出した。
「わかるか? 紙には数字が書かれていた。これが電話番号だと気づいてかけたら、あんたの携帯に繋がった。で、ここに呼び出したってわけだ」
貫野の説明が終わるまで、綾花は視線を床に落とし続けていた。裕貴が促すように綾花の耳元で小さく囁く。
「大丈夫。信頼できる刑事さんだから、知っていることは全部教えてあげて」
横にいた十一朗には、はっきりと裕貴の声が聞き取れた。貫野には聞こえたのだろうか。何の反応も見せていないので聞こえていないだろう。
しかし、優しく促されても綾花は首を振った。
男を知らない――これは事実なのかもしれない。十一朗は確信した。これ以上聞いても彼女は何も話せないのだろう。
「分かった。じゃあ、もう何も聞かないよ」
十一朗の言葉を聞いて、貫野が「おいおい」と割りこんできた。『また刑事面して、事件に足突っ込んでくれる気かよ……』それが貫野の言い分に違いない。
「知らないって言っているんだから、もう聞くなよ。時には紳士的に行動しないと、貫野刑事、いつまでたっても結婚できないぞ」
十一朗の戒めに、貫野はこめかみを引き攣らせ、ほぼ同時に文目が爆笑した。
静寂包む病院内なので、少しでも声が大きければ非常に目立つ。患者の検診時刻なのか、病室の出入りをしていた看護師が、鬼の形相でこちらを睨みつけていた。
部下の失態で恥をかいたのと、図星を刺されたのが相当気にくわなかったのだろう。
貫野は積もり積もった十一朗への怒りを発散させるかのように、文目の頭を手帳で叩く。
毎回、十一朗は感じている。父が刑事部長でなければ、とっくに貫野は暴行を仕掛けてきていて、裁判沙汰になっているだろうと。
顔をあげた綾花は貫野に目を向けると、冷静に思い出すかのように語りはじめた。
「電話で内容を聞いた時には、母が飛び込み自殺をしたものだと思ったんです。だけど、寝ていたのは知らない男のかたで……」
納得しきれていないのか貫野が妙な舌打ちをする。刑事というより悪人にしか見えない。
十一朗は相変わらずの、いい加減な判断と行動に呆れながら貫野を見た。
「どうせ電話で詳細を語らなかったんだろ。あんたの親が電車に飛び込み自殺したって、言ったんじゃないか? 『あんたの携帯番号を持っていた男が、電車に飛び込み自殺した』って言わなきゃいけないのに」
これも図星だったのだろう。貫野が一歩引いて言葉にならない唸り声を出した。
すると、貫野は逃げ場を失ったのか、十一朗たちミス研全員を追い払うかのような手の動きを見せる。
「あーっ、わかった。全部信じたわけじゃないが、今回は放免だ。また事情聴取するかもしれないが、全ては他が繋がってからだ。いけ」
いけと言われても、十一朗たちが全面的にいうことを聞く必要はない。
「裕貴、八木さんを送ってあげてくれ。俺はもう少し、ここに残る」
十一朗の発言に、まずワックスが動揺した。自分はどちら側につけばいいのか、選択仕兼ねているのだ。
困った挙句に不機嫌そうに睨みつける貫野と目が合い、ワックスは裕貴のほうについた。
「じゃあ、帰るね。貫野巡査……じゃなかった。警部補を困らせたら駄目だよ」
途中で失言したことに気づいた裕貴が慌てて訂正するが、完全に周りには聞こえている。
反射的にというか貫野は、部下の文目に目を向けて拳を握り締めた。今度こそ叩かれては困ると、文目は笑いを堪えるのに必死になっている。
裕貴たちがエレベーターに乗って姿が見えなくなるまで、十一朗と貫野、文目の三名は黙り続け、三階を示したランプが一階になったところで、ようやく向き合った。