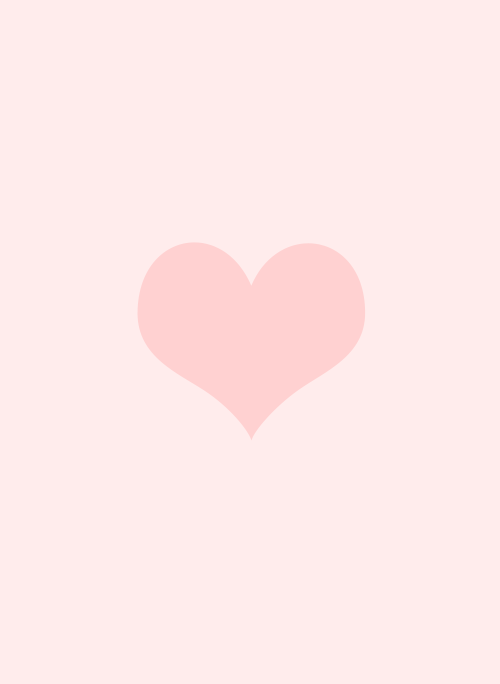そんな周囲の状況を考えれば、「とにかく、入籍する」と言い張る翔平君の願いをすぐに叶えてあげることは難しい。
もちろん、私も早く翔平君と結婚して、幸せな毎日を送りたいと思っているけれど、社会人として段取りを踏まなければならないことが次々と頭に浮かんで踏み切れない。
「そこで悩むところが白石のいいところでもあるけど、やっかいな欠点でもあるよな」
「な、なに、突然」
不意に聞こえた声に視線を上げると、小椋君がにやにやしながら立っていた。
「びっくりさせないでよ。それに、どうしたのよ。さっきまでパソコンの前でうなってたのに」
「まあな。いいデザインが浮かばないから休憩しようと思ってこの辺を歩いてたら、小難しい顔でひとりごとを言ってる見慣れた顔があったから、からかってやろうかと」
突然やって来たかと思えば私の向かいの席にさっさと腰掛けた小椋君は、カウンターの向こう側にいるマスターにコーヒーを注文した。
「で? どうするんだ?」
「え?」
「先週、水上さんがうちの事務所にきて白石との結婚を所長と相談してただろ?」
「うーん」
「え? もしかして、結婚したくないとか? 天下の水上翔平との結婚を断るなんて大それたこと、考えてるのか?」
「ま、まさかっ。子どもの頃から大好きな翔平君と結婚できなかったら、私は生きていけないし、そんなこと考えたくもない。ばかなこと言わないでよ」
からかわれているとわかっていても、私は小椋君の言葉に大きく反応してしまった。
翔平君との結婚を断るなんてあり得ない。
この週末に、翔平君は私の家に引っ越してくるし、その受入れ準備も完璧だ。
といっても、ほとんどの段取りは翔平君が整えてくれて、私は自分の物を地味に片づけた程度だけど。
翔平君の商売道具ともいえるパソコン関係は早々に運び込まれていて、セッティングも完了している。
毎日私の家に帰ってきては夜遅くまで仕事をしている翔平君の背中を見ながらベッドに潜るのにも慣れた。
そのまま朝まで何事もなく眠れるかといえばそうでもなくて、翔平君の熱のこもったあれやこれやに起こされるのにも……慣れた。
慣れたというよりも、待ちわびるようになったと自覚して恥ずかしくもあるけれど……。
とにかく、翔平君との暮らしは甘くて優しくて、とても幸せなのだ。