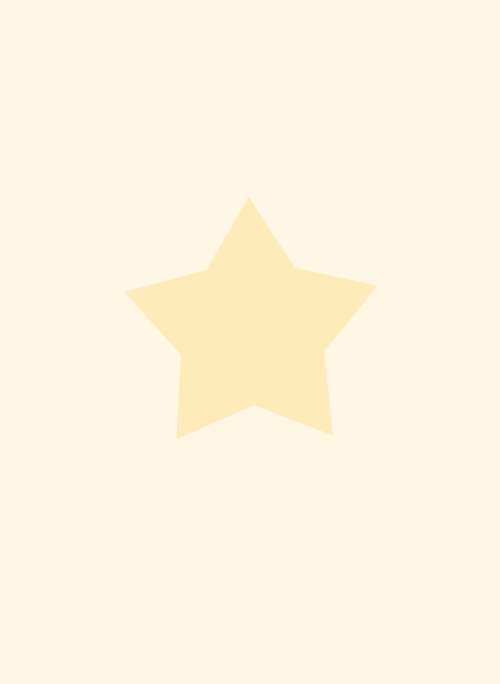「そう言えば兄妹みたいだったよなお前ら」
児玉が茶々を入れる。
「そんなことないよ」
治は一瞬ふさぎ込んだ。宮本がすかさず、
「ねえ、覚えてる?私が若林君に手紙渡したこと?」
わざとらしく明かるげに覗き込む。
「忘れたよそんなこと」
治は不機嫌に答えた。
「柴山さんのこと好きですかって書いて渡したじゃない、
おぼえてない?」
「おぼえてない!」
治はきっぱりと否定した。
「彼女返事がなくて落ち込んでたわよ」
「知らないよそんなこと。だって好きとか嫌いとかわからないよ小学生じゃ」
治はむきになった。ここぞとばかり宮本は食い下がる。
真剣なまなざしで、立ち止まり、
「じゃあ、今はどうなの?」
じっと治を見つめる宮本。思わず治も児玉も立ち止った。
「いや、それは・・・。それこそ妹みたいで。何というか
嫌いじゃないし。ちょっと太めだけど、どちらかというと、
好きだったかも」
3人はまたゆっくりと歩きだした。勝ち誇ったかのように宮本は、
「ほら見てごらん。はっきりと言ってほしかったのよ彼女。
その一言で幸せに死ねたのに。男ってホント鈍感なんだから」
児玉が茶々を入れる。
「そんなことないよ」
治は一瞬ふさぎ込んだ。宮本がすかさず、
「ねえ、覚えてる?私が若林君に手紙渡したこと?」
わざとらしく明かるげに覗き込む。
「忘れたよそんなこと」
治は不機嫌に答えた。
「柴山さんのこと好きですかって書いて渡したじゃない、
おぼえてない?」
「おぼえてない!」
治はきっぱりと否定した。
「彼女返事がなくて落ち込んでたわよ」
「知らないよそんなこと。だって好きとか嫌いとかわからないよ小学生じゃ」
治はむきになった。ここぞとばかり宮本は食い下がる。
真剣なまなざしで、立ち止まり、
「じゃあ、今はどうなの?」
じっと治を見つめる宮本。思わず治も児玉も立ち止った。
「いや、それは・・・。それこそ妹みたいで。何というか
嫌いじゃないし。ちょっと太めだけど、どちらかというと、
好きだったかも」
3人はまたゆっくりと歩きだした。勝ち誇ったかのように宮本は、
「ほら見てごらん。はっきりと言ってほしかったのよ彼女。
その一言で幸せに死ねたのに。男ってホント鈍感なんだから」