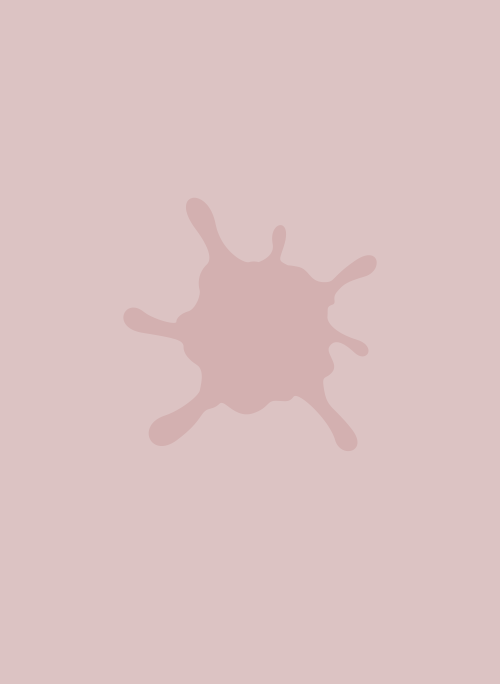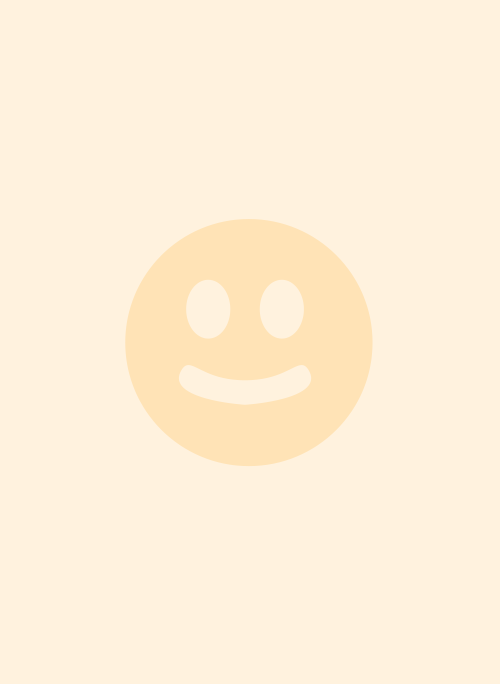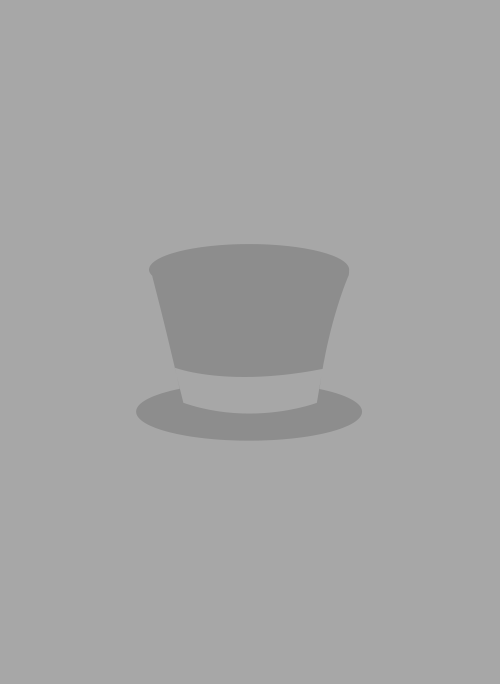ここは一面、見渡す限りの田園地帯、簡単に言ってしまうと田舎である。
社から転勤と通達を受けて一か月後、環境を一転して空気のまずい都心から、新鮮な空気の都外へ――
定年退職をした夫婦なら、羨ましいと口を揃えて言うのかもしれない。
だが、自分は若いし独り者。遊びたい盛りでもある。
繁華街も遊戯施設もデパートもないこんな場所で、どう人生を満喫しろというのだ?
引っ越しをすませ、一息ついた二週間後になって、ようやく田舎生活の苦労を男は思い知らされていた。
まず、スーパーに買い物に行こうとしても距離があり、車を出さなくてはならない。
そして、親友をつくろうにも趣味が合う仲間は近所にいないので、否が応でも孤独な生活に悲壮感を覚える。
「過疎地帯。出会いのない場所で、人生の楽しみといえば限られている……畑仕事でもはじめるか」
そう考えつくとすぐさま近場の畑を借り入れ、畑仕事に挑戦しはじめた。
ところが、はじめてみると畑仕事も意外に難しく、慣れない爬虫類や一般の図鑑に載ってない昆虫の出現に驚いて妙な悲鳴を上げたり、また、思いがけない天候の変化で農作物を全て駄目にしてしまうなど、失敗の連続ばかりであった。
しかし、妥協をせずに根気よく続けてみると実に奥が深い世界で、結構真剣に野菜をいかに立派に育てるか勉強し、天候を見極める技術も獲得し、更に土の成分から肥料にまでこだわった。
畑仕事をはじめて四か月の頃には、田舎の生物に驚くこともなくなり、蛇でも怖がることなく手掴みして放り投げるまで成長した。
その頃からである。
年配ではあるが栽培仲間の友人もできて、徐々にではあるが、田舎生活の楽しみを実感してきた。
ひとつ不満をあげるならば、夏の夜に蛙が騒がしく鳴くのが原因で、睡眠をろくにとれないことだろうか。
まあ、これは夏の時期だけ……一過性のものだし、我慢しよう。
季節が過ぎれば、この合唱も愛着あるものに思えてくることだろう。
一時的な転勤だから、社から戻ってくるようにと連絡がくるはずだ。一生涯ここで暮らす気はないが、定年退職したら老後をここで過ごすのも、悪くないかもしれない。
そう感じはじめた矢先、ある事件が男の身に降りかかった。
朝、新聞を取りに行くと必ず、玄関に大量の昆虫の死骸があるのだ。
一日目は、大して気にも留めなかった。
明りに反応した虫たちが群がって逃げ場を失い、力尽きたのだろう。
ほうきを取り出して奇麗に掃き取ると、ゴミ袋に入れて朝のうちに捨てた。
ただそれが二日、三日と続くと、さすがに怖くなって、誰が悪戯の犯人なのか詮索するようになった。
畑仕事の仲間だろうか……いや、彼らが犯人だと決めつけたくない。
互いに収穫した野菜を交換し、品評会までする大切な仲間たちだ。
では、社内の誰かに恨みを買い、身に覚えのない嫌がらせを受けているのだろうか?
それも考えられない。昇格競争には参加せず無欲で、仕事も他の者と相違なく、そつなくこなしている。
事件発生から二週間後――
休暇前日に徹夜する覚悟をし、絶対に犯人を捕まえてやると男は決めた。
玄関の扉越しに椅子を置いて、飲食物を準備する。
覗き穴から犯人の姿を確認したら、その場で取り押さえて、理由を問い詰めることにした。
時刻十二時。
玄関前を確認するが、昆虫の姿は見当たらない。
光に虫が集まって力尽き死んだというのは、大きな間違いだったようだ。
何十分かおきに、車が走り抜けるライトが見えたが、停車の様子もなく犯人ではないと男は断定した。
夜が深まり丑三つ時ともなると人影も明かりさえも消えて、漆黒の世界が広がる。
睡魔も徐々に襲いはじめてきて、眠気を栄養ドリンクや缶コーヒーで撃退させ、辛抱強く息を凝らし、犯人が現れる時を待ち続けた。
ふと男が気がつくと辺りは白みはじめ、犯人の姿を確認できないまま、朝を迎えてしまっていた。
「さすがに昨晩は、僕が見張っていると気づいてこなかったようだ。残念だな。徹夜までしたのに……」
今日、撃退したのだから、明日犯人が現れることもないだろう。
さすがに毎晩徹夜だと、体を壊すし仕事にも支障が出てしまう。
新聞配達のバイク音が近づいているのが聞こえ、扉を開けて朝刊を直接受け取ろうとする。
ところが、ありもしない現実を前にして男は言葉を失い、呆然とその場で立ち尽くした。
いつものように昆虫の死骸が、いつもより多く一纏めに整頓され山積みになっていたのだ。
近づいてきた新聞配達員に、思わず詰め寄って質問をする。
「君、怪しい奴を見なかったか! こんな悪戯をする奴に心当たりはないか」
男にしてみれば必死だった。
こんな気味の悪いことが、毎晩続くと想像しただけでも背筋が凍る思いがする。
積み上がった昆虫の死骸を見た新聞配達員は、深い息を吐いた。
私は関係ありません。あなた自身で解決してくださいといった様子だ。
「こんなに早起きして騒ぐのは、僕ら配達員かカエルくらいですよ。それに昨日もありましたよ。虫の死骸は……」
配達員の返答に、男は呆然と立ち尽くすことしかできない。
そんな。では深夜のうちに誰が姿も見せずに置いていったんだ?
怪奇現象か幽霊の仕業だろうか? しかし、そんな非科学的なものが存在するというのだろうか。
どちらにしろ謎のままだ。人間業ではない。
朝刊を受け取り、いつものように昆虫の死骸を集めてゴミ袋に入れる。
どうにも腑に落ちないまま家に入ると、受け取った新聞記事を読む。
徹夜が理由であろう。襲いかかってきた睡魔相手に、男は逆らうことなく床につくと体を横たえた。
蛙の合唱を聞きながら混濁していく意識の赴くままに、眠りに誘われ目を閉じる。
騒がしい真夏の蛙の合唱は、やむことなく昼夜響き渡っていた。
だがもし、この蛙の合唱が翻訳できたのなら、謎は全て解明されたかもしれない。
『蛇を投げ捨てて 命を救ってくれた恩人に今日も贈り物をするよ 山の幸のご馳走さ♪ 僕らの美しい合唱を 休むことなく続けるのさ♪ それが最高の感謝の気持ち♪♪』
※ ※ ※ ※
カエルたちにとっては誠心誠意。心をこめたプレゼントだったはず。
ここは大目に見てあげましょう。
さて、音符を違ういいかたにすると……?
社から転勤と通達を受けて一か月後、環境を一転して空気のまずい都心から、新鮮な空気の都外へ――
定年退職をした夫婦なら、羨ましいと口を揃えて言うのかもしれない。
だが、自分は若いし独り者。遊びたい盛りでもある。
繁華街も遊戯施設もデパートもないこんな場所で、どう人生を満喫しろというのだ?
引っ越しをすませ、一息ついた二週間後になって、ようやく田舎生活の苦労を男は思い知らされていた。
まず、スーパーに買い物に行こうとしても距離があり、車を出さなくてはならない。
そして、親友をつくろうにも趣味が合う仲間は近所にいないので、否が応でも孤独な生活に悲壮感を覚える。
「過疎地帯。出会いのない場所で、人生の楽しみといえば限られている……畑仕事でもはじめるか」
そう考えつくとすぐさま近場の畑を借り入れ、畑仕事に挑戦しはじめた。
ところが、はじめてみると畑仕事も意外に難しく、慣れない爬虫類や一般の図鑑に載ってない昆虫の出現に驚いて妙な悲鳴を上げたり、また、思いがけない天候の変化で農作物を全て駄目にしてしまうなど、失敗の連続ばかりであった。
しかし、妥協をせずに根気よく続けてみると実に奥が深い世界で、結構真剣に野菜をいかに立派に育てるか勉強し、天候を見極める技術も獲得し、更に土の成分から肥料にまでこだわった。
畑仕事をはじめて四か月の頃には、田舎の生物に驚くこともなくなり、蛇でも怖がることなく手掴みして放り投げるまで成長した。
その頃からである。
年配ではあるが栽培仲間の友人もできて、徐々にではあるが、田舎生活の楽しみを実感してきた。
ひとつ不満をあげるならば、夏の夜に蛙が騒がしく鳴くのが原因で、睡眠をろくにとれないことだろうか。
まあ、これは夏の時期だけ……一過性のものだし、我慢しよう。
季節が過ぎれば、この合唱も愛着あるものに思えてくることだろう。
一時的な転勤だから、社から戻ってくるようにと連絡がくるはずだ。一生涯ここで暮らす気はないが、定年退職したら老後をここで過ごすのも、悪くないかもしれない。
そう感じはじめた矢先、ある事件が男の身に降りかかった。
朝、新聞を取りに行くと必ず、玄関に大量の昆虫の死骸があるのだ。
一日目は、大して気にも留めなかった。
明りに反応した虫たちが群がって逃げ場を失い、力尽きたのだろう。
ほうきを取り出して奇麗に掃き取ると、ゴミ袋に入れて朝のうちに捨てた。
ただそれが二日、三日と続くと、さすがに怖くなって、誰が悪戯の犯人なのか詮索するようになった。
畑仕事の仲間だろうか……いや、彼らが犯人だと決めつけたくない。
互いに収穫した野菜を交換し、品評会までする大切な仲間たちだ。
では、社内の誰かに恨みを買い、身に覚えのない嫌がらせを受けているのだろうか?
それも考えられない。昇格競争には参加せず無欲で、仕事も他の者と相違なく、そつなくこなしている。
事件発生から二週間後――
休暇前日に徹夜する覚悟をし、絶対に犯人を捕まえてやると男は決めた。
玄関の扉越しに椅子を置いて、飲食物を準備する。
覗き穴から犯人の姿を確認したら、その場で取り押さえて、理由を問い詰めることにした。
時刻十二時。
玄関前を確認するが、昆虫の姿は見当たらない。
光に虫が集まって力尽き死んだというのは、大きな間違いだったようだ。
何十分かおきに、車が走り抜けるライトが見えたが、停車の様子もなく犯人ではないと男は断定した。
夜が深まり丑三つ時ともなると人影も明かりさえも消えて、漆黒の世界が広がる。
睡魔も徐々に襲いはじめてきて、眠気を栄養ドリンクや缶コーヒーで撃退させ、辛抱強く息を凝らし、犯人が現れる時を待ち続けた。
ふと男が気がつくと辺りは白みはじめ、犯人の姿を確認できないまま、朝を迎えてしまっていた。
「さすがに昨晩は、僕が見張っていると気づいてこなかったようだ。残念だな。徹夜までしたのに……」
今日、撃退したのだから、明日犯人が現れることもないだろう。
さすがに毎晩徹夜だと、体を壊すし仕事にも支障が出てしまう。
新聞配達のバイク音が近づいているのが聞こえ、扉を開けて朝刊を直接受け取ろうとする。
ところが、ありもしない現実を前にして男は言葉を失い、呆然とその場で立ち尽くした。
いつものように昆虫の死骸が、いつもより多く一纏めに整頓され山積みになっていたのだ。
近づいてきた新聞配達員に、思わず詰め寄って質問をする。
「君、怪しい奴を見なかったか! こんな悪戯をする奴に心当たりはないか」
男にしてみれば必死だった。
こんな気味の悪いことが、毎晩続くと想像しただけでも背筋が凍る思いがする。
積み上がった昆虫の死骸を見た新聞配達員は、深い息を吐いた。
私は関係ありません。あなた自身で解決してくださいといった様子だ。
「こんなに早起きして騒ぐのは、僕ら配達員かカエルくらいですよ。それに昨日もありましたよ。虫の死骸は……」
配達員の返答に、男は呆然と立ち尽くすことしかできない。
そんな。では深夜のうちに誰が姿も見せずに置いていったんだ?
怪奇現象か幽霊の仕業だろうか? しかし、そんな非科学的なものが存在するというのだろうか。
どちらにしろ謎のままだ。人間業ではない。
朝刊を受け取り、いつものように昆虫の死骸を集めてゴミ袋に入れる。
どうにも腑に落ちないまま家に入ると、受け取った新聞記事を読む。
徹夜が理由であろう。襲いかかってきた睡魔相手に、男は逆らうことなく床につくと体を横たえた。
蛙の合唱を聞きながら混濁していく意識の赴くままに、眠りに誘われ目を閉じる。
騒がしい真夏の蛙の合唱は、やむことなく昼夜響き渡っていた。
だがもし、この蛙の合唱が翻訳できたのなら、謎は全て解明されたかもしれない。
『蛇を投げ捨てて 命を救ってくれた恩人に今日も贈り物をするよ 山の幸のご馳走さ♪ 僕らの美しい合唱を 休むことなく続けるのさ♪ それが最高の感謝の気持ち♪♪』
※ ※ ※ ※
カエルたちにとっては誠心誠意。心をこめたプレゼントだったはず。
ここは大目に見てあげましょう。
さて、音符を違ういいかたにすると……?