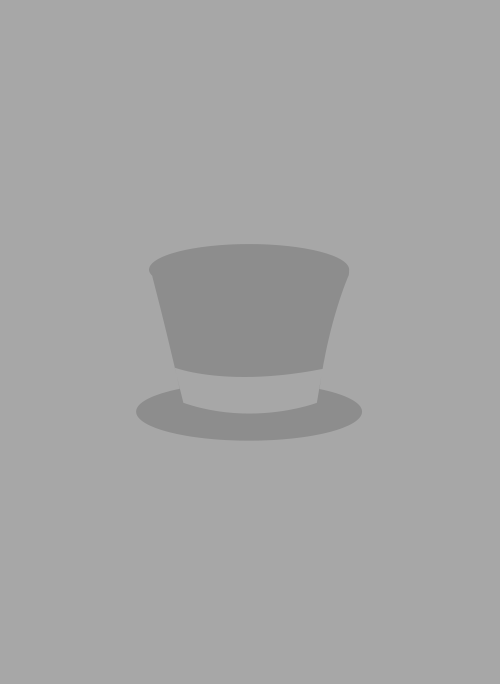心地よく鼻をくすぐる焙煎されたコーヒーの香りが、喫茶店の中に充満していた。店の扉に取りつけられた入店客を知らせる鈴が響くたびに、十一朗と裕貴は首を伸ばす。
入ってきたのは、真紅のショルダーバックを手にしたOLだった。また違ったと肩を落として壁掛け時計を見る。時刻は四時半――そろそろきてもいい頃だ。
「おかわりはどういたしますか?」
近づいた店員が、十一朗のカップが空になっているのを見て訊いてきた。これで四杯目になる。ケーキつきでコーヒーのおかわり自由のセットだが、十一朗は断った。
丁寧に焙煎されたコーヒーだから味はいいが、十一朗には物凄く濃く感じる。インスタントでも砂糖とミルクを大量に入れて飲む。これ以上飲んだら胃が悲鳴を上げてしまうと十一朗は思った。
「あっ、きた。こっち、こっち」
店員との会話で鈴の音に気づかなかった。裕貴が友達の登場に手を振って応える。
「ごめん、部活動なかなか抜けられなくって……何か頼んでいい?」
向かい側に座った裕貴の友達と妹に、十一朗は見覚えがあった。中学の時に同じクラスだった溝口千恵だ。誕生日に招待されたことがある。妹もその時に会っていた。
「友達って溝口のことだったのか……確か、私立高校に通ってんだっけ?」
十一朗は、空になったコーヒーの代わりに水を飲んだ。
「うん。女子高だよ。このケーキセット二つ」
メニューを聞きにきた店員に、溝口は注文を言うと、置かれたおしぼりで手を拭いた。妹も視線を下に落としながら、姉に続くように手を拭く。
「確か、冴恵(さえ)ちゃんだっけ? 俺のこと覚えてる? オセロゲーム一緒にしたよな」
緊張したままの妹に、十一朗は話しかける。真実を話してもらわなければ意味がない。それには親近感を持ってもらうことが大切だ。
「うん覚えてる。三勝一敗」
置かれた水を飲んでから、冴恵は物怖じせずに答えた。どうやら人見知りはしない性格のようだ。十一朗は安心した。
「年下に負けたの? だらしないなぁ……」
間を置かずに裕貴が言って突いてくる。それを見て千恵が笑った。
「二人とも変わらないなぁ……何か羨ましくなっちゃう。付き合ってんでしょ?」
千恵の質問に、十一朗は口に含もうとした水を吐き出しかけた。
「裕貴とはただの幼馴染み。付き合ってないって何度も――」
言いかけて言葉をとめた。昨日、久保に言ったのと同じセリフだ。
裕貴も思うところがあったのだろう。コーヒーを一口飲むと、冴恵を見た。
「あのね、冴恵ちゃん。私たち、自殺屋事件のことで知ってることを全部教えてほしいの」
冴恵は横の姉をちらりと見ると、水を飲んだ。メールに書かれた内容は姉の千恵から教わっているはずだろう。
『私たちの友達が自殺屋に殺されたの! お願い、妹さんが自殺した中学生のことを知っていたら詳しく教えて!』
裕貴はそう訴えのようなメールを送った。それを受けた千恵も悟ったのだろう。
『わかった。妹に聞いてみる!』返信は驚くほど早かった。
そして直後に、二つ目のメールが送られてきた。
『自殺した子、同級生だって。詳しく知ってるみたいだから、学校が終わったら会おう』
事の一部始終を聞いて、快く協力してくれると約束してくれた冴恵の返事は嬉しかった。
中学生の少女が忘れかけていた事件を思い出して語るのは、相当の辛苦を伴うはずだ。
店員が持ってきた紅茶に砂糖を入れながら、冴恵は口を開いた。
「自殺した子ってみんな言うけど、あれは自殺なんかじゃないよ。あの子が自殺するなんて考えられないもん。絶対に殺されたんだよ……」
冴恵は口火を切るように言うと、紅茶にミルクを入れた。ミルクは渦を巻いて溶け込んでいく。
「書きこみに、いじめが理由で死ぬってあったらしいけど、いじめをしていたのは、あいつ等のほうだから。相当、たくさんの人に恨まれていたらしいよ。私も階段で押されたことがあるし、と言っても、最初に自殺した子はつるんでいた感じかな……一番悪かったのは、二番目に責任を取って死にますって書いて自殺した子」
自殺ではないとしたら、第一の公開自殺から自殺屋は存在し、罪を犯したということになる。そうなると、久保の事件と共通する点も見えてくる。
入ってきたのは、真紅のショルダーバックを手にしたOLだった。また違ったと肩を落として壁掛け時計を見る。時刻は四時半――そろそろきてもいい頃だ。
「おかわりはどういたしますか?」
近づいた店員が、十一朗のカップが空になっているのを見て訊いてきた。これで四杯目になる。ケーキつきでコーヒーのおかわり自由のセットだが、十一朗は断った。
丁寧に焙煎されたコーヒーだから味はいいが、十一朗には物凄く濃く感じる。インスタントでも砂糖とミルクを大量に入れて飲む。これ以上飲んだら胃が悲鳴を上げてしまうと十一朗は思った。
「あっ、きた。こっち、こっち」
店員との会話で鈴の音に気づかなかった。裕貴が友達の登場に手を振って応える。
「ごめん、部活動なかなか抜けられなくって……何か頼んでいい?」
向かい側に座った裕貴の友達と妹に、十一朗は見覚えがあった。中学の時に同じクラスだった溝口千恵だ。誕生日に招待されたことがある。妹もその時に会っていた。
「友達って溝口のことだったのか……確か、私立高校に通ってんだっけ?」
十一朗は、空になったコーヒーの代わりに水を飲んだ。
「うん。女子高だよ。このケーキセット二つ」
メニューを聞きにきた店員に、溝口は注文を言うと、置かれたおしぼりで手を拭いた。妹も視線を下に落としながら、姉に続くように手を拭く。
「確か、冴恵(さえ)ちゃんだっけ? 俺のこと覚えてる? オセロゲーム一緒にしたよな」
緊張したままの妹に、十一朗は話しかける。真実を話してもらわなければ意味がない。それには親近感を持ってもらうことが大切だ。
「うん覚えてる。三勝一敗」
置かれた水を飲んでから、冴恵は物怖じせずに答えた。どうやら人見知りはしない性格のようだ。十一朗は安心した。
「年下に負けたの? だらしないなぁ……」
間を置かずに裕貴が言って突いてくる。それを見て千恵が笑った。
「二人とも変わらないなぁ……何か羨ましくなっちゃう。付き合ってんでしょ?」
千恵の質問に、十一朗は口に含もうとした水を吐き出しかけた。
「裕貴とはただの幼馴染み。付き合ってないって何度も――」
言いかけて言葉をとめた。昨日、久保に言ったのと同じセリフだ。
裕貴も思うところがあったのだろう。コーヒーを一口飲むと、冴恵を見た。
「あのね、冴恵ちゃん。私たち、自殺屋事件のことで知ってることを全部教えてほしいの」
冴恵は横の姉をちらりと見ると、水を飲んだ。メールに書かれた内容は姉の千恵から教わっているはずだろう。
『私たちの友達が自殺屋に殺されたの! お願い、妹さんが自殺した中学生のことを知っていたら詳しく教えて!』
裕貴はそう訴えのようなメールを送った。それを受けた千恵も悟ったのだろう。
『わかった。妹に聞いてみる!』返信は驚くほど早かった。
そして直後に、二つ目のメールが送られてきた。
『自殺した子、同級生だって。詳しく知ってるみたいだから、学校が終わったら会おう』
事の一部始終を聞いて、快く協力してくれると約束してくれた冴恵の返事は嬉しかった。
中学生の少女が忘れかけていた事件を思い出して語るのは、相当の辛苦を伴うはずだ。
店員が持ってきた紅茶に砂糖を入れながら、冴恵は口を開いた。
「自殺した子ってみんな言うけど、あれは自殺なんかじゃないよ。あの子が自殺するなんて考えられないもん。絶対に殺されたんだよ……」
冴恵は口火を切るように言うと、紅茶にミルクを入れた。ミルクは渦を巻いて溶け込んでいく。
「書きこみに、いじめが理由で死ぬってあったらしいけど、いじめをしていたのは、あいつ等のほうだから。相当、たくさんの人に恨まれていたらしいよ。私も階段で押されたことがあるし、と言っても、最初に自殺した子はつるんでいた感じかな……一番悪かったのは、二番目に責任を取って死にますって書いて自殺した子」
自殺ではないとしたら、第一の公開自殺から自殺屋は存在し、罪を犯したということになる。そうなると、久保の事件と共通する点も見えてくる。