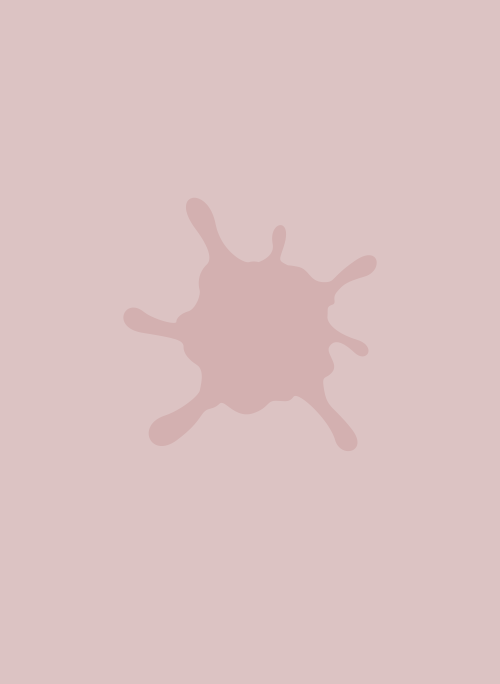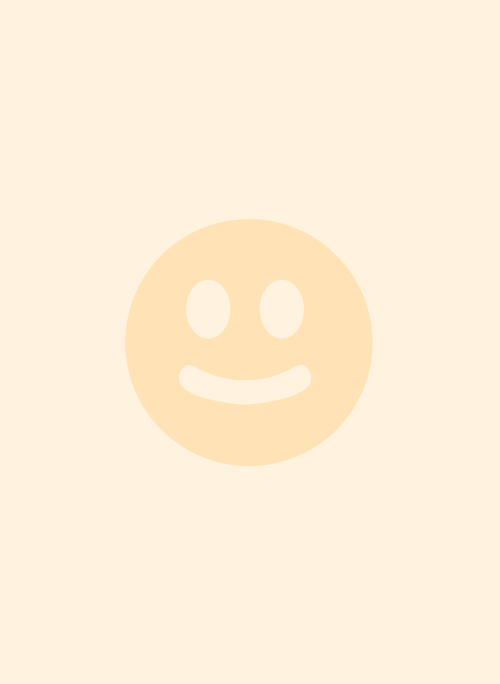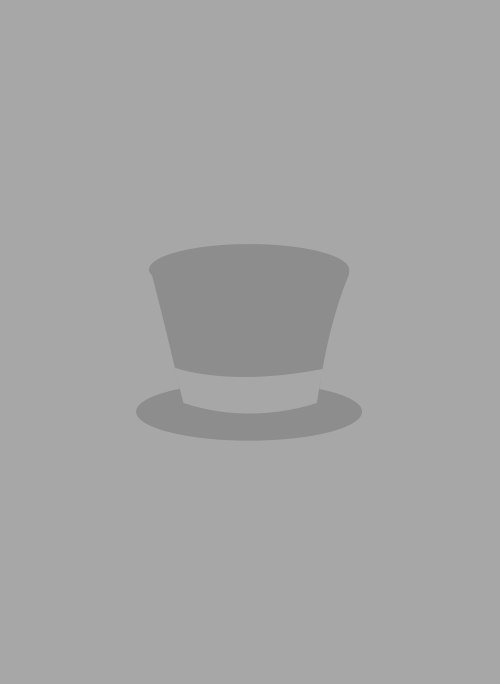強気で発言する十一朗を裕貴が指で突いてくる。さすがに刑事相手に喧嘩はよせということなのだろう。
「自殺屋とかネットで妙な噂があるから、一応、俺たちも鑑識も動かざる負えないんだよ――って、何でお前に、そんなことまで答えなきゃいけないんだ?」
貫野という刑事は十一朗を嫌な目で見た。探りを入れるような目だ。
「自殺って決めつけるなって言ったってことは、他殺だと言える証拠はあるのか?」
貫野に言われて十一朗は、背後にいる裕貴に合図を送った。
すかさず裕貴が口を開く。
「みんなにもきてほしい。大切な話があるからって、京子は言ったんです」
「京子?」
裕貴の説明を聞いてから、貫野は目を細くした。
「自殺者の名前です。久保京子、高校二年生」
貫野の背後にいた若い刑事が、メモした手帳を見ながら答える。
十一朗は後に続いた。
「自殺を決めた人間が、みんなにもきてほしい。大切な話があるなんて言うか? 首吊り自殺は完遂しなきゃ、重い後遺症が残る。少なくとも十五分は一人きりの時間が必要だ」
首吊りだと、踏み台から足をはずした瞬間に、椎骨動脈が絞められて血液が回らなくなる。その時、一番ダメージを受けるのは脳だ。血液がまわらずに酸欠状態になった脳細胞は破壊され、二度と修復しない。死に至らず助かった場合、必ず記憶障害などの後遺症が残る。
ミス研部員の久保なら、絶対に理解している知識だ。本気で自殺するつもりなら、誰かを呼ぶなどという、そんな考えは起こさないだろう。
十一朗の話に若い刑事が「確かに……」と相槌を打った。
それが気に入らなかったのか、貫野は「馬鹿野郎、高校生の意見に納得するな」と若い刑事を叩く。
「公開自殺なんて真似をする人間なら、常人に理解できない行動だってするだろう。第一、他殺なら……」
「吉川線がない。それに久保の爪には、犯人に抵抗した跡がなかった」
貫野より早く十一朗が答えたために、若い刑事が驚いて目を丸くした。
吉川線とは首絞めをされた被害者が抵抗し、縄などを取ろうとして首につける引っ掻き傷をいう。
そして、爪も大きな証拠となる。殺されそうになった側は必死だから、相手の腕に手をかける。その時に相手の皮膚を引っ掻いて皮膚片を爪の間に残すことも多い。それがあるかないかを見るのが、自他殺を判断する方法のひとつである。
貫野と若い刑事は、十一朗が何者なのかと推し量っているかのようで、黙ったままだ。
顎に手を添えて考えこんだ十一朗は、黙ったままの二人を見た。
「単独犯ではないとしたら? 腕をつかまれた状態で首を絞められたら、抵抗は無理だ」
貫野は腕を振り上げると、「あーっ」と鑑識の者たちが振り返るほどの大声を上げた。
「一般人が、妙な推理で捜査を掻きまわさないでくれ。公開自殺をやる人間にまともな奴はいない。抵抗した跡もない。遺書だって公開されている。自殺だよ。これは」
若い刑事が「自殺ですかねぇ」と呟く。振り返った貫野が「自殺だよ」と、また若い刑事を叩いた。
傍から見れば漫才のような二人から目をそらすと、十一朗は室内を見る。
「鑑識さん。どこか濡れている場所はなかった?」
そして、現場作業を続ける鑑識班に向かって質問した。
「自殺屋とかネットで妙な噂があるから、一応、俺たちも鑑識も動かざる負えないんだよ――って、何でお前に、そんなことまで答えなきゃいけないんだ?」
貫野という刑事は十一朗を嫌な目で見た。探りを入れるような目だ。
「自殺って決めつけるなって言ったってことは、他殺だと言える証拠はあるのか?」
貫野に言われて十一朗は、背後にいる裕貴に合図を送った。
すかさず裕貴が口を開く。
「みんなにもきてほしい。大切な話があるからって、京子は言ったんです」
「京子?」
裕貴の説明を聞いてから、貫野は目を細くした。
「自殺者の名前です。久保京子、高校二年生」
貫野の背後にいた若い刑事が、メモした手帳を見ながら答える。
十一朗は後に続いた。
「自殺を決めた人間が、みんなにもきてほしい。大切な話があるなんて言うか? 首吊り自殺は完遂しなきゃ、重い後遺症が残る。少なくとも十五分は一人きりの時間が必要だ」
首吊りだと、踏み台から足をはずした瞬間に、椎骨動脈が絞められて血液が回らなくなる。その時、一番ダメージを受けるのは脳だ。血液がまわらずに酸欠状態になった脳細胞は破壊され、二度と修復しない。死に至らず助かった場合、必ず記憶障害などの後遺症が残る。
ミス研部員の久保なら、絶対に理解している知識だ。本気で自殺するつもりなら、誰かを呼ぶなどという、そんな考えは起こさないだろう。
十一朗の話に若い刑事が「確かに……」と相槌を打った。
それが気に入らなかったのか、貫野は「馬鹿野郎、高校生の意見に納得するな」と若い刑事を叩く。
「公開自殺なんて真似をする人間なら、常人に理解できない行動だってするだろう。第一、他殺なら……」
「吉川線がない。それに久保の爪には、犯人に抵抗した跡がなかった」
貫野より早く十一朗が答えたために、若い刑事が驚いて目を丸くした。
吉川線とは首絞めをされた被害者が抵抗し、縄などを取ろうとして首につける引っ掻き傷をいう。
そして、爪も大きな証拠となる。殺されそうになった側は必死だから、相手の腕に手をかける。その時に相手の皮膚を引っ掻いて皮膚片を爪の間に残すことも多い。それがあるかないかを見るのが、自他殺を判断する方法のひとつである。
貫野と若い刑事は、十一朗が何者なのかと推し量っているかのようで、黙ったままだ。
顎に手を添えて考えこんだ十一朗は、黙ったままの二人を見た。
「単独犯ではないとしたら? 腕をつかまれた状態で首を絞められたら、抵抗は無理だ」
貫野は腕を振り上げると、「あーっ」と鑑識の者たちが振り返るほどの大声を上げた。
「一般人が、妙な推理で捜査を掻きまわさないでくれ。公開自殺をやる人間にまともな奴はいない。抵抗した跡もない。遺書だって公開されている。自殺だよ。これは」
若い刑事が「自殺ですかねぇ」と呟く。振り返った貫野が「自殺だよ」と、また若い刑事を叩いた。
傍から見れば漫才のような二人から目をそらすと、十一朗は室内を見る。
「鑑識さん。どこか濡れている場所はなかった?」
そして、現場作業を続ける鑑識班に向かって質問した。