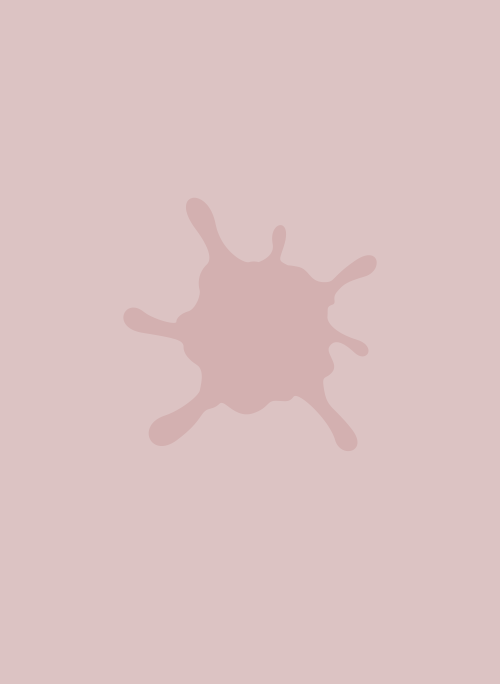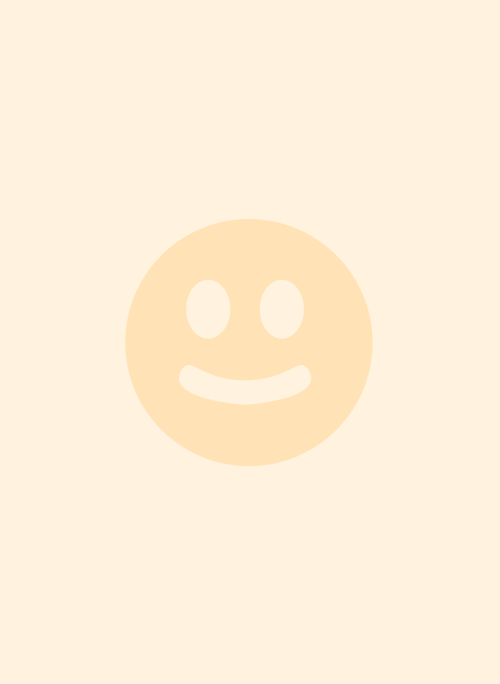一時間後――久保の家の前には重大事件を反映するように、何台もの警察車両が集結していた。騒ぎを聞いて駆けつけてきた、ヤジ馬の数も尋常ではない。
「死んだのって誰?」「何が起きたの?」
そんな声が微かに聞こえてくる。関係者にとってこれほどの苦痛はない。
十一朗と裕貴は久保の部屋を出た二階の窓から、眼下の様子を眺めていた。
その騒ぎをかき分けて、久保の両親が姿を見せた。日曜にも関わらず、生活費のため、娘の将来のために仕事をしていた両親は、たった一本の電話で娘の死を伝えられたはずだ。
久保の母親は人形のように冷え切った我が子を見て、口を押さえながら号泣し、座りこんだ。父親は妻を労わるように肩を寄せた。だが、その手は小刻みに震えていた。
久保の両親の反応を間近にして心が痛んだ。本来なら見ないほうが良かったのだろう。
しかし、第一発見者である十一朗と裕貴は、否でも応でも現場で事情を語らなければならない。それに刑事から久保の両親に君を引き留めておいてほしいと頼まれたと聞かされ、十一朗は会うと決めていた。
しばらくして久保の両親が部屋から出てきた。これから久保が自殺であるか他殺であるか、鑑識、警察、監察医が詳しく調べるためだ。
鑑識が撮るカメラのシャッター音を横で聞きながら、両親と目が合った十一朗と裕貴は頭を下げた。久保の両親も十一朗達以上に頭を深く下げ、父親は十一朗に語りかけてきた。
「話は刑事さんから聞いたよ。最善の処置をしてくれたみたいで……ありがとう」
久保の命は戻らない。しかし、久保の父親にそう言われたのは救いだった。
もう少し早ければ……十一朗はそう言いかけたが、口にできなかった。傷口を触るようなものだ。何を言ったとしても、過ぎたことは変わらない。虚しさだけが残るだけだ。
最後にまた頭をさげて、久保の両親は一階におりていった。娘が死んだ現場。そんな悲しい場所に居続けるのは、身を切り裂かれるような思いだろう。
十一朗たちも同じだった。現場を後にしようとした。その時だ。
「こりゃ、公開自殺に便乗した模倣自殺だな……」
部屋の奥から声が聞こえた。
信じられない決断に十一朗は足をとめ、声の主を確認しようと部屋を覗きこんだ。三十代半ばくらいの男、一警察署勤務の刑事だろうか。現場経験が浅いようにも見えた。
「あんた何歳? 観察眼がないから、まだ巡査長なんじゃないの?」
刑事の背中に向かって十一朗は声を上げた。
巡査長は階級ではない。士気を高めるのを目的に、長年働いた巡査部長になれない者に与えられる肩書である。それを知っている十一朗は彼を皮肉ったのだ。
すぐに刑事は反応した。こちらに向かって豪快な足音を立てながら近づいてくる。見開いた眼は怒りで充血していた。
「お前が第一発見者さんですか……詳しい状況を教えてくれないですかねぇ……」
慇懃無礼な口調で話しかけてきた刑事を、一瞥してから十一朗は息を吐いた。
「そこの若い刑事に全部話したよ。それより、あんたの名前を聞かせてよ。遺族の前で平気で自殺って決めつけるなんて、納得できるように説明してくれ」
十一朗に言われた刑事は、眉間に皺を寄せたまま警察手帳を開いて突きつけた。
「警視庁捜査一課の貫野(かんの)だ。そして俺は……巡査部長だ」
「警視庁捜査一課? 自殺って言っているのに、警視庁捜査一課が動いてるのか?」
十一朗は、貫野が一警察署の刑事と思いこんでいたので驚いた。
そういえば、久保の死は自殺と決めつけているのにも関わらず、鑑識、監察医が駆けつけてくること自体おかしい。
公開自殺の裏に自殺屋がいる。証拠がなくても、警察が考えていることは同じなのだろう。異例ともいえる彼らの行動が、それを決定づけていた。
「死んだのって誰?」「何が起きたの?」
そんな声が微かに聞こえてくる。関係者にとってこれほどの苦痛はない。
十一朗と裕貴は久保の部屋を出た二階の窓から、眼下の様子を眺めていた。
その騒ぎをかき分けて、久保の両親が姿を見せた。日曜にも関わらず、生活費のため、娘の将来のために仕事をしていた両親は、たった一本の電話で娘の死を伝えられたはずだ。
久保の母親は人形のように冷え切った我が子を見て、口を押さえながら号泣し、座りこんだ。父親は妻を労わるように肩を寄せた。だが、その手は小刻みに震えていた。
久保の両親の反応を間近にして心が痛んだ。本来なら見ないほうが良かったのだろう。
しかし、第一発見者である十一朗と裕貴は、否でも応でも現場で事情を語らなければならない。それに刑事から久保の両親に君を引き留めておいてほしいと頼まれたと聞かされ、十一朗は会うと決めていた。
しばらくして久保の両親が部屋から出てきた。これから久保が自殺であるか他殺であるか、鑑識、警察、監察医が詳しく調べるためだ。
鑑識が撮るカメラのシャッター音を横で聞きながら、両親と目が合った十一朗と裕貴は頭を下げた。久保の両親も十一朗達以上に頭を深く下げ、父親は十一朗に語りかけてきた。
「話は刑事さんから聞いたよ。最善の処置をしてくれたみたいで……ありがとう」
久保の命は戻らない。しかし、久保の父親にそう言われたのは救いだった。
もう少し早ければ……十一朗はそう言いかけたが、口にできなかった。傷口を触るようなものだ。何を言ったとしても、過ぎたことは変わらない。虚しさだけが残るだけだ。
最後にまた頭をさげて、久保の両親は一階におりていった。娘が死んだ現場。そんな悲しい場所に居続けるのは、身を切り裂かれるような思いだろう。
十一朗たちも同じだった。現場を後にしようとした。その時だ。
「こりゃ、公開自殺に便乗した模倣自殺だな……」
部屋の奥から声が聞こえた。
信じられない決断に十一朗は足をとめ、声の主を確認しようと部屋を覗きこんだ。三十代半ばくらいの男、一警察署勤務の刑事だろうか。現場経験が浅いようにも見えた。
「あんた何歳? 観察眼がないから、まだ巡査長なんじゃないの?」
刑事の背中に向かって十一朗は声を上げた。
巡査長は階級ではない。士気を高めるのを目的に、長年働いた巡査部長になれない者に与えられる肩書である。それを知っている十一朗は彼を皮肉ったのだ。
すぐに刑事は反応した。こちらに向かって豪快な足音を立てながら近づいてくる。見開いた眼は怒りで充血していた。
「お前が第一発見者さんですか……詳しい状況を教えてくれないですかねぇ……」
慇懃無礼な口調で話しかけてきた刑事を、一瞥してから十一朗は息を吐いた。
「そこの若い刑事に全部話したよ。それより、あんたの名前を聞かせてよ。遺族の前で平気で自殺って決めつけるなんて、納得できるように説明してくれ」
十一朗に言われた刑事は、眉間に皺を寄せたまま警察手帳を開いて突きつけた。
「警視庁捜査一課の貫野(かんの)だ。そして俺は……巡査部長だ」
「警視庁捜査一課? 自殺って言っているのに、警視庁捜査一課が動いてるのか?」
十一朗は、貫野が一警察署の刑事と思いこんでいたので驚いた。
そういえば、久保の死は自殺と決めつけているのにも関わらず、鑑識、監察医が駆けつけてくること自体おかしい。
公開自殺の裏に自殺屋がいる。証拠がなくても、警察が考えていることは同じなのだろう。異例ともいえる彼らの行動が、それを決定づけていた。