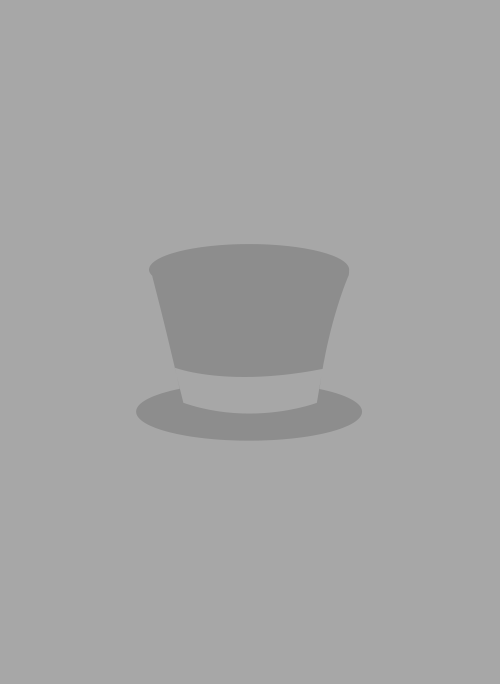翌日、休日にもかかわらず十一朗は、目覚まし時計で起床して、しっかり六時には食卓についていた。
父は刑事、母は記者。帰宅時間がまちまちな両親と十一朗が決めた約束事があった。
必ず全員揃って朝食を取ること!
それは、一家団欒の時間を大切にしたいと十一朗が決めたことだった。十一朗はすでに座って、新聞を広げている父の正面の席につく。
「あのさ、父さん。あの事件って解決に向かってるの?」
十一朗はコーヒーに砂糖を入れながら、正面で新聞を読んでいる父に訊いた。
「なんだ? 気になるのか?」
新聞の下にある週刊誌の広告を見ながら、父は「だろうなぁ」と小さく呟いた。
「自殺者の遺族のほとんどが、あの子が自殺するわけがないと言っている。だから、事件も視野に入れて捜査しているよ。今はそれしか答えられない」
厳格な父だが、十一朗が事件に興味を持って質問した時には必ず答えてくれる。
本来、刑事は家族にも捜査の進展を話さないものなのだが、十一朗も母も絶対に他言しないとわかっているからだ。
そして、記者である母も、無理に父から話を聞き出そうとはしない。仕事上の関係と壊してはいけない壁を知っているからこそ、二人は結ばれたのだから。
「うちの出版社では、自殺屋はいるのかって大騒ぎ。その人物って本当にいるの?」
自分と父、二人分の弁当を詰め終えた母が、席について質問した。
「捜査中」
父は記者の母の質問を一言で片付けると、ブラックコーヒーを一口飲んだ。これ以上訊いても父が答えることはないだろう。家族内の暗黙の了解がここにあった。
十一朗は、たっぷりのミルクで完成したカフェオレを一口飲む。
「話変わるけどさ。俺、出掛ける予定あるんだ。母さん、今日は何時に帰ってくる?」
久保の家から帰ってくる正確な時間はわからない。十一朗は母に合わせようと思った。
母の帰りがはやい時は夕食を一緒にしている。しかし最近では、自殺屋事件で忙しいのか、母も父も帰宅時間が遅い。
そんな時には十一朗は一人で食事をするのだ。コンビニ弁当で済ませるのがほとんどだから、先に訊いておいたほうが楽なのである。
「忙しいからはっきりした時間は……とっ君、携帯持ってよ。そうすれば連絡できるのに」
いつもと同じことを言われて、十一朗は息を吐いてしまった。
「たいして使わないのに持っていたら、契約料がもったいないだろ……」
本当はそれが理由ではない。前にもあったように十一朗は機械操作が苦手なのだ。
「契約料ならお母さんが払うから……もう、誰に似たんだか」
母は父の性格に似たと言いたいのだろう。思いがけず話題を振られた父は、誤魔化すかのように、わざとらしく音を立てて新聞を置くと、
「行ってくる。多分遅くなるから、夕食はいらないよ」
いつもの通勤時刻より二十分もはやいのに、カバンを持って席を立った。
父は刑事、母は記者。帰宅時間がまちまちな両親と十一朗が決めた約束事があった。
必ず全員揃って朝食を取ること!
それは、一家団欒の時間を大切にしたいと十一朗が決めたことだった。十一朗はすでに座って、新聞を広げている父の正面の席につく。
「あのさ、父さん。あの事件って解決に向かってるの?」
十一朗はコーヒーに砂糖を入れながら、正面で新聞を読んでいる父に訊いた。
「なんだ? 気になるのか?」
新聞の下にある週刊誌の広告を見ながら、父は「だろうなぁ」と小さく呟いた。
「自殺者の遺族のほとんどが、あの子が自殺するわけがないと言っている。だから、事件も視野に入れて捜査しているよ。今はそれしか答えられない」
厳格な父だが、十一朗が事件に興味を持って質問した時には必ず答えてくれる。
本来、刑事は家族にも捜査の進展を話さないものなのだが、十一朗も母も絶対に他言しないとわかっているからだ。
そして、記者である母も、無理に父から話を聞き出そうとはしない。仕事上の関係と壊してはいけない壁を知っているからこそ、二人は結ばれたのだから。
「うちの出版社では、自殺屋はいるのかって大騒ぎ。その人物って本当にいるの?」
自分と父、二人分の弁当を詰め終えた母が、席について質問した。
「捜査中」
父は記者の母の質問を一言で片付けると、ブラックコーヒーを一口飲んだ。これ以上訊いても父が答えることはないだろう。家族内の暗黙の了解がここにあった。
十一朗は、たっぷりのミルクで完成したカフェオレを一口飲む。
「話変わるけどさ。俺、出掛ける予定あるんだ。母さん、今日は何時に帰ってくる?」
久保の家から帰ってくる正確な時間はわからない。十一朗は母に合わせようと思った。
母の帰りがはやい時は夕食を一緒にしている。しかし最近では、自殺屋事件で忙しいのか、母も父も帰宅時間が遅い。
そんな時には十一朗は一人で食事をするのだ。コンビニ弁当で済ませるのがほとんどだから、先に訊いておいたほうが楽なのである。
「忙しいからはっきりした時間は……とっ君、携帯持ってよ。そうすれば連絡できるのに」
いつもと同じことを言われて、十一朗は息を吐いてしまった。
「たいして使わないのに持っていたら、契約料がもったいないだろ……」
本当はそれが理由ではない。前にもあったように十一朗は機械操作が苦手なのだ。
「契約料ならお母さんが払うから……もう、誰に似たんだか」
母は父の性格に似たと言いたいのだろう。思いがけず話題を振られた父は、誤魔化すかのように、わざとらしく音を立てて新聞を置くと、
「行ってくる。多分遅くなるから、夕食はいらないよ」
いつもの通勤時刻より二十分もはやいのに、カバンを持って席を立った。