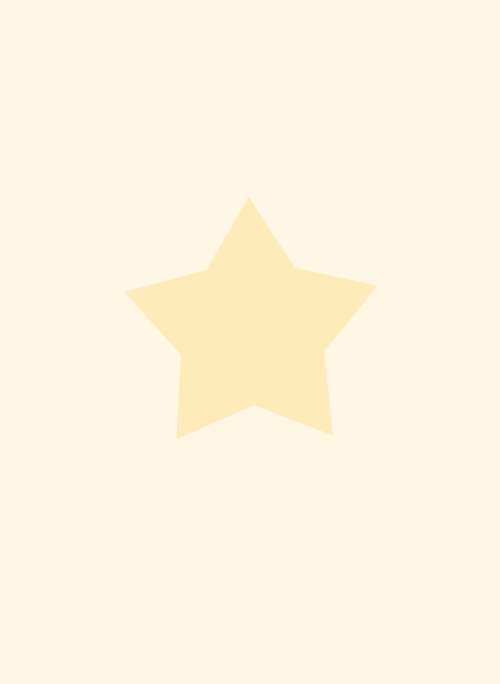だから、恐ろし過ぎて、私達はただ黙って舞華の思うままに動いている。
でも、さすがに、既に痣だらけになった相手の生まれつきあどけない体に、ボールをぶつけるのには、少し抵抗があった。
「春?」
私が動いてないのを見つけた舞華は、不思議そうな声で、顔はニヤつきながら私を見つめた。
…はぁ。
…ごめんなさい……っ!
私に…私に強さがあれば……
私は、目を固く瞑り、ボールを思いっきり女の子に向かって投げ付けた。
呻き声をあげる女の子に、思わず強い嫌悪感が脳を駆け巡る。
春の、意気地無し。
そんなに嫌悪感があるなら、舞華に言ってやれば良いのに。
でも、やっぱり、言えない。