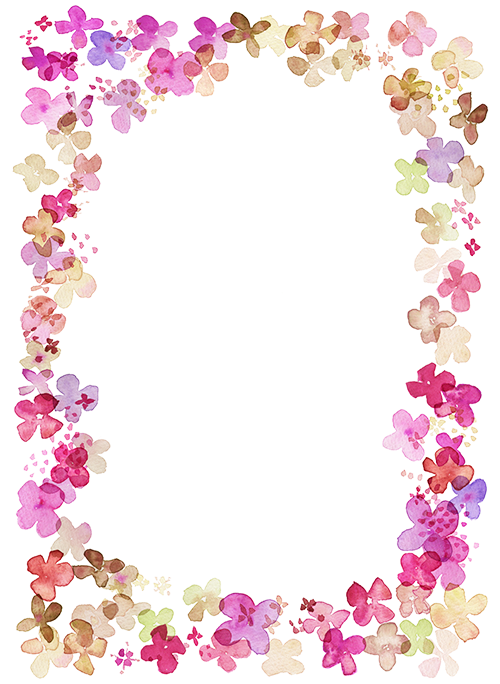…そうだ、そうだよ。
なんで今まで気づかなかったんだ、俺…!
鬼才の作曲家サマが、聞いてあきれるぜ…!
「おい、
『歌』でなら言えるのか」
「え?」
「セリフを歌詞にして歌えるか、って訊いてんだよ」
俺はホールの隅に置いてあったキーボードへ走って、思い浮かぶまま、メロディを弾き始めた。
役になりきることができないなら。
いっそ役なんか、この瞬間だけ忘れちまえ。
俺がおまえのためだけに、とびきりの曲を作ってやる。
奏でるのは、ミディアムテンポの落ち着いたメロディ。
つらい日々と、運命の出会い、初めての恋。
そして愛しい人と新たな道を歩んでいく、みずみずしいよろこび。
そんな、シンデレラのいろんな気持ちと思い出をたくさんに詰めた、
あまくメロウな、
ラブソング。
「わぁ…綺麗なメロディ…!
即興で作れるなんて、さすがあや」
「感心してないで、セリフ乗せろ」
「う、うん…!」
目を閉じて、耳を澄まして、小鳥の歌声を重ねる優羽。
あてずっぽうに乗せるのではなく、曲の盛り上がりに合わせて歌詞を選ぶ上手さはさすがだった。
単音のメロディが歌声を乗せることによって色味を増していくと共に、指先がどんどんメロディを生み出していく。
そうすると優羽もノって、もっといい声で、高く低く、情感豊かに歌い、おまけに、この俺に指図までしてくる。
けどそれは絶妙なスパイスをあたえ、俺の想像を超えた姿に曲がどんどん進化していく。
やっぱ、
こいつは本物だ。
俺はすっかり楽しくなって、とうとうと湧きあがるメロディを夢中で奏でていく。
困惑しながらも、対等に歌声をのばしていく優羽も、すごくいい笑顔を浮かべていた。
いつしか劇の練習なのも忘れて、俺たちは曲作りに没頭していた。