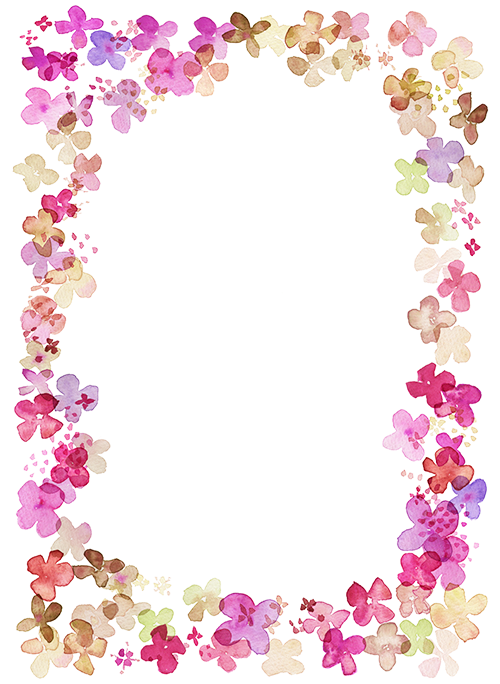ただ強引に手を引いて、痛いという訴えにも耳を貸さず、優羽を寮に連れ帰る。
寮に着いた早々、多目的用に設けられたホールに優羽を押し込んだ。
「彪斗くん…」
「おら、グズ、
もたもたしてねぇで今日の練習始めるぞ」
「ね…
なにをそんなに怒ってるの?」
「怒ってねぇよ!」
びくり、と震えて、優羽は口をつぐんだ。
くそ…
怖がらせるつもりなんてないのに…!
優羽に問い質したいことが山とあった。
なにがあった。
連れて行ったのは誰だ。
頬はどうした。
誰に叩かれた。
いつ雪矢と会った。
なに話してた。
なにされてた―――。
山ほどあり過ぎて、頭がメチャクチャになっていた。
こんなんじゃ、ふたりきりで落ち着いて練習なんてできやしねぇ。
今のこの俺の心じゃ、優羽になにしでかすかわからなかった。
俺たち生徒会は今、約一週間後に開催される学校祭で特別公開することになった演劇の練習にはげんでいた。
この学校の生徒会とは、無理矢理役職を押し付けられた連中で構成された、ほとんどお飾りのような存在だ。
当然ながら、各自に職務へのヤル気なんてあるはずもなく、
クサクサした気持ちで集まっているため、メンバー同士の仲もいいと言えるものではなかった。
『わたしたちはちがうと思うんだよねー!』
けど、異論を唱えてきたやつが一人。
『わたしたちってー、歴代の生徒会の中でもかなりまとまってていいカンジのグループなんじゃないかなって思うわけ』
寧音のクソチビだ。
寮に着いた早々、多目的用に設けられたホールに優羽を押し込んだ。
「彪斗くん…」
「おら、グズ、
もたもたしてねぇで今日の練習始めるぞ」
「ね…
なにをそんなに怒ってるの?」
「怒ってねぇよ!」
びくり、と震えて、優羽は口をつぐんだ。
くそ…
怖がらせるつもりなんてないのに…!
優羽に問い質したいことが山とあった。
なにがあった。
連れて行ったのは誰だ。
頬はどうした。
誰に叩かれた。
いつ雪矢と会った。
なに話してた。
なにされてた―――。
山ほどあり過ぎて、頭がメチャクチャになっていた。
こんなんじゃ、ふたりきりで落ち着いて練習なんてできやしねぇ。
今のこの俺の心じゃ、優羽になにしでかすかわからなかった。
俺たち生徒会は今、約一週間後に開催される学校祭で特別公開することになった演劇の練習にはげんでいた。
この学校の生徒会とは、無理矢理役職を押し付けられた連中で構成された、ほとんどお飾りのような存在だ。
当然ながら、各自に職務へのヤル気なんてあるはずもなく、
クサクサした気持ちで集まっているため、メンバー同士の仲もいいと言えるものではなかった。
『わたしたちはちがうと思うんだよねー!』
けど、異論を唱えてきたやつが一人。
『わたしたちってー、歴代の生徒会の中でもかなりまとまってていいカンジのグループなんじゃないかなって思うわけ』
寧音のクソチビだ。