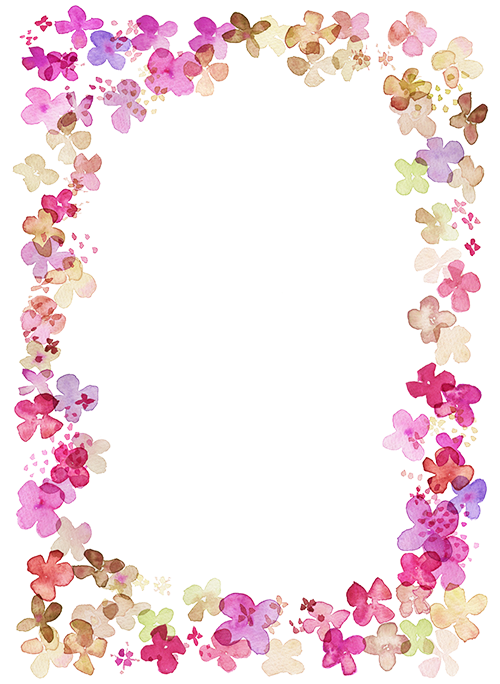少し行った先にベンチがあったので、わたしたちはそこに座って溶けかかったソフトクリームに口を付けた。
甘くて冷たい味。
でも、美味しいはずなのに、わたしの心は無反応だった。
彪斗くんはパクパクとおっきな口であっという間に食べてしまうと、ノロノロと食べているわたしを見つめていた。
「優羽。
手についてるぞ」
「え…っ」
「ほら、垂れるって…!」
「あっ…」
ちゅ…
彪斗くんの唇が、わたしの小指をそっと、吸った。
「あっ、あああ、ごめん、なさいっ…!」
パニックになりながらティッシュをコーンに巻いて、わたしは食べるのに集中する。
彪斗くんの唇の感触が…
まだ小指に残ってるよ…!
ドキドキしながら、気まずくてひたすら食べるのに集中すると、あっという間に食べ終えてしまった。