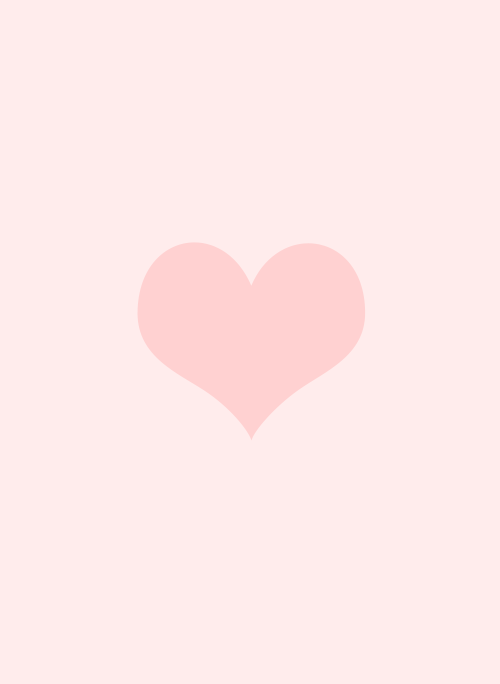「おいおい困ってるだろ、潤。放してやれよ。」
そういって近づいてきた男の子は、まるで中学生のような顔立ちだった。
「知り合いなの?」
「うん、幼馴染なの。ってか私のペットみたいな?」
その言葉を聞いて男の子は耳まで真っ赤に染めた。
「今度そんなこと言ったら、容赦なくはたくぞ!…俺、ペットじゃなくて、恭(みつ)ね。今井恭だから。」
那に向き直って、自己紹介をした恭は、本当に潤のペットなんじゃないかって思っちゃうほど可愛らしい顔をしていた。
「小動物みたいだね、恭くん。」
那が言うと、潤は誇らしげに言うんだ。
「うん、でしょう?那も小動物みたいだけどねー。あ、でも恭は私のだから!」
また恭は顔を真っ赤に染めた。
顔を覆った左手の薬指には、綺麗なシルバーリングがはめられていた。