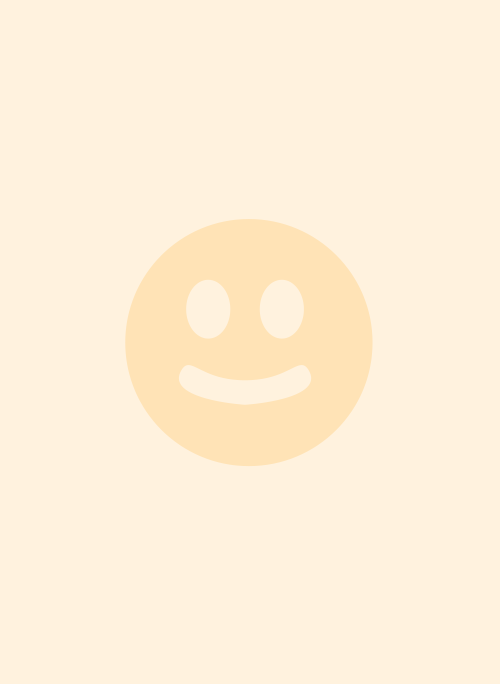「うん、例えばだね。『右と左の二つに分かれていた道があります。さて、A君はどちらに進んだでしょう?』 という設問があったとする。この答えを導き出すとき、重点にあるのは設問そのものじゃない。ソレが、クイズであるかナゾナゾであるか、ということに尽きる事なのだよ」
と、ナゾナゾ博士は語り始めた。
「その設問がクイズであったのなら、答えは簡単だ。『右』か『左』で答えればいいわけだからね。それは、『どちらに』という言葉が答えを限定していることになるわけだが、これがナゾナゾだとそうはいかない。『引き返す』というのもあるし『真ん中に道を新しく作る』ということもある。『A君』が何人でその道に来たのかもわからないから、『二手に分かれる』なんていうのも…」
そこで急に押し黙ったナゾナゾ博士は、手元にあるコーヒーを少し口に含んで、一頻り物思いにふけった後
「まぁ、あるという事だ」
と、半ば強引にまとめた。
「なるほど」
と、僕は必要以上に難しい顔を作り大きく頷く。
「つまり、ナゾナゾには文法や文体そのものを壊すことのできる自由度を兼ね備えているというわけですね」
「うむ。そうとも言えるが、違うとも言える。程度の低いナゾナゾになると、文字そのものが答えになっている場合もあるからね。まぁ、そんなもの私はナゾナゾと認めていないが。それに君、自由というものを推し量るのならば、そもそも壊すという概念自体が存在しない世界なのだよ。ナゾナゾにも制限がある。いや、その制限こそが答えを導き出せる唯一の手がかりと言ってもいい」
「では、先ほどの博士が出した例えは、クイズなんですね」
僕がそう言うと、ナゾナゾ博士は興味深そうな目で僕を見た。
「ほう。何故そう思うんだい」
「制限が少ないからです」
自信を持って答えた僕を前にナゾナゾ博士は、大笑いをした。
ナゾナゾ博士の笑い声が狭い部屋中に響き渡り、コーヒーカップがカタカタと音立てて揺れた。その振動を抑えるようにカップを持ち上げて、一啜りするとナゾナゾ博士は真顔に戻った。
「なかなかいい答えだが、残念ながらそうとも言い切れないのがこの業界の難しいところなのだよ。だが、君はクイズ向きだな」
「どうしてですか」
納得のいかない僕にナゾナゾ博士は、ため息混じりにこう答えた。
「君に制限が少ないからだ」
と、ナゾナゾ博士は語り始めた。
「その設問がクイズであったのなら、答えは簡単だ。『右』か『左』で答えればいいわけだからね。それは、『どちらに』という言葉が答えを限定していることになるわけだが、これがナゾナゾだとそうはいかない。『引き返す』というのもあるし『真ん中に道を新しく作る』ということもある。『A君』が何人でその道に来たのかもわからないから、『二手に分かれる』なんていうのも…」
そこで急に押し黙ったナゾナゾ博士は、手元にあるコーヒーを少し口に含んで、一頻り物思いにふけった後
「まぁ、あるという事だ」
と、半ば強引にまとめた。
「なるほど」
と、僕は必要以上に難しい顔を作り大きく頷く。
「つまり、ナゾナゾには文法や文体そのものを壊すことのできる自由度を兼ね備えているというわけですね」
「うむ。そうとも言えるが、違うとも言える。程度の低いナゾナゾになると、文字そのものが答えになっている場合もあるからね。まぁ、そんなもの私はナゾナゾと認めていないが。それに君、自由というものを推し量るのならば、そもそも壊すという概念自体が存在しない世界なのだよ。ナゾナゾにも制限がある。いや、その制限こそが答えを導き出せる唯一の手がかりと言ってもいい」
「では、先ほどの博士が出した例えは、クイズなんですね」
僕がそう言うと、ナゾナゾ博士は興味深そうな目で僕を見た。
「ほう。何故そう思うんだい」
「制限が少ないからです」
自信を持って答えた僕を前にナゾナゾ博士は、大笑いをした。
ナゾナゾ博士の笑い声が狭い部屋中に響き渡り、コーヒーカップがカタカタと音立てて揺れた。その振動を抑えるようにカップを持ち上げて、一啜りするとナゾナゾ博士は真顔に戻った。
「なかなかいい答えだが、残念ながらそうとも言い切れないのがこの業界の難しいところなのだよ。だが、君はクイズ向きだな」
「どうしてですか」
納得のいかない僕にナゾナゾ博士は、ため息混じりにこう答えた。
「君に制限が少ないからだ」