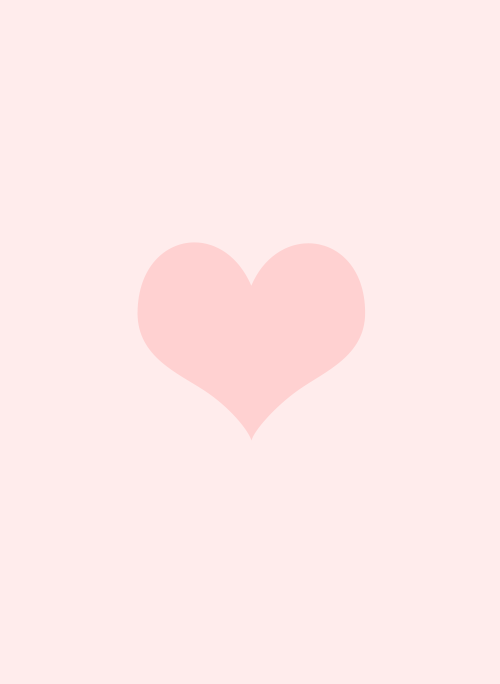「おはよう」
気のせいだ。
昨日気づいたことは、きっとなにかの間違えだ。
だって冬は、女の子だから。
そして私も。
『普通じゃない』
昨晩から、頭の中に同じ文字がグルグルと回り続けている。
前にも女の子にときめいたことは何度かあった。
だけど、冬は違うのだ。
具体的に何が違うとは言えないけれど、彼女が私にとって他とは違う特別な人だとゆうことはわかっている。
昨日出会ったばかりなのに、私の中心には彼女がいる。
私は、きっと少しオカシイのだ。
「春?」
突然顔を覗きこまれて、私は驚きのあまり席から立ち
「ふっ、ゅ」
状況が認識できないまま、なんの躊躇いもなく顔を近づけてくる彼女を目を丸くして見た。
「声かけたんだけど、気づかなかった?」
一瞬足りとも目を逸らさない。
「こ、声?あー…考え事してて……」
私はこんなに近くで冬と目が合うことに耐えられず、ほとんど彼女と自分のスカートや床に視線を向ける。
背凭れに両手をついて、近づいてくる冬と距離を取ろうと必至になった。
「へぇ…」
冬はゆっくりと唇を動かして、私を舐めるように見た。
そんな瞬間ばかりハッキリと見つめてしまうから、本当に嫌になる。
彼女の視界が自分でいっぱいになっている。
喉を締め付けられるような感覚と、激しい乾き。
とうとうバランスを崩して、私の身体は大きく揺れて椅子へ戻った。
冬の手が頬に触れてくる。
私はくすぐったさに目を瞑った。
「おはよう。って、言ったの」
「ぁ、うん…おはよ」
近くで冬の唇を見たせいだ。
彼女の唇にばかり目が行ってしまう気がして、疚しい気持ちがあるようで辛くなった。
冬はとても意地悪だ。
あの目は絶対に確信犯の目。
あぁ、本当に、相当たちが悪い。
昨日のこともあって、私は少しおかしいのだ。
それを煽るようなことをされると、心臓までもがおかしくなりそうなのだ。
余裕が欲しい。
整理する時間が欲しい。