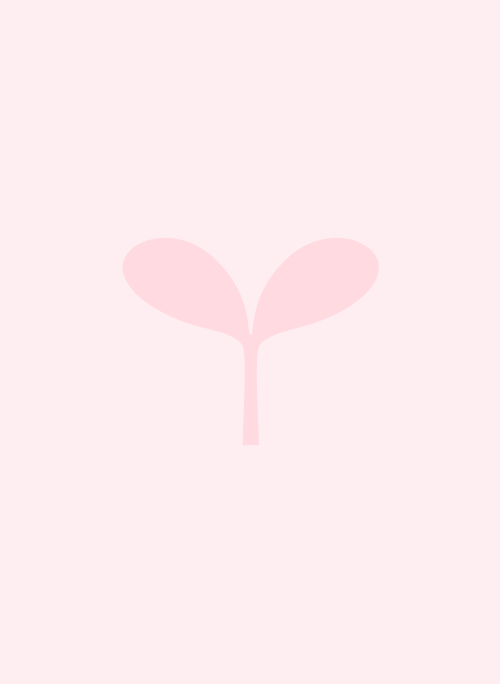「結局誰も見つけてこなかった」
「まだ言ってんのか、一臣」
2泊3日の合宿は終わった。帰りの電車の中、きもだめしの時のことを久喜会長はまだ嘆いている。事前に隠していたあるものを誰も持ってこなかったからだった。
次の日、すねたままの久喜会長のためにしぶしぶ回収しにいった千夜先輩の手には、試写会のチケットが握られていた。
「"星降る街で"はあの人気小説がついに映画化されたもので、何枚もの手書きハガキを出して当てたものだというのに、それを……」
「わかったって。悪かったよ、一臣」
「それに、天候の変化で流星群を見ることができなかった……」
「俺たちは見たよ」
私たちの後をつけて楽しもうと、きもだめしに参加しなかった久喜会長。ちょっと休んでから行こうと思ったらラウンジのソファーの柔らかさと睡魔に負けてしまったらしい。
森をさまよっていた私たちは、流星群を偶然見れた。
次の日は晴れの予報とは裏腹に雨が降ってしまい、雲だらけの空だった。
「アンちゃん、大丈夫?」
「……えっ、あ、ごめん。どうしたの、リンゴ」
「ううん。ボーッとなってたから大丈夫かなって。疲れた顔してる」
「まあ、ちょっと疲れたかな……」
隣に座るリンゴが心配そうに私をのぞきこんでいる。
きもだめしから、真島くんとは一言も話していない。事情を知らないリンゴにも感じるくらい、違和感があったと思う。
偶然、迷子になっていたリンゴと会わなければ、あの森から動くこともできなかっただろう。
それほどに、一生忘れることのできない合宿になってしまった。
「まだ言ってんのか、一臣」
2泊3日の合宿は終わった。帰りの電車の中、きもだめしの時のことを久喜会長はまだ嘆いている。事前に隠していたあるものを誰も持ってこなかったからだった。
次の日、すねたままの久喜会長のためにしぶしぶ回収しにいった千夜先輩の手には、試写会のチケットが握られていた。
「"星降る街で"はあの人気小説がついに映画化されたもので、何枚もの手書きハガキを出して当てたものだというのに、それを……」
「わかったって。悪かったよ、一臣」
「それに、天候の変化で流星群を見ることができなかった……」
「俺たちは見たよ」
私たちの後をつけて楽しもうと、きもだめしに参加しなかった久喜会長。ちょっと休んでから行こうと思ったらラウンジのソファーの柔らかさと睡魔に負けてしまったらしい。
森をさまよっていた私たちは、流星群を偶然見れた。
次の日は晴れの予報とは裏腹に雨が降ってしまい、雲だらけの空だった。
「アンちゃん、大丈夫?」
「……えっ、あ、ごめん。どうしたの、リンゴ」
「ううん。ボーッとなってたから大丈夫かなって。疲れた顔してる」
「まあ、ちょっと疲れたかな……」
隣に座るリンゴが心配そうに私をのぞきこんでいる。
きもだめしから、真島くんとは一言も話していない。事情を知らないリンゴにも感じるくらい、違和感があったと思う。
偶然、迷子になっていたリンゴと会わなければ、あの森から動くこともできなかっただろう。
それほどに、一生忘れることのできない合宿になってしまった。