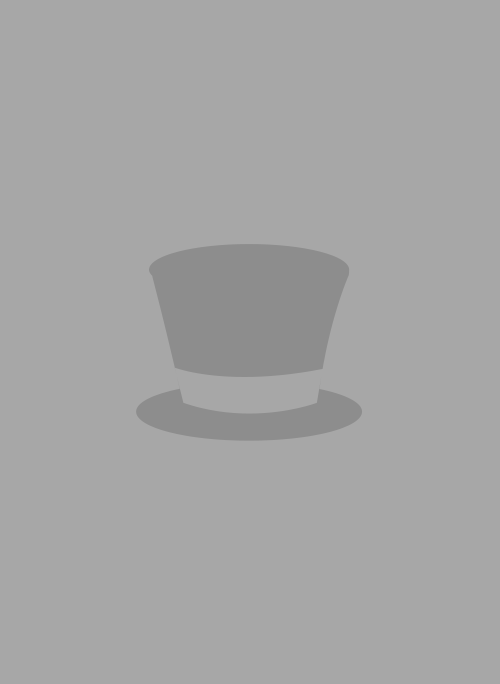校門まで行って一緒に帰る友達の紗菜(さな)を待っていた。
紗菜はテニス部なので、終わる時間が少し違って、テニス部の方が遅くなる。
だからいつも私は一人で紗菜を待つことになる。
だんだん人が少なくなってきて、残っているのはソフト部の5人の先輩と、違う部活の人が数名しかいなくなってしまった。
私は隅の方であまり先輩の目につかない所に立っていた。
「ねえ、今日の伊藤さあ、マジキツかったよね」
先輩達の声は大きいから離れていても普通に聞こえてくる。
正直に言うと、うるさい。
もうちょっと小さく出来ないのか、と毎日思う。
「それな!いい加減にしろよって言いたかった」
「それ逆ギレじゃん!」
きゃははははと、甲高い声が響く。
ホントに耳が痛い。
「でもさあ、厳しすぎて教え子にけがさせるとかマジやだわ」
ドキッとした。
私のことだよね。
「あー、茜ちゃんね。
肘に当たるとかマジで痛そうだった」
「そいえばそうだね、大丈夫だったんかな」
「ア、それなら私訊いたよ」
今までずっと話を聞いて笑っていただけの椎名先輩が話に入ってきた。
「え~、何て言ってたの」
「うーんとね、重傷の恐れがあるんだってぇ、だから病院行くって言ってたよぉ」
「あーそーなんだ~。
まあ、確かにあれで軽傷で済んだらすごいよね」
「それにしても、椎名が誰かを心配するなんて珍しくない?」
「え~、私だって心配くらいするよぉ」
「うっそだ、椎名いっつも〈私が心配してもあの人は治らないから心配しても意味がない〉っていってたじゃん」
「だってぇ、今回は茜ちゃんだったからさあ」
「そんなに茜ちゃんのことお気に入りだったっけ?」
「ううん。
だってぇ、あの子レギュラーの中でも一番下手だから、あの子が試合出て失敗すると安心するから。
だからけがされると困るなぁって思ったの」
「あははっ。それは言えてる!」
「確かにね」
空が堕ちてくるというのはまさにこの事だった。
椎名先輩の今日の優しさは心配じゃなかった。
ただ、心の中で嘲笑っていただけだった。
私が試合で失敗すると安心する?
なんで、なんで、なんで。
今日2回目の涙が零れた。
話を聞いていた事がバレないように必死で嗚咽を消した。
最終下校時刻、5分前のチャイムが鳴って、先輩たちは帰って行った。
すると紗菜がダッシュでこっちに走って来た。
「茜!ごめん、片付けが遅くなっちゃって…。え、あれ?茜?泣いてるの?」
「うう~。もうやだよ~」
「ど、どうしたの?なんで泣いてるの?」
紗菜は背中を擦りながら優しく言ってくれた。
だけどそれだけじゃ私の不安は止まらなくて、涙も止まらなくて。
「大橋さん、いいよ。
そいつは俺が送ってく」
「園川(そのかわ)君」
そこに来たのは陽葵だった。
私の左肘を引っ張ってそのまま引きずられ状態だった。
学校から少し離れた所で私は陽葵の腕に抵抗した。
「ちょ、ちょっと離してよ!
痛い!」
そう言うとすぐに腕をほどいて私を自分の隣に置いた。
「痛くしたのはごめん、わざとじゃない。
でも、お前が泣くなんて。何があったんだと思って、思わず…」
「何でもないよ。大丈夫だから」
「大丈夫じゃないだろ、じゃあなんで泣いてんの」
自覚はなかったが、私の頬には涙が伝っていた。
あれ?私泣いてた?
もう既に止まったと思った涙は今も流れ続けていた。
「あれ?あれ?」
「なにかあったんだろ?
言ってみろよ」
心が痛い。
肘も痛い。
全部痛い。
体のそこら中が。
痛い。
「陽太には話したくない」
陽葵に言うのはなぜか嫌だった。
なんでかはわからないけど、言ってしまうと自分がひどくカッコ悪い気がした。
「お前、俺に言っただろ、言ってみって。
だから、そんなお前だったから俺は話したんだぞ」
「言ったけど、それとこれはちがうから」
「なんでだよ。優太には話してたじゃねえかよ」
「…見てたの?」
陽葵は野球部なので外に、しかもグランドのど真ん中にある水のみ場で話していれば目立つのは当然だ。
だけど、私にとってそれを見られていたのが、すごく屈辱だった。
「だって、優太と話してたから…。
それにお前、泣いてたし」
そう言って私の頬に手で触れようとした。
「触らないで!」
「え…」
振り払ってしまった。
振り払った私の手も痛いけど、陽葵の手はもっと痛そうだった。
「あ、ご、ごめん…」
「もういいよ。俺には話さなくていい。
でも今日は送ってくから」
私の手を引いて歩き出した。
今度はさっきみたいに痛くなくて、優しくて、少し動かせばほどけそうなくらいだった。
ああ、この手があの人の手だったら良かったのに…。
そんなことを考えてながら私はさっきよりもっと泣いた。
うわあぁぁぁんと、小さい子どものように大声で泣いた。
周りに人がいなくて良かった。