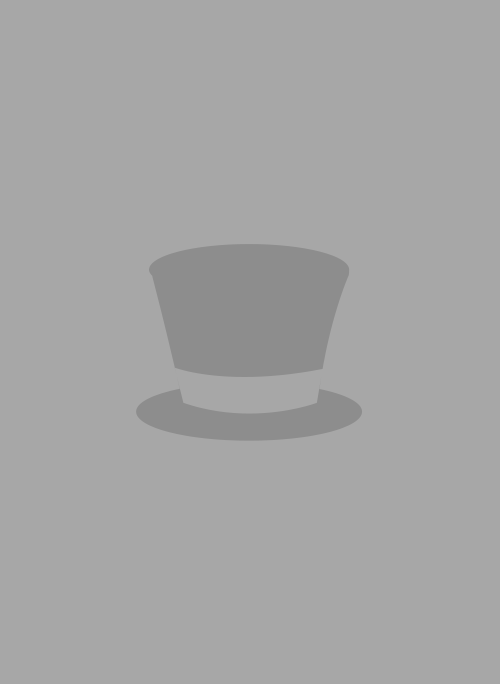この状況は気まずい。
四角いテーブルで、優太と陽太が、私を囲うようにして座った。
「で、決まった?」
沈黙を破ったのは優太だった。
「うん。決まった」
「じゃあ、言ってくれ」
二人とも、心の準備は出来ているようだった。
「私が選んだのは――…」
私が言った。
「陽太、です」
思わず、かんでしまうところだった。
あぶねー。
気温がただでさえ高いのに、私の体温はどんどん上がっていく。
「……だから、その、優太、ごめん」
ちゃんと優太に向き合って言った。
ごめん。
選んであげられなくて、ごめん。
あんなに頑張って伝えてくれたのに、ごめん。
そんな意味を込めて言った。
「俺は」
優太が言った。
「何となく、フラれるだろうなって思ってた」
「え、どういうこと?」
照れ臭そうに頭をかいた。
「自信はあったよ。
でも、それはちがくて。
茜は陽太に対しては、男だとしてみてるけど、俺は安心しきってる感じで。
恋愛対象としては違う気がしてた」
「なんか、…ごめん」
「謝んなよ。
俺がカッコ悪いだろ」
優太は笑ったけど、それは悲しげだった。
あの日の落合先生のような。
「じゃあ、俺は帰るわ。
お幸せに」
「…………」
「じゃあな」
「見送るよ」
「いいよ。家そこだし」
「いいの。ほら、陽太も」
そして、玄関で別れた。
これで、優太とはただの友達でもいられなくなってしまった。
後に残るのは、悲しさと清々しさだった。
後悔はしなかった。