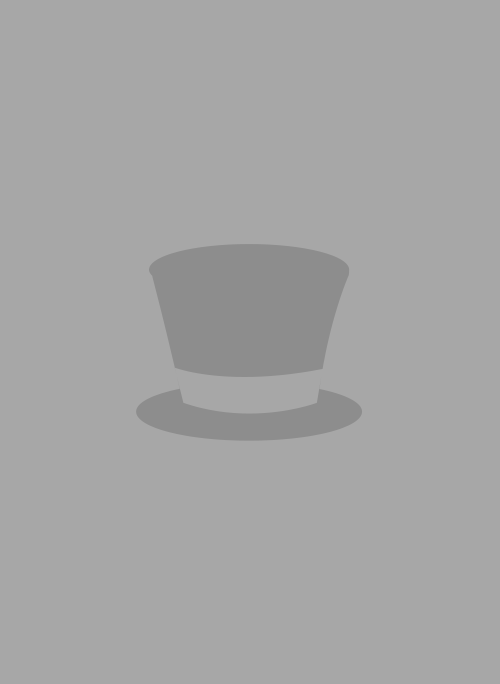8月のある土曜日、部活が休みでその日の夜には夏祭りがあった。
私はソフト部の数人と行く約束をしていたので、当然私服の予定だ。
夏休みの私の家には、誰もいない。
夜には母も父も帰って来るけど、それまでは誰もいない。
基本的には宿題をやったり、部活がない日は昼間まで寝てしまったりした。
今日は完全に後者だ。
午前11時まで寝てしまった。
しまった、今日は宿題を終わらせる予定だったのに。
今さら後悔しても遅い。
そう言えば、陽葵とは話が終わっていない。
失恋したことや、告白されたこととかたくさんあって忘れてた。
けじめを付けなきゃいけないけど、そうしたら陽葵とはもうダメになってしまいそうな気がする。
私は落合先生にフラれて、優太に慰められて、少し心の傷が癒えた気がしてる。
ひとまず、気持ちは落ち着いている。
フラれたのに、あんまりショックな気持ちは長続きしなかった。
「……ふぁー」
大きなあくびが出てしまう。
夜までは暇だから、どこか買い物にでも行こうかな。
買い物と言っても、私の住むこの田舎には服や化粧品が一気に揃うようなデパートはない。
だから、私は本屋に行くことにした。
着替えをして、お金の用意をして。
一時間すれば、私の用意は完璧に済まされた。
学校では隠しているが、私は相当な読書好きだ。
私は、同級生の皆がスマホで遊んでる時間に本を読んでいるような人間だ。
母には「本の虫ね」と言われる。
暑い日差しの下を自転車で走り抜けていく。
本屋までは20分とかからない。
ただ、汗がすごい。
汗っかきの私は店に入る前にタオルで顔や首を拭いて、自販機でサイダーを買った。
喉を通る炭酸の刺激が気持ちいい。
生き返った、やっぱり汗をかいた後の炭酸は素晴らしい。
と、一人で感動していたのが顔に出てしまっていたようで、誰かに話掛けられた。
「あれ?菊崎じゃん」
私に話掛けたのは、同じクラスで席が隣の槇田俊輔(まきたしゅんすけ)くんだった。
〈マキちゃん〉と呼んでいる。
「マキちゃん、久しぶり」
「おう、お前また本買いにきてんのかよ」
マキちゃんがニヤニヤと笑った。
私はクラスでマキちゃんだけは本好きなことが知られている。
隣の席の人がいつも違う、小難しい題名の本を読んでいたら、そりゃあわかるよな。
「うん。
マキちゃんは?」
「俺もだよ。
読書感想文の本が決まらなくてな」
「へえ、そうなんだ。
私は夏休みに入った瞬間に終わらせたよ」
「読書好きなお前と一緒にすんなよ。
俺は普段からもともと本は読まねーし、文を書くのも苦手だし」
「じゃあ、私が選んであげるよ!
文を書くのは無理だけど」
「マジで、サンキュー!」
私達は二人で店に入った。
「やっぱり、感想文はミステリーとかそういう謎解き系はやめた方がいいよ、書きにくいから。
だから、主人公が私達と同じくらいで青春物語が一番書きやすい。
共感した部分は…とか、自分も同じようになりたい…とか。
そういう文章が書けるから」
「………お前、スッゲーな。
ホントに好きなんだな、本」
マキちゃんが感心したような溜め息をはいて言った。
そう言われるのは、悪い気はしない。
「ちなみにお前は何で書いたの?」
私はある本の名前を言った。
「どういう話?」
「主人公が自分の街の秘密を解き明かす話」
「思いっきりミステリーじゃん。
てことは、さっきの体験談な訳?」
「そうだよ。私、書くのに2日かかった」
「マジかよ」
マキちゃんは笑うけど、マジだ。
本当は原稿用紙4枚半でいいのに、私は原稿用紙5枚をはみ出すところまで書いた。
「あ、これとかいいんじゃない?」
私はそこまで分厚くも、薄くもなく、中学生を題材したと思われるタイトルの本をとった。
「お前がいいって言うならこれにする」
「え、ホントに?」
「ああ。値段もいいしな」
と言って、ホントにレジの方向に向かって行った。
自分が選んだ本を誰かに読んでもらえるというのはとても嬉しかった。
マキちゃんがレジから戻って来た。
「菊崎、ありがとな。
助かった」
「ううん、私も楽しかった。
それにまだ文章出来上がってないんだから、頑張ってね」
「うっ…。
そっちは自信ない」
「じゃあ、これで」
私は用も済んだし、これ以上一緒にいる意味はないので自分の本を買いたかったから手を振った。
するとマキちゃんは私の手を引っ張った。
「なんかおごるよ、お礼に」
「いや、いいよ。
この後用があるから」
「用ってなんだよ?どうせまた本買うんだろ」
図星だ。
マキちゃんはたまに私の考えていることがわかるときがある。
「それならアイスでも買ってやるよ。
コンビニのでいいよな」
そう言うと、私の左手をつかんで歩き出した。
ここからだとコンビニまでは近いので、まあいいか、と思って私はマキちゃんに従った。
そういえば、マキちゃんは何気なく私の左手を掴んだけど、右肘をけがしたことを知ってるのだろうか。
もうギプスは外れたから、もう包帯だけだけど、今日の私の服装は七分袖なので肘から上は見えないようになっている。
「ほら、何がいい?」
マキちゃんはコンビニのアイスコーナーで私に訊いた。
「何でもいい?」
「ハーゲンでもいいぞ」
「ホントに!?
やった!じゃあこれにする」
私は遠慮することなく、250円の120mlのアイスを選んだ。
「お前、遠慮とかそういうものが全くないな」
「だってマキちゃんいいって言ったんだよ」
「そうなんだけどさ……。
まあいいや、買ってくるわ」
「うん、サンキュー」
店の外で、マキちゃんが買ってくれたアイスを食べた。
「んー!
やっぱおいしー!!」
「そりゃ良かった」
「一口食べる?」
「ん、もらう」
私はマキちゃんに〈あーん〉して食べさせてあげた。
私達は普段、学校でお互いに弁当に嫌いなものが入っているとこうやって交換しあうようになった。
周りには付き合ってるとか言われてからかわれたりしたけど、これが私達の友情なのだ。
逆に、優太や陽太とは恥ずかしくてこんなことできない。
「やっぱうめーわ。
暑いから余計に」
「ねー。また買ってね」
「もう金ねーよ」
私はふと思い付いて、
「ちょっと待ってて」
と、マキちゃんに言ってもう一度店の中に入った。
そして店のすぐ側にいたマキちゃんのほっぺたにサイダーを当てた。
「つめたっ」
「はいっ。これ買ってあげたから感想文頑張ってね」
「………菊崎にもらってもなあ」
「ねえ、それどういう意味?」
「いや、だってお前は倉元も園川もいるから彼氏持ちにもらってもなあ」
「彼氏じゃないし。友達だし」
「あのな、あっちは少なくともお前のこと友達だとは思ってないと思うぞ」
そんなこともう知ってる。
だけどそうとは言えないので、私は黙秘した。
「……ねえ、なんでマキちゃん、私のけが知ってるの?」
話題を変えたくて、無理矢理訊いた。
「あれ?俺そんなこと言ったっけ?」
「ううん。さっき、手を引っ張られた時なんで敢えて左手なのかなと思って」
「ああ。倉元に聞いた」
思い返してみれば、マキちゃんは優太と同じバスケ部だった。
「外練行ったら、あいつ急にいなくなって。
それで探したら、菊崎と抱き合ってるし」
「え、そこまで見てたの」
「見てたんじゃなくて、あんなグランドの真ん中であんなことやってたら嫌でも目につくわ」
「痛て」
ぺし、と頭をチョップされた。
「だから、園川は知らんけど、倉元のことをただの友達とかは言ってやるな。
結構あいつ傷ついてるから」
「そうなんだ……」
知らなかった。
じゃあ、あの時も。あの時も。あの時も。
優太は傷ついていたのかもしれない。
「これからは気を付ける」
「お、急に素直になったな。
どうした?」
「失礼な、私はいつだって素直で優しい乙女である」
「どこに乙女がいるんだよ」
「ここにおるわ。
お前の目玉は節穴か」
今度は私がマキちゃんのすねを爪先でけった。
「お、お前なそれは痛てーだろ」
「うるさい。
純情培養の乙女に失礼なことを言う貴様が悪い」
「なんだよ、純情培養って」
また鼻で笑ったので、また爪先で、今度は膝裏をけった。
「……お前な」
「乙女を鼻で笑うな」
苦しむマキちゃんを見ていると、何となく自分まで笑えてきた。
「ちょ、笑ってんじゃねーよ。
マジでいてーから」
そう言うマキちゃんも少し笑っている。
男女の友情はあり得ない、と誰か芸能人が言っているのを見たことがあったけど、これこそまさに男女の友情である。
マキちゃんとは付き合いこそ浅いけど、信頼はすごくある。
だから、今こうして笑い合っていられる。
もう優太や陽太とは友情ではなくなってしまった。
《男と女》というのを認識させられてしまったから。
「マジで痛てーよ、骨折れたわ」
「大丈夫。私がもっと、芯まで砕いてあげるから」
「何が大丈夫なんだよ!?」
私は自分の言ったことに対しても、マキちゃんのマジなリアクションにも噴いてしまった。
「あれ?もうこんな時間じゃん」
何気なくコンビニの中の時計を見ると、1時を回っていた。
「どうりでお腹が減ると思った」
「お前、さっきアイス食ってなかった?」
「アイスとお昼ご飯は違うのー」
「そんなこと言って…。
また太るぞ」
「ねえ、またって何?
私が人生で太ったことなんてないけど?」
周りの人にクスクスと笑われていることに気がついた。
中には、迷惑そうに見ている人もいてかなり恥ずかしい状態だった。
「…………」
「…じゃあ、帰りますか」
「そうだな。
送って行こうか?」
「え、でもマキちゃん歩きでしょ」
「俺がこぐから、お前は後ろ乗ればいい」
「いいの?マキちゃん家反対方向じゃん」
「いいよ、別に」
「じゃあお願いします」
「おう」
本当は一人で帰りたかったけど、特に断る理由もなかったから私は自転車の荷台にまたがった。
いつもだったら、15分かかる距離をマキちゃんは10分かからずに到着した。
「じゃあ、今日はありがとね」
「ああ。俺も本選んでくれてホント助かった」
「じゃあ、バイバイ」
「じゃあな」
マキちゃんは一人で歩いて帰って行った。