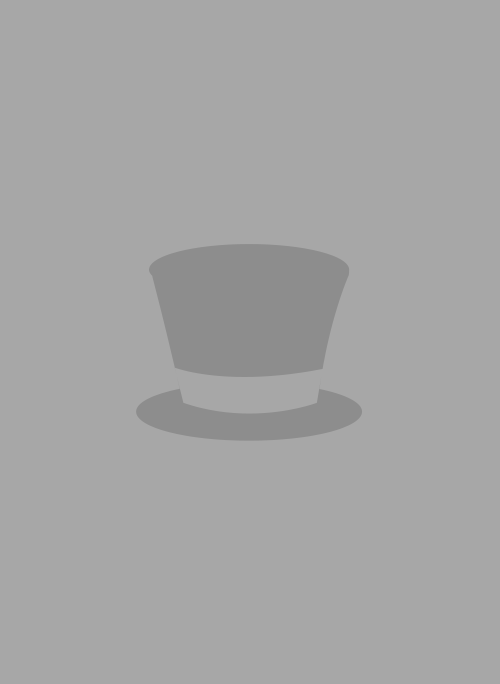陽葵に告白された。
…………。
あれ?あの人、つい最近まで彼女いたよね。
で、また違う人に告白?
ふざけてんのかな。
でもアイツはかるいヤツじゃないし、チャラくもないし。
本気なのかな?
そう考えると頭が沸騰しそうだ。
「どーしよー」
部活のない私は、また誰もいない教室で宿題をしていた。
今のは独りごとであり、誰かに聞いて欲しかった訳ではない。
あくまでも。
でもまた落合先生に会えないかな~。
「あれ、またお前か」
期待通り。
落合先生は現れた。
すっごい運がいい。
「今度は何の宿題だ?」
「今日は数学と理科です」
「そうか、じゃあな」
「ちょ、先生。自分の苦手科目だからってほっとかないでくださいよ」
「ち、バレたか」
「落合先生が理数系苦手なのは学年全員が知ってることですよ。イヤ、学校全体が知ってるかも」
「嘘つけ」
「はい。嘘の嘘の嘘の嘘の嘘の嘘です」
「どっちだよ」
実は本当なのだが。
それはそうと、落合先生はまた私の席の前の椅子に座った。
「理科はまだいいけど、数学は本当に俺、無理だから」
「奇遇ですね。私もです。
数学なんて数字見るだけで気持ち悪くなります。数学作った人って、人間の域を越えてます」
「ははっ。言えてる」
今日は全て本音で話していた。
先生に会うのが久しぶりだからだろうか。
言葉が出てきて止まらない。
30分後、やっとのことでプリントが終わった。
「お前、ホントに理数系嫌いなんだな」
「その言葉、そっくりそのまま先生にバットで打ち返してやりたいですよ」
「はあ、数学教えるのってこんなに大変なんだな」
先生はそう言って、携帯灰皿を取り出して、煙草を口にくわえた。
「なっ…。
こんな所で、しかも教師が煙草吸っていいんですか!?」
「イヤダメだけど。つーか生徒の前で吸ったらもっと起こられるけど」
「じゃあなんで…」
「君は、大人っぽいから妙に落ち着く」
心臓がまた跳ねた。
先生といると寿命が縮んでしまう。
「君といると、なぜか生徒といる気持ちにはならないんだ。
他の生徒や、友達、家族とも違う感じがする」
「……………」
君は特別な存在なんだ。
そうやって言われてる気がした。
また跳ねた。心が踊る。
「先生…」
「第一、生徒にこんなこと言ったらダメなんだけどね」
先生が笑った。
熱が灯る。夏の太陽より、私の心は焼ける。焦がされる。
「先生、私、好きな人がいるんです」
「うん?」
急にどうしたという対応だった。
「先生、今いくつですか?」
「25だよ」
「そうですか。
じゃあ、11歳年下の異性に想われていたら迷惑ですか?」
「……それは君たちと同じ年齢ってこと?」
「そうです」
「それは…」
思わず、息をのむ。
涼しい風が頬を撫でる。
「世間体という言葉がある。
君はもちろん知っているよな。
だから俺は、生徒に被害が及ばないのなら愛せる。でも、一度でも世間からの被害に遭ったのなら、いくら好きでも、それでも守ってあげるとは言い難いかもしれない」
先生は終始穏やかな口調だった。
その答えは、私にとって意外で少し奇跡が起こるかもしれないとさえ思った。
「私、好きな人いるんです。
でも他の人に告白されて…、どうしたらいいんですかね」
「その告白してきた人のこと、君は好きなの?」
「いいえ、恋愛感情はありません。
でも告白された時、無理矢理キスされて」
「え、無理矢理?」
「はい。
私もそれが初めてだったんで、すごく頭にきて。
でも大事な友達だったので、どうしたらいいかわからなくて」
「今の子は進んでるんだねぇ。
俺の時はそんなことするヤツ居なかった」
「先生、急におじさんくさくなりましたね」
「おじさん言うな」
こつ、と頭を小突かれた。
先生が触れたのは本当に少しだったのに、触れられた場所が熱い。
「話戻しますけど、先生ならどう思いますか?」
「どうもこうもないよ。
自分の意思に従う」
また体温がはね上がった。
「……わかりました。
じゃあ、私もそうします」
「そうだね、そうした方がいい…」
私は先生の唇を塞いだ。
唇と唇が触れあっていた時間は2秒にも満たなかった。
「え、……」
「先生、私、先生のことが好きなんです」
先生の口は、ちょっとだけ煙草の臭いがした。
嫌いな匂いなのに今日は、すごくいいにおいにしか思えない。
「先生は、私なら愛せますか?」
先生の頬は紅く染まっていた。
それがすごく嬉しくて、先生に触れたくなった。
私は指で、先生の腕を触った。
「ねえ、先生。
私のことどう思っていらっしゃるんですか?」
「えっと、その…」
真面目な落合先生は真剣に考えてくれていた。
その姿が愛しくて愛しくて。
「先生、もう一回キス、していいですか…?」
先生は驚いていたが、すぐまた顔を真っ赤にして椅子に座り直して言った。
「…いいよ。君なら」
嬉しくて、今度はいっぱいした。
何度も、何度も。
何度も。
これが私の危ない恋の始まりだった。