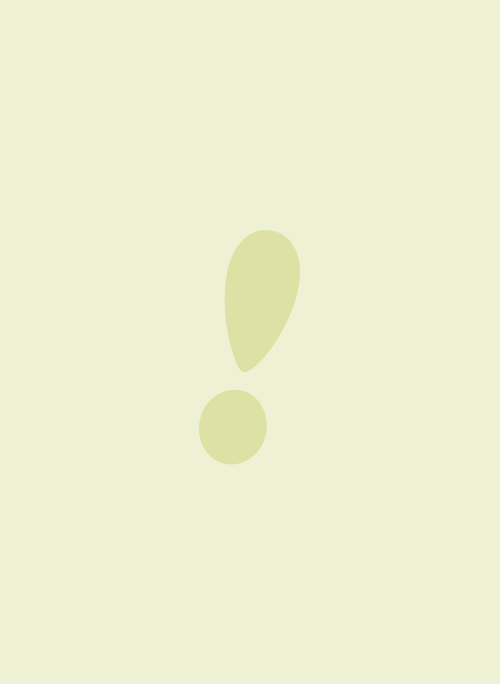深町は、言葉が苦手だけれでも、なるべく言葉を選んで。
「古い北ヨーロッパの言い伝えなんだけど、
絶海の古城に双子のprincessが居てね、」
その手の話が好きな松之は、深町の方を見て。
「うん...?」
「その二人には、お互いに家が決めた許婚者が居て..
二人ともそれぞれに、幸せだったそうなんだ。」
「ふーん、そんなものかな」と、松之は。
「ところが、ある時、4人で会う機会があって。
古城だから、舞踏会とか、そういうんだろうな。
その時に....。その双子の、妹さんの方かな。
お姉さんのパートナーが、気になってしまった。」
「ふーん...。」
松之は感じる、実感として。
深町は、あまりたとえ話が得意でないが、それでも続けた。
「それで、お姉さんのパートナーの方も、
妹さんが気になりはじめてしまった。
まあ、そういうのは雰囲気だから、そういう事もあるだろう。」
「うんうん」と、松之は生返事。
雰囲気なんかじゃない、それは。そう言いたいが...
「でも、当時の事だから、それはそのままだ。
妹さんのパートナーも、本気で彼女を愛してくれている。
だから、そのまま...で良いんじゃないか、自分さえ我慢すれば、と、彼女はそう思った。」
「良くないよ、それは。」松之は、彼らしく言葉を発す。
「まあ、松さ、これは伝説だから。それで、そのお姉さんの方も、その妹さんの変化には気づいていた。でも、
やっぱり当時の事だから、しきたりを重んじた」
「うーん...。」松之は唸る。確かに制度は守るべきだ。
しかし...?と、彼は思う。
「それで、お姉さんの方は、それを承知で結婚した。
妹さんも迷ったが、でも、当時の事だから。
従わざるを得なかった。」
「それで?」
「うん、物語としてはそれで終わりだけど、いつまでも
その4人は幸せに、いつも一緒に暮らしていたそうだ。
その絶海の古城は、今でも観光名所になってるらしいな。」