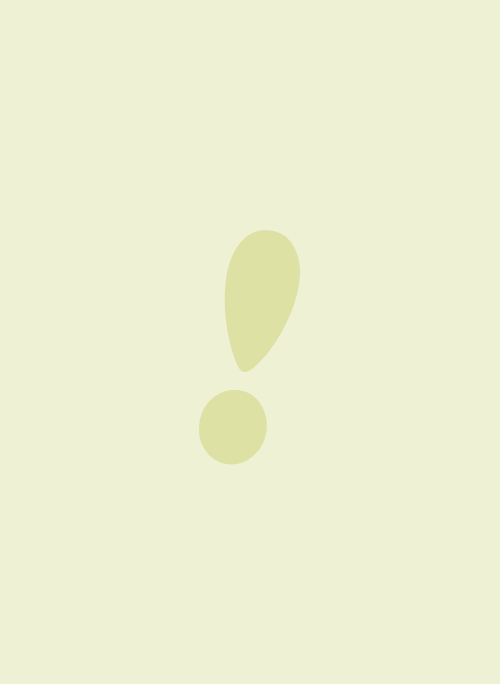シュウのイメージ中にある理想の恋人だったら
無闇に抱きしめられたら撥ね逃けるだろう、と。
でも、シュウに抱きすくめられたままだったから、
なんか、慣れてるんじゃないかな?と疑念を持った。」
「そうか。」シュウは、自分の中で納得できていない気持ちを
叔父に解析されて、初めて納得したような気持ちになった。
「そう疑うと、誘われ慣れてるような感じに見えて、
ああ、こういう人だと他にもボーイ・フレンドが一杯いるんだろう、
恋人もいるかもしれない、って嫌になった。.....更に。」
叔父は、深町の顔を見た。
「ムスクの香水が、朋恵ちゃんと同じだったから、あの頃、彼女は割と
男にモテてて、それに嫌になって投げ出した記憶を思い出した。」
内心、分かってはいても、的確に分析されると
改めて納得する。
「どうしてそんな事が分かるの?」と深町は言う。
叔父は、事も無げに「分かるさ。僕だってシュウの年には
そんな事で悩んだ事もあったから。
でも、それは誤解かもしれない。
今回は事故回避だろ?気が動転して、諒子ちゃんは
どうしていいか分からなかったかもしれない。
それに、他の部分はシュウの想像に過ぎないし....
単に、シュウはさ、朋恵ちゃんを連想して
忌まわしい記憶から逃げたかっただけさ。
諒子ちゃん自身を何も見ていない。」
うーん....と頷き「そうなのかな...。」