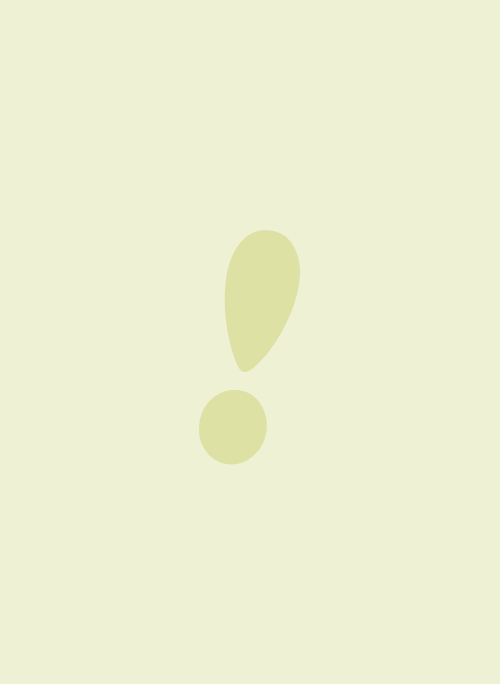ディスクが終わったので、叔父はやはり
オスカー・ピーターソン・トリオの"The trio"を掛けた。
今度は、CDでなくレコードで。
黒いビニールのレコードを、深町は珍しそうに見た。
ターンテーブルに慣れた手つきでそれを乗せると
叔父は、白いカートリッヂをそっとレコードに乗せた。
SATIN、と刻まれた白いカートリッジは、天使の衣擦れのように
繊細で、凋密な音を奏で始めた。
"I've never been in love before"恋したことはない、と言う曲だ。
運命の人に出会ってしまって、いままで恋した事などないけれども
恋せずにはいられない、と言う情熱的な曲だ。
「なあ、シュウ」叔父は曲を聞きながら
この曲の意味を告げる。
「恋したことない、なんて言ったってなぁ。
だいたい、相手の子がもし「深町さん好き」って思ってても
シュウがいなくなっちゃたら、その思いを告げる事もできないだろ?」
と、叔父はおどけてそう言う。もともとこの人は、ユーモアが好きなのだ。
「だからさ、もっと気楽に生きようよ。
...そうだ、その諒子さんとか夏名ちゃん?あと...誰だっけ、あ、そうか。湯瀬さんか。
みんなでパーッとやったらどうだ、ここの裏山でバーベキューとかさ。
いくらでもあるぞ、空き地は。
時節柄、海もいいじゃないか。ビーチも近いぞ。
真夏にビキニの女の子、なんて想像だけでも楽しいじゃないか。
連れてこいよ、今度。」
叔父は、楽しそうだ。