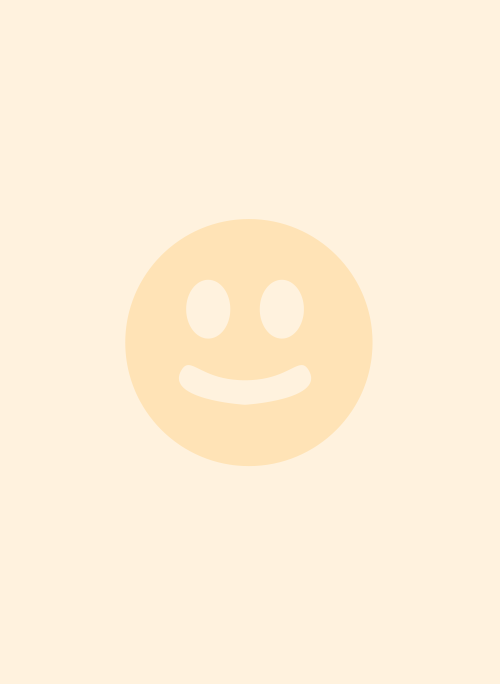皆の記憶から消えるのが早すぎて、私は一瞬本当に彼女は妖怪がお化けだったのではないか、と思ったほどだった。
まあいつも通りに雑誌をぼんやりと読んでいた亀山が、「あいつは迷惑だった・・・」と呟いたから現実だったんだ、と思えたのだけれども。
「あの・・・梅沢さんを慕っていた若い女性ですよね、田中さん」
マスターがそういうのに、私はちっちと人差し指を動かす。
「慕っていたわけじゃなかったんですよ。真似をして、乗っ取ろうって企んでいたらしいです。本人がそう言って暴れてましたからねえ~。凄いこと考えますよね?」
へえ、と男二人がはもる。恋愛フィルターがかかっているにもかかわらずマヌケに見えるのは、多分本当にそうなのだからだろう。呆気に取られるのはようく判るよ、君たち。私は鷹揚に頷きながら、お酒を口にした。
「で、辞めちゃったのか」
「そう」
「ってことは翔子、全部楽になったってこと?」
「そう。素晴らしい!」
それは良かったな、正輝の手が伸びてきて、何と頭を撫でてくれた。
私は赤面した。
あ・・・頭を撫でられるとかっ・・・!うきゃー、親にされて以来だわ!ダメ、冷静にならなきゃ鼻血でそう。折角全身を完璧に装っているのに鼻の穴にティッシュなんか突っ込んでたら、コメディ以外の何者でもなくなってしまう。耐えろ、鼻血はダメよ、私。
正輝の愛撫を上手かつ紳士的に見ないふりをして、マスターがグラスを拭きながら言う。
「とにかくお二人にまたご来店頂きまして、嬉しい限りです」