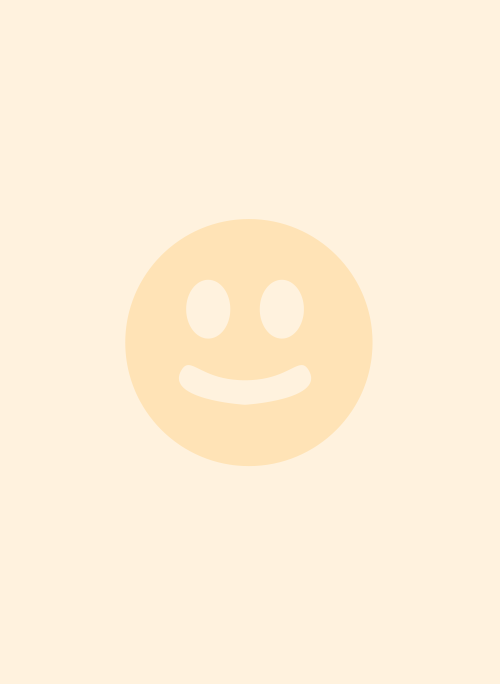「・・・翔子?」
正輝の声はぼんやりとしか届かなかった。それよりも、自分の胸の音が大きかったから。ドクドクと傷口があいて、大量の血が流れ出しているようだった。
「帰るわ」
「え?」
全身が震えるような怒りに支配されて、私は鞄を引っつかむ。
「・・・女心が判らない鈍感な正輝。これ以上一緒にいたら刺してしまいそうだから、今日は帰る。また連絡するわ」
「ちょ・・・」
何か聞こえたけれど、そのままバタバタと店を飛び出してしまった。周囲のお客さんの視線が背中に張り付いてくるようだ。
お洒落というのはちっとも全力疾走には向かない。だけどとにかく、ヒールのせいでバランスが悪いなんて言ってられない。自分の部屋に帰りたかった。すぐに。それから泣きたかった。
夜の中、私は懸命にピンヒールで走って行く。
正輝一人を、置き去りにして。