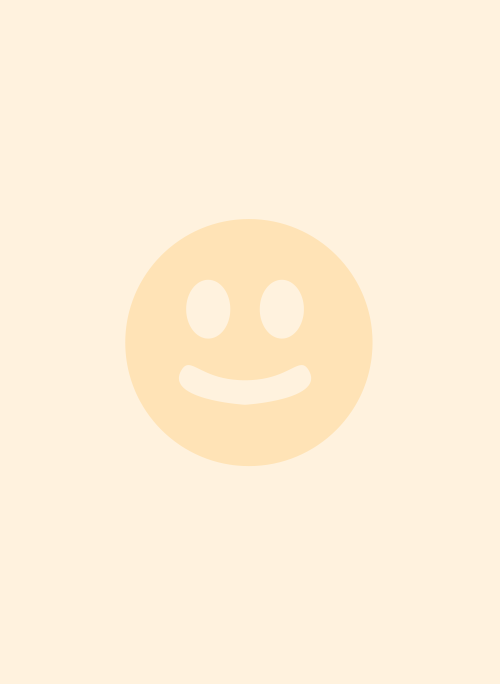ざくっと遮って言った。正輝は驚いた顔でちょっとの間言葉をなくしたけれど、ゆっくりと身を乗り出して声を低め、説得するような口調で言った。
「翔子、大したことじゃない。あの子がいくら真似したところで翔子とは違う。それは判ってるだろう?それに、例えばややこしい恋愛問題なら社内の人には話したくないってこともあるんじゃないか?そこに偶々お前の彼氏がいた。だから聞こうとしたんじゃないのか?それだけの話だろう」
硬い表情のままで私は辛抱強く言葉を返す。
「私なら、人様の彼氏に恋愛相談はもちかけないわ」
「翔子ならそうだろう。だけどあの子は違うんだろうな」
憮然とした。
私は八つ当たりでフォークをレタスに突き刺す。それを前から見ていた正輝が、お手上げだっていう風に肩を竦めた。
「あの子はそんな悪いこじゃないと思うぜ。挨拶した時だって、ハキハキした感じだったし。素直な可愛いらしい新人に見えたよ」
「素直?可愛らしい!?」
「翔子も一緒にいただろう、挨拶の時」
何てこと・・・一緒にいただろうって、それはこっちのセリフよ!私はフォークを放り出して、身を乗り出した。
「そうよ一緒にいたのよ。だから判ったでしょう、あの子の媚びた仕草が!笑顔も態度も、あの時のあの子の挨拶、私には計算高く見えたのよ。だから驚いて思わずガン見しちゃったんだから!」
「それは言いすぎだろう。あの子はそんなんじゃ―――――――」
限界だ。
ガタン!と大きな音を立てて私は立ち上がった。