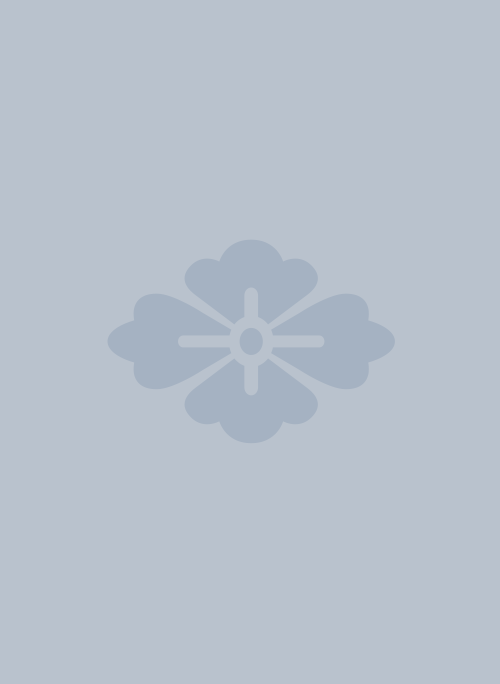「本当に宜しいのですか、シモーヌ様?」
申し訳なさそうにそう尋ねるジャンヌの方が少し小柄で、何度も戦いに出ていたからか、鎧も色褪せ、どちらかというと、シモーヌが「乙女」で、彼女がお付の者のように見えた。
「ええ。兄……いえ、父には既に文を送っていますから、大丈夫です。それに、良くないお告げがあったのでしょう?」
背の高いシモーヌがそっと馬を近付けてそう言うと、ジャンヌは苦笑した。
「兄からお聞きになられたのですね? もう、兄さんったら、私には二度と口にするなと言っておいて、自分は喋っちゃうなんて!」
「心配なのですよ、それだけ貴女のことが。それに、お兄様の言葉が無くても、貴女に元気が無ければ、出来るだけ傍にいますよ?」
「ありがとうございます。ですが、その……本当に宜しかったのですか?」
そう言うと、ジャンヌはチラリと後ろを見た。そこには、弓兵等を率いている、同じく馬上の黒髪の青年がいた。
「よいのです」
目が合っても何も話そうとはしないバルテルミ・バレッタこと、少し髭の伸びたバートをチラリとみると、シモーヌはそう言い、作り笑いを浮かべた。
「あの……本当にバルテルミさんとは……」
「終わりました。私はまだ好きですが、縁談もきているとのことですから、もう何も無かったことにしなければなりませんし……」
最後の方は、自分自身に言い聞かせる為か、少し小さな声になっていた。
「貴族の方も、それはそれで大変なのですね……」
「まぁ、乙女も既に貴族であらせられますよ?」
シモーヌが微笑みながらそう言うと、ジャンヌも微笑んだ。
「そういえば、そうでしたね! まだ実感などありませんが……。でも、ドンレミの皆の税金が免除されることには感謝しています」
「そうですね。陛下には珍しいご英断だと思いました」
「珍しいって……」
シモーヌの毒舌にジャンヌが苦笑すると、彼女は続けた。
「失礼ながら、今乙女の部隊にいるのは傭兵だけですよね? ですから、これくらいの本音を言っても大丈夫だと思いあす」
「それはそうですが……もう少し何とかなりませんか?」
ジャンヌが困った表情でそう言うと、シモーヌは冷ややかな笑みで応えた。
「それは、陛下におっしゃって下さい。お聞きしていますよ。同じお城におられながら、お二人が互いに避けておられたということを」
「それは……」
「確か、この出陣も陛下のご命令ではありませんよね?」
「今までもそういうことはありましたよ。むしろ、その方が多いと思います」
自分がシャルルをランスで戴冠させた手前、流石に表だって彼を批判こそしなかったが、それでもシモーヌの言葉を肯定する彼女の言葉には、彼女と同じ気持ちが入っていた。
「乙女も大変ですね……」
そんな彼女を見ながら、少し憐れむ表情でシモーヌがそういうと、ジャンヌは苦笑した。
申し訳なさそうにそう尋ねるジャンヌの方が少し小柄で、何度も戦いに出ていたからか、鎧も色褪せ、どちらかというと、シモーヌが「乙女」で、彼女がお付の者のように見えた。
「ええ。兄……いえ、父には既に文を送っていますから、大丈夫です。それに、良くないお告げがあったのでしょう?」
背の高いシモーヌがそっと馬を近付けてそう言うと、ジャンヌは苦笑した。
「兄からお聞きになられたのですね? もう、兄さんったら、私には二度と口にするなと言っておいて、自分は喋っちゃうなんて!」
「心配なのですよ、それだけ貴女のことが。それに、お兄様の言葉が無くても、貴女に元気が無ければ、出来るだけ傍にいますよ?」
「ありがとうございます。ですが、その……本当に宜しかったのですか?」
そう言うと、ジャンヌはチラリと後ろを見た。そこには、弓兵等を率いている、同じく馬上の黒髪の青年がいた。
「よいのです」
目が合っても何も話そうとはしないバルテルミ・バレッタこと、少し髭の伸びたバートをチラリとみると、シモーヌはそう言い、作り笑いを浮かべた。
「あの……本当にバルテルミさんとは……」
「終わりました。私はまだ好きですが、縁談もきているとのことですから、もう何も無かったことにしなければなりませんし……」
最後の方は、自分自身に言い聞かせる為か、少し小さな声になっていた。
「貴族の方も、それはそれで大変なのですね……」
「まぁ、乙女も既に貴族であらせられますよ?」
シモーヌが微笑みながらそう言うと、ジャンヌも微笑んだ。
「そういえば、そうでしたね! まだ実感などありませんが……。でも、ドンレミの皆の税金が免除されることには感謝しています」
「そうですね。陛下には珍しいご英断だと思いました」
「珍しいって……」
シモーヌの毒舌にジャンヌが苦笑すると、彼女は続けた。
「失礼ながら、今乙女の部隊にいるのは傭兵だけですよね? ですから、これくらいの本音を言っても大丈夫だと思いあす」
「それはそうですが……もう少し何とかなりませんか?」
ジャンヌが困った表情でそう言うと、シモーヌは冷ややかな笑みで応えた。
「それは、陛下におっしゃって下さい。お聞きしていますよ。同じお城におられながら、お二人が互いに避けておられたということを」
「それは……」
「確か、この出陣も陛下のご命令ではありませんよね?」
「今までもそういうことはありましたよ。むしろ、その方が多いと思います」
自分がシャルルをランスで戴冠させた手前、流石に表だって彼を批判こそしなかったが、それでもシモーヌの言葉を肯定する彼女の言葉には、彼女と同じ気持ちが入っていた。
「乙女も大変ですね……」
そんな彼女を見ながら、少し憐れむ表情でシモーヌがそういうと、ジャンヌは苦笑した。