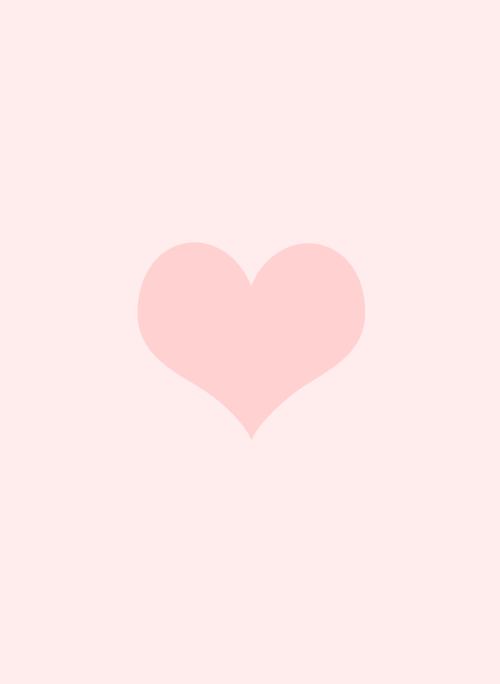もうどれくらい歩いただろうか。
景色から人工的なものは消え、踏みしめる大地はアスファルトの痕跡もない砂漠が続いていた。
アトマイズはかろうじて体内の水分を補うことはできるが、こう長く太陽に灼きつけられると喉が水を欲する。
砂漠では昼は地獄のように暑く、夜は黄泉のように寒く冷たい。
見渡す限りの砂。
時折、行く手を阻むように砂嵐が舞う。
その時はいつもより大きな砂嵐だった。
岩陰に隠れ体を守らないと、一瞬にして砂がカラダを覆い尽くすほどだ。
嵐は2日ほど続いた。3人はその間じっと静まるのを待つしかなかった。
数日後、あたりは日常の砂漠に戻った。
足止めを食ったおかげで次の目的のオアシスまで―そこもすでに朽ちた町だろうが、何か手に入るかもしれない― 急がねばならない。
武が足元の異常に気付いた時、足はすでに砂に吸い込まれていた。
「流砂だ!!」
あっという間に身体の半分まで飲まれていく。
武を引き上げようと2人が近づいた時だった。
轟音とともに3人は砂の中に落ちていった。
まるで大きな砂時計の、最後の一握の砂が落ちるような勢いだった。
視界は真っ暗になり鼻から口から気管へ砂が入りこみ、3人は瞬く間に死への扉を開けた。
景色から人工的なものは消え、踏みしめる大地はアスファルトの痕跡もない砂漠が続いていた。
アトマイズはかろうじて体内の水分を補うことはできるが、こう長く太陽に灼きつけられると喉が水を欲する。
砂漠では昼は地獄のように暑く、夜は黄泉のように寒く冷たい。
見渡す限りの砂。
時折、行く手を阻むように砂嵐が舞う。
その時はいつもより大きな砂嵐だった。
岩陰に隠れ体を守らないと、一瞬にして砂がカラダを覆い尽くすほどだ。
嵐は2日ほど続いた。3人はその間じっと静まるのを待つしかなかった。
数日後、あたりは日常の砂漠に戻った。
足止めを食ったおかげで次の目的のオアシスまで―そこもすでに朽ちた町だろうが、何か手に入るかもしれない― 急がねばならない。
武が足元の異常に気付いた時、足はすでに砂に吸い込まれていた。
「流砂だ!!」
あっという間に身体の半分まで飲まれていく。
武を引き上げようと2人が近づいた時だった。
轟音とともに3人は砂の中に落ちていった。
まるで大きな砂時計の、最後の一握の砂が落ちるような勢いだった。
視界は真っ暗になり鼻から口から気管へ砂が入りこみ、3人は瞬く間に死への扉を開けた。