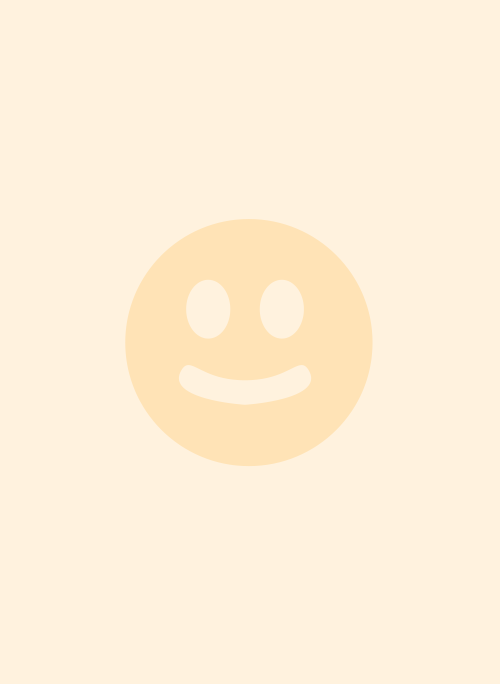柿っぽい何かから出て来た男の子は、産まれたてという程小さくはないですが、幼稚園にあがる程かは微妙な年頃の子供でした。
ヤバい。
二人は目を見合せました。それはそうです。知らなかったとはいえ自分たちが幼児を虐待してしまっていたっぽいのですから。
見合せる二人の目は長年連れ添った夫婦の目付きではなく、共犯者どうしのソレでした。
ですがおじいさんは気付きました。男の子はあれだけやらかした柿の中に居たのに怪我ひとつしていない。それどころかアザすらなく、ただ振り回されたせいでか気持ち悪がっているだけっぽい事に。
おばあさんも気付きました。二人の犯行を誰も見ていない事実に。当の男の子さえも。
ニヤリ。
二人は再び共犯者の目を見合せました。意思統一にはそれだけで十分でした。
「大丈夫かい坊や。ワシらが来たからにはもう安心だ。悪い奴らは追っ払っておいたからな」
「まったくヒドイ事をする人たちがいたものですよ。でももう居なくなりましたからね?」
二人の演技は完璧で、まだ意識がもうろうとしていた男の子はスンナリと信じました。事件は闇に葬り去られたのでした。
ヤバい。
二人は目を見合せました。それはそうです。知らなかったとはいえ自分たちが幼児を虐待してしまっていたっぽいのですから。
見合せる二人の目は長年連れ添った夫婦の目付きではなく、共犯者どうしのソレでした。
ですがおじいさんは気付きました。男の子はあれだけやらかした柿の中に居たのに怪我ひとつしていない。それどころかアザすらなく、ただ振り回されたせいでか気持ち悪がっているだけっぽい事に。
おばあさんも気付きました。二人の犯行を誰も見ていない事実に。当の男の子さえも。
ニヤリ。
二人は再び共犯者の目を見合せました。意思統一にはそれだけで十分でした。
「大丈夫かい坊や。ワシらが来たからにはもう安心だ。悪い奴らは追っ払っておいたからな」
「まったくヒドイ事をする人たちがいたものですよ。でももう居なくなりましたからね?」
二人の演技は完璧で、まだ意識がもうろうとしていた男の子はスンナリと信じました。事件は闇に葬り去られたのでした。