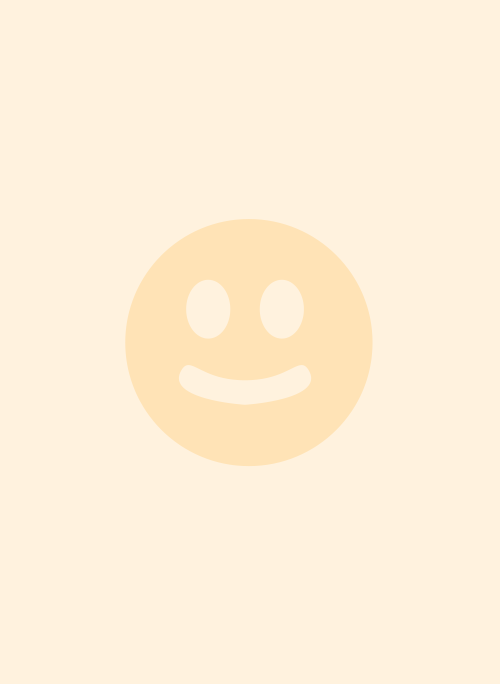中一時の父の日、私はお父さんに、手作りのクッキーをプレゼントした。
「そしたら、『お前がそういうことをするから離婚できないんだ』って叩かれた」
「……、」
坂下は何も言わずに黙って聞いてくれていた。
不思議とどう思われるかなんて気にならなかった。
「結局、それがきっかけで離婚になったんだ」
あの時、自分が何をどう思ったのかは全く覚えていない。
淋しいと思ったわけではない。
がっかりしたわけでもない。
ただ、自分がやって来たことがまるで無駄だったこと、むしろお父さんを怒らせていたということを突き付けられて、何もかもが真っ暗になってしまった。
お父さんが家を出ていって、お母さんは朝から晩まで働き通しで、孝四朗は小さくて。
それでもお母さんの変わりに家事をした。
孝四朗は泣き、剣二も三久も我慢していた。
お母さんは、毎日私に「ごめんね」と言っていた。
毎日毎日、その繰り返しだった。
こんなときに側に居てくれたのが、光太だった。