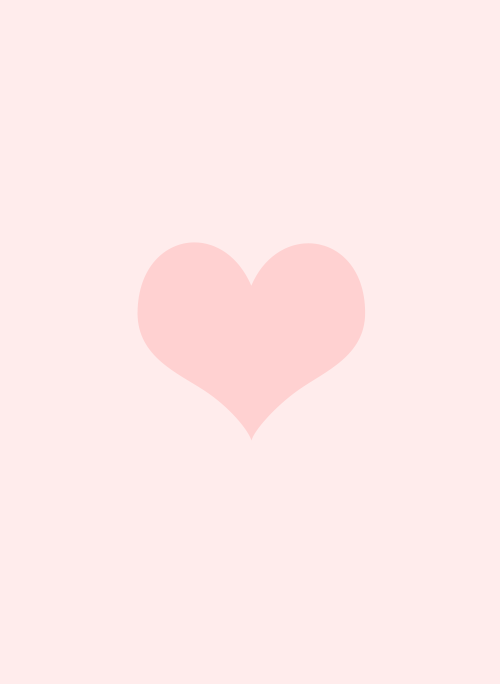もうすっかり紗江の戦闘心は失われていた。
その手元は、紅茶で唇を曖昧に濡らすだけで少しも落ち着かない。
「い、いえ…やはり初対面の方とは…ほら、やっぱり緊張しちゃうし」
まさに狙っていた所にボールが飛んできたとでも言いたげに、目の前の男はにっこりと笑みを深める。
「話はしなかったけど、僕も結構ここへ通ったよね?
そうだなあ…この喫茶店が出来てしばらくからかな」
「ええ…ああ、そうだと…思いますね」
「ご心配は無用だよ、どこへ行くかは全てお嬢さんの采配に任せるつもりだから」
それなら君だって、僕に変な所へ連れ込まれるという杞憂も無くなるだろう?
それはもはや、客と店員の立場を取った甘い脅迫に近かった。
けれど飯村の穏やかな低い声色のお陰なのか、怖さはちっともない。
良くも悪くも。悪くも良くも。
ここでようやく紗江は、カウンターに佇んで聞き耳を立てている響子へ視線を向ける。
助け舟を出して欲しい。
そんな想いを精一杯に込めて。
だがしかし、響子も飯村と同じように笑いを深めるだけだった。
言いくるめられた貴女が悪いのよ、とでも言いたげに。
「………あ、あのぉ…でも」
残りの頼みの綱はマスターだが、彼の姿は飯村が来店してから見ていない。
恐らく、この出来事に巻き込まれたくないとばかりにキッチンに籠っているのだろう。
もはや紗江に味方は店内に誰も居なかった。
「よしっ、じゃあ決まりだな」
そう飯村が嬉々として言っても、紗江に反論の言葉は何も浮かばなかった。
デートではない。
小説の参考にしたいから。
そう頼みこむ常連客を、無碍にも扱えない。
だからこそ困るのだ。
「お嬢さんのお休みはいつ?」
「今週の土曜日です」
答えたのは響子だった。
振り返れば、明らかにこの状況を楽しんでいる笑みが紗江の席からも見えた。
「そうか…うん、なら大丈夫だな。じゃあその日の午前9時にここへ待ち合わせということで」
あっという間に決まった日程に、紗江が狼狽える暇すら与えず、飯村は早々に席を立つ。
「じゃあそういうことで。ご馳走様」
「はぁい、お会計はこちらですー」
「ちょ、ちょっと待って下さい、あの」
「んー?何?」
「お会計、ちょうど600円になりますー」
「1000円でお願い」
「かしこまりました」
「あの!飯村さん!」
「はあい、なにー?」
出入口ドアのベル音に、飯村の間延びした声が混じる。
外は既に闇夜で、商店街のネオンが目に眩しい。