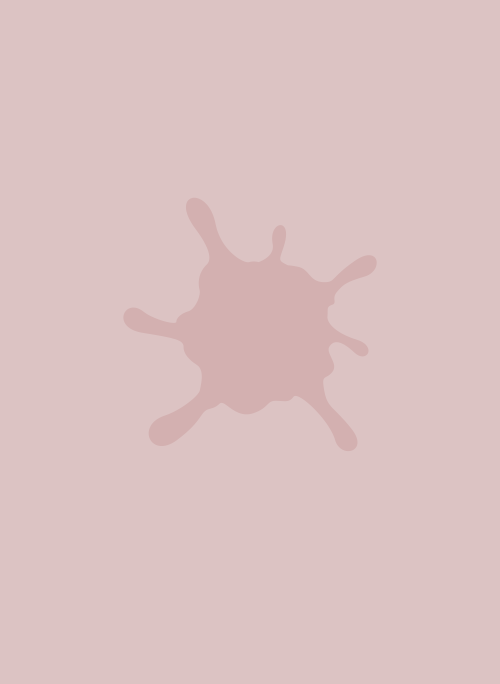「あー、腹減った」
ホームから改札を抜け、自転車置き場までの薄暗い通路を歩く。田舎ということもあり、駅のそばに民家が建ち並んでいるせいで、申し訳程度にしか灯されていない街灯があるだけのなんとも寂しい場所。
まわりの家々から洩れる光はまるで団欒の象徴のように、各戸それぞれ一部屋だけに集中していて夜道を照らす役割などないに等しい。
俺は鞄から携帯を取り出し、フリップを開いた状態で下に向け、自分の自転車を探す。
「お、あったあった」
目印としてサドルの後ろに貼ってあるシール(ちなみに書いてある文字は“要注意人物”だ)を確認し、鍵を差し込むと自宅へとチャリを走らせる。
電車を降りた時に感じた、体中をねっとりとまとわりつく生暖かかった風が、ペダルを漕ぐ度そう不快に感じないのが不思議なほど汗でべたついた肌を快く撫でつけていく。