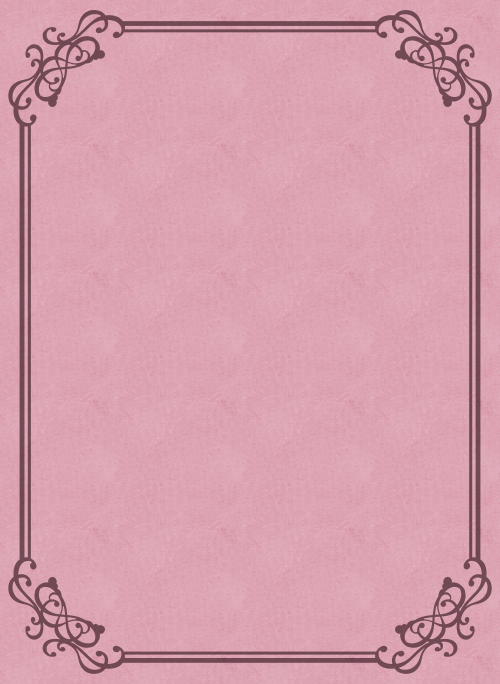「はああああ〜」
大きなため息をついて、僕はその場にしゃがみこんだ。
どうしてこのタイミングで泊まりの話を持ちかけるんだ。
また好きな人について問いただされたら、もう隠し通せる気がしない。
だとしたら僕は行かない方が身のためになるのでは。
そう頭ではわかっていても、本心は尊と一緒にいたくて仕方ない。
結局、本心に嘘を付くことはできず、僕は尊の家のインターホンを鳴らした。
直後、ダダダダッと階段を駆け下りる音がして、勢いよくドアが開いた。
そこには溢れんばかりの笑顔の尊がいて、僕のことを卑しいものとして見ているようには見えなかった。
ひとまず安心して尊の家に入った。
「お邪魔しまーす」