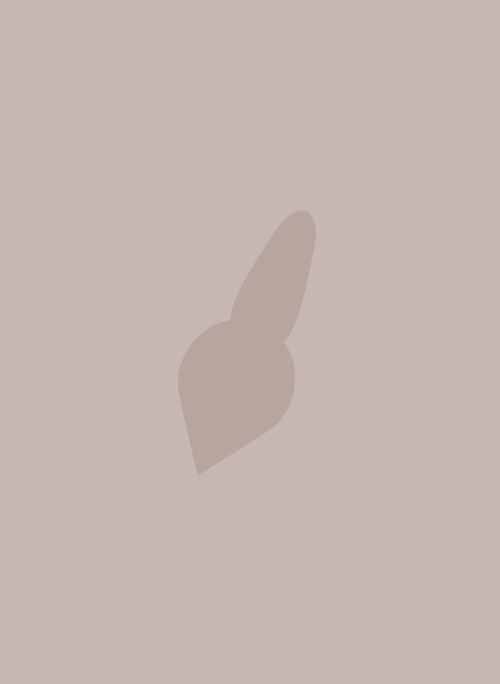そう言われて思い出した。最初に会ったときの彼女は泣いていた。まるでなにかに怯えるように。その姿が今にも崩れて消えてしまいそうで、手をさしのべざるを得なかった。
「あのとき大翔さんがハンカチをくれて声をかけてくれて…大翔さんがいなかったら私はここにいないかもしれない」
「そんな大袈裟な」
「いいえ。あのときの私にとって大翔さんは救いの手でしたから」
はっきりと言う彼女の瞳は真剣そのものだった。
「お前が俺を必要とするなら、俺はその救いになるよ」
気がつけばそんなことを言っていた。言ってから自分の言葉に驚いた。それは彼女も同じようで、目の前を見れば目を見開いて俺を見る彼女の姿。
「あのとき大翔さんがハンカチをくれて声をかけてくれて…大翔さんがいなかったら私はここにいないかもしれない」
「そんな大袈裟な」
「いいえ。あのときの私にとって大翔さんは救いの手でしたから」
はっきりと言う彼女の瞳は真剣そのものだった。
「お前が俺を必要とするなら、俺はその救いになるよ」
気がつけばそんなことを言っていた。言ってから自分の言葉に驚いた。それは彼女も同じようで、目の前を見れば目を見開いて俺を見る彼女の姿。