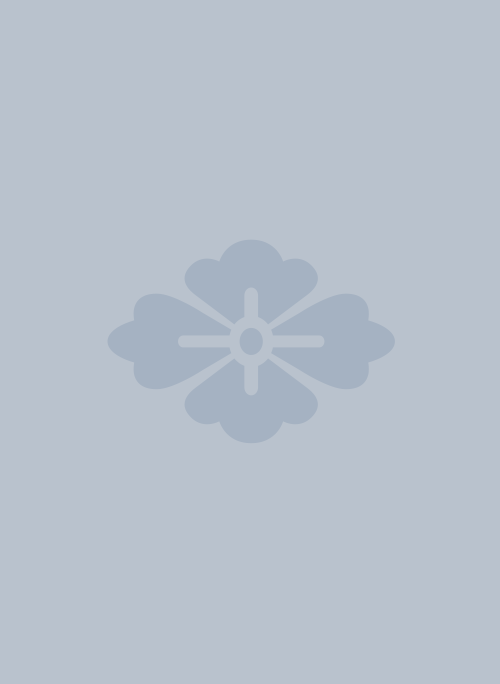「……」
「その手を血で紅く染める覚悟はあるのか?数え切れぬ屍の上を歩く覚悟が、貴様にあるのか」
さらに強く、首を絞められる。
くぐもった息を漏らしながらも、私は芹沢さんと視線を切らさない。
私にはもう他に選択肢はなかった。
この時代に身一つで放り出された今、頼れるのはこの人達だけなんだ。
もし、このまま無罪放免となって此処から釈放されたら、私はもう二度と太陽を拝むことが出来なくなるだろう。
治安が悪い京の都で、生きていく自信なんてこれっぽっちもないのだから。
芹沢さんの言う通り、此処に身を置く以上、毎日が生死の分岐点となり得る。
そして、直接ではないけれど、私は……【人殺し】に関わっていくんだ。
ーーそれでもいい。
「ーー此処で、働かせて下さい」
生きられるなら……どうなろうとも、構わない。
私は、芹沢さんの鋭い視線を弾き返すように、そう言った。
「……」
どのくらいの時間だったのか……。
数分、もしかしたら数秒だったかもしれない。
「……ふっ」
芹沢さんの引き締まった顔が、一瞬緩んだ。
それと同時に、手が離される。
締まっていた首元が一瞬にして解放され、酸素が一気に肺に入った。
軽く咳き込む。
手の甲で口元を拭いながら、芹沢さんを見上げると、彼は先ほどとは見違えるほど優しく笑った。
本当に笑ったかどうかは分からないけど、私には笑ったように見えた。
「ーーこれを持ていろ、いずれ必要になる」
芹沢さんは懐を探ると、短刀を私の前に投げ捨てた。
背筋が凍るような、そんな感覚が奔る。
私は静かに短刀を手に取ると、その重さを確かめるように手の平で小さく揺らした。
ズシリとした短刀本来の重み……それに命の重みが掌から直に伝わってくる。
『いずれ必要になる』
芹沢さんのあの言葉。
私が誰かを殺める時が来るということを言っているのか、それとも……。
「お前は今日から壬生浪士組の一員だ。我々の名に恥じぬよう、精進いたせ」
局長の顔でそう言うと、芹沢さんは腰を上げた。
「有難う、御座いますっ……」
私は短刀を握り締めて、部屋を出ていく彼の背中を見続けていた。