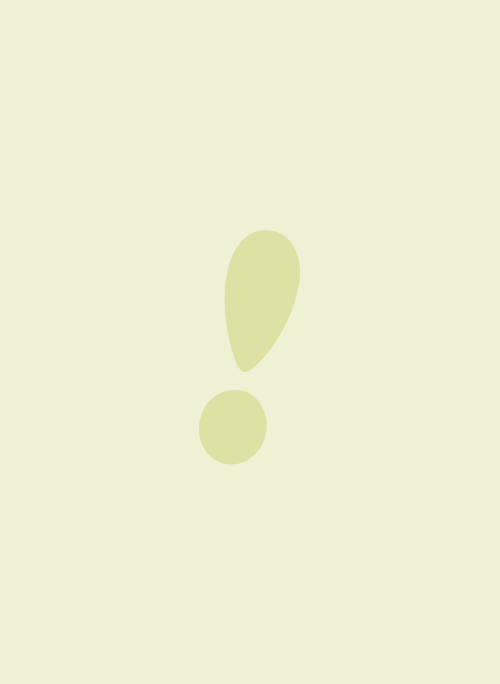「や、や、やややや」
「え?」
言葉にならない。摑まれた手を上手く振り払えない。
〝やめて〟と口を動かそうとするも、体は恐怖で言うことを聞かなかった。
ニヤリと妖しげな笑みを浮かべた男の子は、摑んだ腕に更にぎゅっと力をこめて私を立たせた。
「っ、」
「さ、行こっか?」
ニコリと人懐っこい笑みを私に向け、仲間の男の子に「行こうぜ」と声をかけた男の子は、気分上々で私を引き摺り始めた。
――どうやら、私の無言をOKと勘違いしたようだった。
「いや、いやいやいや」
ちょいとまってよ、そこのきみ。
軽く足を引き摺り抵抗の色を見せるも、男の子はそれに気づくことなく歩き続ける。
地面の砂埃が、真っ暗な夜でも分かるくらいに宙を舞った。
ばっと後ろを振り返ってみる。
どこかに電話をかけているのか、もう一人の男の子が携帯を片手に何やら話していた。
じっと見つめていると、私の視線に気づいたのか男の子は、ひらひらと手を振った。
そして、ニコリと微笑みかけられた私の顔は血の気が引いたように青ざめていった。