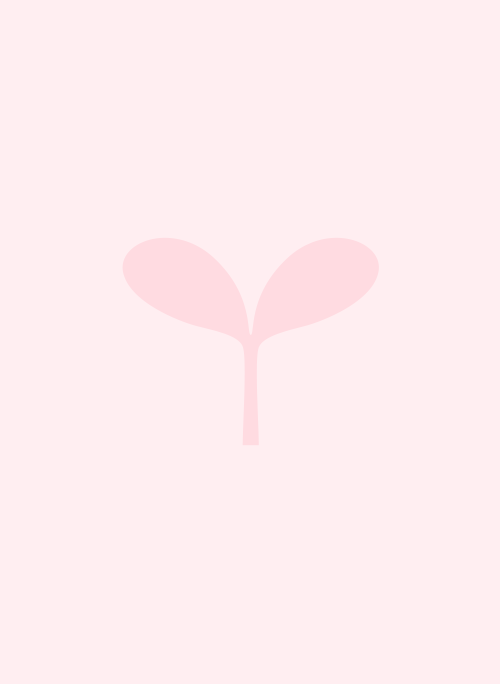放課後
珍しく早く帰ろうと思い、下駄箱の蓋を開けると1通の手紙が入っていた。
「なにこれ」
差出人なし…
『お前の秘密を知っている。日が暮れてから指定の場所に来い』
私は手紙を握りつぶした。
「舐めた真似を…」
夕暮れ
私は寂れた工場の跡に立っていた。ここが指定の場所だったからだ。人気は全くなく、灯りも見当たらない。
「せこい、これだから男は嫌いなのよ」
「独りで来たようだな。度胸は一人前だなぁ」
中には20人ばかりの男達がいた。
「汚らわしい…」
服装を見ると、うちの制服だ。
「まぁ、座れよ」
「結構よ、用件だけいいなさい」
「これに身に覚えがあるだろ?」
私はある写真を見せられた。
それは、私が悠里にキスされたときの写真だった。
「なんで…」
「くくくっ」
「この写真で私を揺すろうってことね…。何が望みなのかしら?」
「俺達は昔、あんたに世話になった奴等でな。望みはお前をひざまずかせることだ」
私は男たちの顔を見渡した。
通りで見たことのある顔だと思った。制服は盗んだのか。
「どのカメラで撮ったのかしら」
「これだよ」
と、一人の男がカメラを掲げた。
「ふむ…、ならここにいるやつ全員潰せばいいのね」
「なんだと?」
「行くわよっ」
私は予め持っておいた細い鉄パイプを片手に走り出した。
「はぁっ!」
1人の顎目掛けて下から思いっきりパイプをぶちこむ。
「1人目っ」
今度は5人、束になって掛かってくる。
「男が女によってたかって…」
「情けないっっ」
パイプを横になぶって、首に命中させる。
「ほらほら、さっさと掛かってきなさいよ」
私がまた襲い掛かろうとすると、腰の辺りに鈍い痛みが走った。
「っく…」
つい、膝をついてしまった。もう、立ち上がれそうになかった。
それどころか、意識までも遠退いて……
暗転
珍しく早く帰ろうと思い、下駄箱の蓋を開けると1通の手紙が入っていた。
「なにこれ」
差出人なし…
『お前の秘密を知っている。日が暮れてから指定の場所に来い』
私は手紙を握りつぶした。
「舐めた真似を…」
夕暮れ
私は寂れた工場の跡に立っていた。ここが指定の場所だったからだ。人気は全くなく、灯りも見当たらない。
「せこい、これだから男は嫌いなのよ」
「独りで来たようだな。度胸は一人前だなぁ」
中には20人ばかりの男達がいた。
「汚らわしい…」
服装を見ると、うちの制服だ。
「まぁ、座れよ」
「結構よ、用件だけいいなさい」
「これに身に覚えがあるだろ?」
私はある写真を見せられた。
それは、私が悠里にキスされたときの写真だった。
「なんで…」
「くくくっ」
「この写真で私を揺すろうってことね…。何が望みなのかしら?」
「俺達は昔、あんたに世話になった奴等でな。望みはお前をひざまずかせることだ」
私は男たちの顔を見渡した。
通りで見たことのある顔だと思った。制服は盗んだのか。
「どのカメラで撮ったのかしら」
「これだよ」
と、一人の男がカメラを掲げた。
「ふむ…、ならここにいるやつ全員潰せばいいのね」
「なんだと?」
「行くわよっ」
私は予め持っておいた細い鉄パイプを片手に走り出した。
「はぁっ!」
1人の顎目掛けて下から思いっきりパイプをぶちこむ。
「1人目っ」
今度は5人、束になって掛かってくる。
「男が女によってたかって…」
「情けないっっ」
パイプを横になぶって、首に命中させる。
「ほらほら、さっさと掛かってきなさいよ」
私がまた襲い掛かろうとすると、腰の辺りに鈍い痛みが走った。
「っく…」
つい、膝をついてしまった。もう、立ち上がれそうになかった。
それどころか、意識までも遠退いて……
暗転