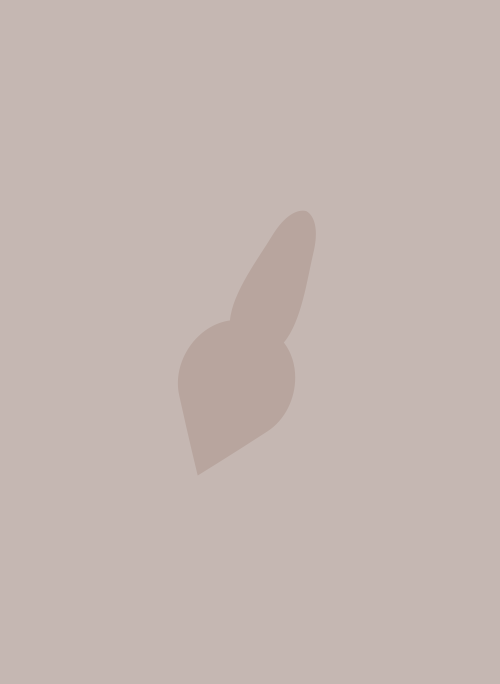酔った勢いなのか、普段の自分なら絶対にしない行動をしてしまう。
掌に戻されたキャラメルを摘み上げて、辻堂さんの口元に運ぶ。
「口、開けてください」
私の言葉に驚いたのか、ほんの少しあいた唇の間にキャラメルをそっと押しこんだ。
「変なものは入っていませんから」
小さくそれだけ言うと、辻堂さんの口の中に消えかかったキャラメルを手放す。その時にほんの少しだけ触れた唇の暖かさに一気に体温が上昇した。
「それに、それに、食べたときに上を向きます。おいしいものを食べたら笑顔になります。だから、下を向くよりもいいことが起きます。下を向いてたら、いいことも目の前を通り過ぎちゃうから、だから…」
自分で言っていることがわからなくなってうつむいてしまう。
下を向いてほしくない。
おいしいものを食べて笑ってほしい。
少しでも元気になってほしい。
「おいしいね」
何を言っていいのかわからなくって、下を向いていた私に辻堂さんがやさしく声をかけてくれた。
「もう一個もらってもいい?」
「は、はい」
もう一個という言葉にうれしくなって、急いで紙袋の中から取り出して、手の上に置く。
「高校生?」
2個目を口に含んだ辻堂さんが、ふとそんな声を漏らした。
その問いかけに、横に頭を振ってから小さな声で「大学生です」と答える。
「なら、いっか。時間があるなら聞いてもらおうかな」
小さく笑うと、ベンチの空いたスペースを指さしながら私に座るように促した。
ゆっくりと腰を下ろせば、手を届くところに好きな人がいる。
今までにないその距離に、夢ではないかと思えてしまう。
掌に戻されたキャラメルを摘み上げて、辻堂さんの口元に運ぶ。
「口、開けてください」
私の言葉に驚いたのか、ほんの少しあいた唇の間にキャラメルをそっと押しこんだ。
「変なものは入っていませんから」
小さくそれだけ言うと、辻堂さんの口の中に消えかかったキャラメルを手放す。その時にほんの少しだけ触れた唇の暖かさに一気に体温が上昇した。
「それに、それに、食べたときに上を向きます。おいしいものを食べたら笑顔になります。だから、下を向くよりもいいことが起きます。下を向いてたら、いいことも目の前を通り過ぎちゃうから、だから…」
自分で言っていることがわからなくなってうつむいてしまう。
下を向いてほしくない。
おいしいものを食べて笑ってほしい。
少しでも元気になってほしい。
「おいしいね」
何を言っていいのかわからなくって、下を向いていた私に辻堂さんがやさしく声をかけてくれた。
「もう一個もらってもいい?」
「は、はい」
もう一個という言葉にうれしくなって、急いで紙袋の中から取り出して、手の上に置く。
「高校生?」
2個目を口に含んだ辻堂さんが、ふとそんな声を漏らした。
その問いかけに、横に頭を振ってから小さな声で「大学生です」と答える。
「なら、いっか。時間があるなら聞いてもらおうかな」
小さく笑うと、ベンチの空いたスペースを指さしながら私に座るように促した。
ゆっくりと腰を下ろせば、手を届くところに好きな人がいる。
今までにないその距離に、夢ではないかと思えてしまう。